文字
背景
行間
建築デザイン系の日々
「国家試験」合格発表(建築デザイン系)
令和6年7月10日(水)AM9時に2級建築施工管理士(第一次検定)の合格発表がありました。
【2級建築施工管理士(第一次検定)】
令和6年6月9日(日)に実施されました。毎年、建築デザイン科3年生は学習の総仕上げとして11月の後期受検をしていましたが、今年は6月の前期受検に挑みました。
【2級土木施工管理士(第一次検定)】
今までは建築デザイン科では2級土木施工管理士を受検していませんでしたが、現3年生は2年生の時に希望者が11月(後期受検)で2級土木施工管理士(第一次検定)を受検しました。令和6年6月(前期試験)には、その時の未受検者が受検しました。
【測量士補】
希望者10名が放課後の補習を受け、測量士補試験を受検しました。
●3年生(39名)の合格率と全国合格率
<試 験 名> <受検日> <受検者数><合格者数><合格率(%)><全国合格率(%)>
2級建築施工管理士(第一次検定) 令和6年 6月 39 36 92.3 48.2
2級土木施工管理士(第一次検定) 令和6年 6月 5 3 60.0 43.0
2級土木施工管理士(第一次検定) 令和5年11月 34 29 85.3 50.6
測量士補 令和6年 6月 10 6 60.0 32.2
国家資格の前期試験は6月に集中しているため、二つの資格試験を受検した生徒は大変でした。今回の不合格者は11月(後期日程)に行われる2級建築施工管理士後期試験を受検する予定です。
2級建築施工管理士(第一次検定)・2級土木施工管理士(第一次検定)・測量士補すべてに合格した生徒人数は、6名です。
「課題研究」の学び・その1(建築デザイン科3年)
令和6年度の建築デザイン科課題研究(3年生)は、4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。栃木県総合運動公園内倉庫に使われずに保管してあった移動式能舞台に新しいデザインを加え1/2の縮尺で再現しています。
<主な研究内容>
●製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作
●装飾班 ・・・内装のデザイン・製作
●設計班 ・・・BIMを使用し設計
●研究発表班・・・能舞台の研究・発表
進捗状況をお知らせします。第1回は 製作班の鏡板製作 です。
栃木県総合運動公園の倉庫に保管してあった能舞台の鏡板をモデルに、松の絵をデザインし1/2の縮尺で製作を始めました。


保存してあった鏡板 下絵描き作業 塗装作業
教育実習生によるホームルーム(建築デザイン科)
令和6年6月3日(月)~令和6年6月14日(金)まで、2名の大学生が建築デザイン科にて教育実習を実施しています。1年生と2年生のクラスにおいてホームルームと専門の授業を担当してもらいました。また、研究授業では、創意工夫が凝らされた授業が展開されました。

建築デザイン科2年にてのHR 建築デザイン科1年にてのHR
みやJOY2024~けんちく博~ボランティア活動(建築デザイン科)
一般社団法人栃木県建築士会が主催する「みや JOY2024~けんちく博~」(於:ライトキューブ宇都宮)に、2年生28名と1年生15名が、ボランティア活動を行いました。

ボランティア活動の様子1 ボランティア活動の様子2
建築デザイン科3年 建築製図による住宅設計と町並み模型
建築デザイン科3年生では、建築製図の授業で木造2階建て専用住宅の設計や模型製作に取り組んでいます。今年度は、宇工高西側の敷地を住宅地と見立てて、抽選によって割り当てられた敷地にそれぞれが諸条件のもと住宅を設計しました。住宅のプランニングや基本図面の作成、模型やプレゼンテーション図面の作成などに取り組み、1年間の成果としてそれぞれの模型が敷地に配置され、新たな町並みを模型で表現することができました。



生徒達は細部までこだわって作品製作に取り組みました。
建築デザイン科3年生 施設見学会
1月18日(木)に建築デザイン科3年生の施設見学会を実施しました。
東京、上野駅周辺の有名建築家の設計による建築物や歴史的建築物などを見学し、都市空間を体験することで、建築に関する知見を深めました。
国立西洋美術館(設計:ル・コルビュジェ)にて記念撮影
建築デザイン科 課題研究発表会
1月16日(火)に建築デザイン科の課題研究発表会を実施しました。
3年生で取組む課題研究は、1年間の研究を通して、建築に関する知識や技術だけでなく、主体的に研究を進めるための総合的なスキルを向上させます。
○発表の様子


○発表テーマ(発表順)
・養蜂箱作り ・学習環境改善の取り組み ・THE GATE
・建築模型の表現に関する研究 ・宇工祭の物品販売 ・建築設計競技への挑戦
・The 陶壁
令和3年度 建築デザイン科 課題研究発表会


小砂消臭壁の完成(建築デザイン科)

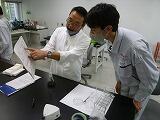







2級建築施工管理技術検定 建築系就職内定生徒合格100%達成!








