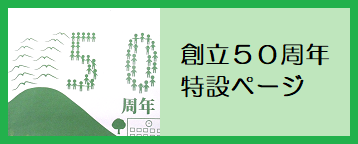文字
背景
行間

2
2
4
8
6
7
6
日誌
自然いっぱいコーナー
アケビの仲間たち
7月14日(火) 校庭のアケビ棚を見ると、小さなアケビの実がなっていました。そういえばアケビの種類ってどれくらいあるんだろうと思い調べてみました。

アケビの仲間には、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類があるそうです。本校のアケビは、小葉5枚からなる掌状複葉で、小葉は楕円形で縁にギザギザ(きょ歯)がないため、アケビであることが明らかです。

校庭の植物をいろいろ調べてみると楽しいですね。

アケビの仲間には、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類があるそうです。本校のアケビは、小葉5枚からなる掌状複葉で、小葉は楕円形で縁にギザギザ(きょ歯)がないため、アケビであることが明らかです。

校庭の植物をいろいろ調べてみると楽しいですね。
山崎宇宙飛行士と宇宙を旅しました!
7月7日(火) 校庭の片隅にある課外活動の花壇から、かわいいカボチャの双葉が顔を出していました。これは、6月25日(木)、課外活動の時間にまかれた宇宙を旅したカボチャです。
この種は、山崎直子宇宙飛行士の公式記念品(OFK)として宇宙を旅しました。

そして、こちらは宇宙を旅したアサガオです。「NAOKO☆アサガオ」と呼ばれており、「やさしさ」「おもいやり」『きぼう』を育てることをねらいとしています。さらには、いのちを育てることの大切さを学んでもらいたいという大きな願いも込められています。

この種は、山崎直子宇宙飛行士の公式記念品(OFK)として宇宙を旅しました。

そして、こちらは宇宙を旅したアサガオです。「NAOKO☆アサガオ」と呼ばれており、「やさしさ」「おもいやり」『きぼう』を育てることをねらいとしています。さらには、いのちを育てることの大切さを学んでもらいたいという大きな願いも込められています。

ヒヨドリのひな誕生!
6月8日(月) 学校中庭に作られたヒヨドリの巣を観察しました。
先日、御紹介した時は4個の卵がありました。昨年のひなの数も4匹、そして今日4匹のひなが確認されました。ヒヨドリは、シジュウカラなどの小型の鳥よりも身体が大きいためか、卵も4つくらいが適当なのかも知れません。(本校の児童生徒によるシジュウカラの観察では、6個~11個までの記録があります)
今年も無事に巣だってほしいですね。そしてまた来年も同じ木で繁殖してほしいと願っています。

先日、御紹介した時は4個の卵がありました。昨年のひなの数も4匹、そして今日4匹のひなが確認されました。ヒヨドリは、シジュウカラなどの小型の鳥よりも身体が大きいためか、卵も4つくらいが適当なのかも知れません。(本校の児童生徒によるシジュウカラの観察では、6個~11個までの記録があります)
今年も無事に巣だってほしいですね。そしてまた来年も同じ木で繁殖してほしいと願っています。

ユスラウメの赤い実
「ユスラウメの実が美味しそうでしたね」 本校の交流運動会(5月30日)、生徒を引率して来校してくださいました交流校の先生のお話。「食べたかったけど、悪いと思って・・・」そう言いながら昔をなつかしんでいました。
小学生の頃、通学路になっていた果物たちの一つに、このユスラウメがありました。ちょっとサクランボに似た味がします。
このコーナーで、ユスラウメの実を御紹介するのは初めてです。あっと言う間に小鳥が食べてしまうためか、あまり目立たなかったようです。

小学生の頃、通学路になっていた果物たちの一つに、このユスラウメがありました。ちょっとサクランボに似た味がします。
このコーナーで、ユスラウメの実を御紹介するのは初めてです。あっと言う間に小鳥が食べてしまうためか、あまり目立たなかったようです。

ブルーベリーのお話
5月29日(金) 運動会を明日に控えた校庭の片隅の「野鳥の庭」。ブルーベリーが実を付け始めました。このブルーベリーは、結実を促進するために、ハイブッシュ系とラビットアイ系の2品種が植樹されています。
ブルーベリーに適した用土は、pH4,3~5,5という強い酸性土です。ピートモス(カナダの水苔を腐熟させた園芸資材)などを土にすき込みます。
児童生徒のみなさん、今年も小鳥たちに負けないように、甘い果実を楽しんでくださいね。

ブルーベリーに適した用土は、pH4,3~5,5という強い酸性土です。ピートモス(カナダの水苔を腐熟させた園芸資材)などを土にすき込みます。
児童生徒のみなさん、今年も小鳥たちに負けないように、甘い果実を楽しんでくださいね。

今年は防水性?の巣だ!
5月26日(火) 中庭にあるツバキの木に、今年もヒヨドリが巣を作りました。巣をそっとのぞいてみると、卵が4つ産み付けられていました。親鳥はまだ卵を温めていません。小鳥たちは、強い猛禽類とは異なり、卵を多く産みます。そして、卵を同時に孵化させるために、最終卵を産んでから卵を抱き始めます。雛たちを均一に育てるための工夫なんですね。
その点、タカやフクロウなどの猛きん類は、卵を1~2個しか産まず、第1卵から卵を抱き始めてしまいます。(強い雛しか育てません )しかし、小鳥たちは、厳しい生存競争を生き抜かなければならず、多くの卵を産んで、効率よく、しかも速やかに巣立ちさせる合理的な方法を選択しています。
ところで、今年の巣を下から見ると、なんとビニール袋が使われています。防水のためなんでしょうか? 雨がたまって、その重さで巣が落ちなければいいのですが・・・。
スイレンとミカンの花
ビオトープのスイレンの花が咲きました。このビオトープは、すでに御紹介のとおり、平成8年度に当時の観察池を改造して作られたものです。前回のヤゴのお話は、このビオトープで繁殖したギンヤンマのことでした。
「先生、スイレンとハスってどう違うの?」 「・・・なんでハスの花の上に仏像がいるの?」昔なつかしい生徒との会話を思い出しました。
ミカンの花も咲いていました。今年は、昨年より早い開花だったようです。今年の秋も甘いミカンが食べられそうですね。



「先生、スイレンとハスってどう違うの?」 「・・・なんでハスの花の上に仏像がいるの?」昔なつかしい生徒との会話を思い出しました。
ミカンの花も咲いていました。今年は、昨年より早い開花だったようです。今年の秋も甘いミカンが食べられそうですね。



ミズアオイの種まきをしました。
総合的な学習の時間「チャレンジタイム」において、小学部の児童たちによって「ミズアオイ」の種まきが行われました。昨年度に見事な花を咲かせた株からとった種をまきました。
このミズアオイの栽培は、平成8年度から始められました。当時は絶滅危惧植物の保護を通して、障害のある児童生徒たちの「生きる力」を育てることを目的としていました。
今年度は、野鳥の観察やメダカの飼育などを通して、もう一度原点に立ち返り、生命について考えてみるよい機会とします。


このミズアオイの栽培は、平成8年度から始められました。当時は絶滅危惧植物の保護を通して、障害のある児童生徒たちの「生きる力」を育てることを目的としていました。
今年度は、野鳥の観察やメダカの飼育などを通して、もう一度原点に立ち返り、生命について考えてみるよい機会とします。


♪ メダカの学校は ♪
本校の玄関に設置されているアクアリウム(120×45×45㎝)に、新しいメダカ(約40匹)がやってきました。今年度の環境教育推進委員会の活動テーマのひとつであるメダカの繁殖、児童生徒たちの活躍が期待されています。

赤、青、黄色のメダカたち、とても元気です。

赤、青、黄色のメダカたち、とても元気です。
ビオトープで発見!!
ゴールデンウィーク明けの木曜日、学校中庭のビオトープにてヒメガマの葉につかまった虫の抜け殻を発見しました。


体長を測ると約5cm、この日だけで5匹発見しました。小学部の子供たちも大きさにびっくりしていました!図鑑によると種類はギンヤンマ、成虫になると9cmほどにまで成長するようです。
ギンヤンマは幼虫で越冬し、大きくなるとメダカやオタマジャクシも捕食します。十分に成長した幼虫は4月の終わりから5月にかけて、成虫への脱皮を行います。夜に脱皮した成虫は朝早くまで、じっと動かず羽や腹が固くなるのを待つので、朝早くビオトープをのぞくと脱皮したての成虫を見ることができるかもしれません。


体長を測ると約5cm、この日だけで5匹発見しました。小学部の子供たちも大きさにびっくりしていました!図鑑によると種類はギンヤンマ、成虫になると9cmほどにまで成長するようです。
ギンヤンマは幼虫で越冬し、大きくなるとメダカやオタマジャクシも捕食します。十分に成長した幼虫は4月の終わりから5月にかけて、成虫への脱皮を行います。夜に脱皮した成虫は朝早くまで、じっと動かず羽や腹が固くなるのを待つので、朝早くビオトープをのぞくと脱皮したての成虫を見ることができるかもしれません。
学校風景
連絡先
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町619-1
電話 0284-91-1110
FAX 0284-91-3660
ナビを利用して本校に来校される場合には、
「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。
リンクリスト