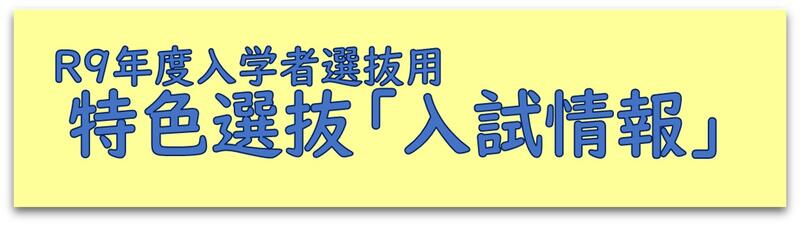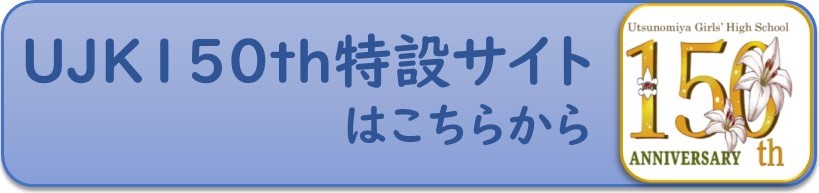文字
背景
行間
SSH日誌
Skype交流
Skype交流
平成27年6月23日(火)、9月7日(月)、8日(火)
生物講義室
2年SSクラス希望者、1年希望者
■第2回 | 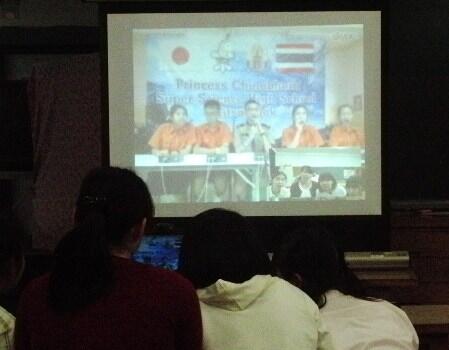 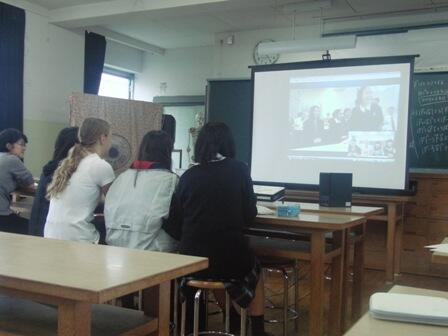  |
積極的にコミュニケーションをとろうとする姿勢はあるが、現在は毎回異なる生徒が参加しているため、継続的な交流が難しい。オーストラリアとは手紙による交流もスタートしたが、今後はより継続性のある交流をする工夫と、英語力の強化も必要である。
【生徒の感想】
・楽しく話せてよい経験になった。話そうと思ったことがうまく伝えられなかった。
・相手の話すことを聞き取ることが難しかった。
・とても難しかったが、お互いにわかり合えたときのうれしさを実感することができた。
・原稿を用意してそちらばかり見てしまった。
・直接会って話したいと思った。
・相手の国のことをもっと知りたいと思った。
・相手の話がわからないのが悔しかった。
・もっと準備をしっかりすればよかった。
・コミュニケーション力、判断力、計画力などいろいろ足りないところに気づいた。
・一方的に話して、相手の確認を怠ってしまった。
・もっと自分から積極的に話した方がよかった。
・ゆっくり話すことが大切。文法を気にしすぎて黙ってしまった。
※十分な準備ができず、思ったように話すこともできなかったと悔いが残る一方で、貴重な体験をしたので、次はもっとしっかりやりたいとか、もっと多く交流したいという意欲やモチベーションを高めた生徒が多かった。
日本生物学オリンピック2015本選(広島大会)
日本生物学オリンピック2015本選
平成27年8月20日(木)~23日(日)
広島大学 総合科学部
3年生 1名 |
7月に行われた日本生物学オリンピック予選において優秀な成績を収め、本校より1名が広島大学で行われた全国大会に出場した。
SSH指定女子高校研究交流会
SSH指定女子校研究交流会
平成27年8月11日(火)
お茶の水女子大学
群馬県立前橋女子高等学校
(1) 日程 1.開会行事 |  |
大学の先生、学生、他校の生徒など、様々な立場からの貴重な話を聞くことができ、有意義な交流会となった。
【生徒の感想】
・他校のSSHの研究内容について情報交換ができ、新しい考えや参考になることをたくさん知ることができよかった。
・現役の大学生や院生に直接質問できたことが良かった。
・准教授の講演や大学院生による講義では、発表方法がとても参考になった。
・これから線形代数学のテーマを決めるにあたり、数学はいろいろな分野に使えることがわかり参考になった。
・プログラミングの体験がとても楽しく進路の参考になった。
・大学院生に自分たちの研究のアドバイスをもらえてよかった。
・普段は交流ができない他の女子校の生徒と理系の勉強の話や学校生活の話などを聞くことができ楽しい時間が過ごせた。
・他県の女子校の生徒と話すことで研究に対するモチベーションが上がった。
・大学生から研究についての改善点や体験談を多く聞くことができてよかった。
・一浪した先輩、米国の高校から入学した先輩、他の大学から3年に編入した先輩など、いろいろな立場での話が聞けてよかった。
ウィルス学体験講座
ウィルス学体験講座
平成27年8月7日(金) 13:00~17:00
獨協医科大学病院
2年生希望者
|   |
【生徒の感想】
・電子顕微鏡で細胞小器官が見られて良かった。熟練の技で研究が進められることが分かった。
・ウイルスに関する興味が増し、理解が深まった。
・電子顕微鏡を覗かせてもらったり、高校ではできない実験などができ貴重な体験であった。
・先生方の体験談が興味深く、自分の進路を考えるうえで参考になった。
平成27年度生徒研究発表会(大阪)
平成27年度 SSH生徒研究発表会 (大阪)
平成27年8月5日(水)、6日(木)
インテックス大阪
3年生 2名(ポスター発表)
(1) 日程 8月5日(水) |   |
他校の工夫を凝らしたポスター発表やプレゼンテーションに触れ、刺激を受けるとともに、これからの研究を進める上で大いに参考になった。
【生徒の感想】
<生徒感想>
・どの学校の発表もすごく工夫されていて、自分が研究を進める上での参考になった。
・実験が仮説通りにいかなかったときの考察の立て方が参考になった。
・プレゼンテーションの方法、質問する際の着眼点など、参考になった。
・この研究が社会にどう役立つのかなどといった目的をはっきりさせることや、地道なことを繰り返し行って確実な結果を得ることの大切さなどを学んだ。
・専門用語が多くて理解しにくい研究もあったが、多くが関心のもてる内容であった。
・資料だけではよくわからない研究成果を動画で詳しく見せてくれる研究があり面白かった。
・ポスターを全文英語で書いて、発表も全て英語で行っている学校が何校かあり見習わないといけないと思った。
・身近なものを研究テーマにしている高校多かったので、自分たちで研究テーマを見つけられるようにしたい。
・ステージ発表に選ばれた研究は、選ばれるだけあって、どれもおもしろい研究であった。
・自分たちの研究を熟知しているためか、質疑応答にもスムーズに対応している発表が多く見習いたい。
・海外の学生もこの発表会に多く参加しており、世界では同年代の学生が非常に高いレベルで研究を行っていることを知り驚いた。