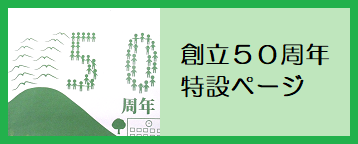文字
背景
行間

2
2
5
2
4
6
9
日誌
自然いっぱいコーナー
第5期「野鳥の庭」工事始まる!
平成23年度から始められた「野鳥の庭」整備計画は、
今回で5回目を迎えました。
今回の工事は、プール西側に植樹された
温州ミカンの縁石工事です。
これは、第1回(平成23年度)整備工事の一環として
植樹されたものです。
これらの工事は、いずれも
(公益社団法人)とちぎ環境・みどり推進機構の支援に
よるものです。
この温州ミカンは、昨年から多くの実をつけはじめ、
17年前に植樹された校庭のみかんとともに味わわれています。
今回で5回目を迎えました。
今回の工事は、プール西側に植樹された
温州ミカンの縁石工事です。
これは、第1回(平成23年度)整備工事の一環として
植樹されたものです。
これらの工事は、いずれも
(公益社団法人)とちぎ環境・みどり推進機構の支援に
よるものです。
この温州ミカンは、昨年から多くの実をつけはじめ、
17年前に植樹された校庭のみかんとともに味わわれています。

「野鳥の庭」の工事完了!
11月18日(水) 「野鳥の庭」の縁石造成工事
(周長23m)が完了しました。
これは、「ふるさととちぎみどりづくり事業」として
実施されたもので、公益社団法人
とちぎ環境・みどり推進機構の支援による
「大塚実みどりの基金」を活用させていただいたものでです。

きれいに整えられた「野鳥の庭」で、児童生徒たちが、
安心で安全な自然観察が行えるようになりました。
(周長23m)が完了しました。
これは、「ふるさととちぎみどりづくり事業」として
実施されたもので、公益社団法人
とちぎ環境・みどり推進機構の支援による
「大塚実みどりの基金」を活用させていただいたものでです。

きれいに整えられた「野鳥の庭」で、児童生徒たちが、
安心で安全な自然観察が行えるようになりました。
果物屋さん !でしょうか ?
11月12日(木) 職員室の廊下に、
かわいい果物屋さん ?が・・・。
果物の名前が書かれた名札と、「学校の庭でとれました」という
看板がついていました。
高等部の生徒が、先生と一緒に飾ってくれたそうです。
この果物の中に、バレンシアオレンジがありますが、
平成11年度に、プール東側にある「ちょうの里」に植樹され、
近年ようやく実をつけはじめました。
本校は、いろいろな果物が楽しめる、とても楽しい校庭があります。
かわいい果物屋さん ?が・・・。
果物の名前が書かれた名札と、「学校の庭でとれました」という
看板がついていました。
高等部の生徒が、先生と一緒に飾ってくれたそうです。

この果物の中に、バレンシアオレンジがありますが、
平成11年度に、プール東側にある「ちょうの里」に植樹され、
近年ようやく実をつけはじめました。
本校は、いろいろな果物が楽しめる、とても楽しい校庭があります。
「野鳥の庭」の工事はじまる!
11月9日(月) 校庭の「野鳥の庭」の工事が始まりました。
これは、「野鳥の庭」の縁石工事で、
周長約23mのブロック積花壇が造成されます。

この工事は、公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構による
「ふるさととちぎみどりづくり事業」として実施されています。

上の写真の左側には、昨年度に完成したブルーベリーを
囲む縁石があり、
今回の工事は、乙女ツバキやユスラウメなどが
植樹されているエリアです。
この観察フィールドは、初めて「野鳥の庭」として誕生し、
本校における環境教育の原点とも言える場所です。
これは、「野鳥の庭」の縁石工事で、
周長約23mのブロック積花壇が造成されます。

この工事は、公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構による
「ふるさととちぎみどりづくり事業」として実施されています。

上の写真の左側には、昨年度に完成したブルーベリーを
囲む縁石があり、
今回の工事は、乙女ツバキやユスラウメなどが
植樹されているエリアです。
この観察フィールドは、初めて「野鳥の庭」として誕生し、
本校における環境教育の原点とも言える場所です。
ミズアオイの種ができました。
小学部の児童たちが、春から大切に育ててきたミズアオイ。
今年も、たくさんの種ができました。

このミズアオイは、10月になると、
結実した実が枝からはずれて、
下に落ち出します。
水面に落ちた実は、成熟すると自然にはじけて種を放出します。

来年も、きれいな花が咲いてくれることでしょう。
今年も、たくさんの種ができました。

このミズアオイは、10月になると、
結実した実が枝からはずれて、
下に落ち出します。
水面に落ちた実は、成熟すると自然にはじけて種を放出します。

来年も、きれいな花が咲いてくれることでしょう。
今年もミズアオイが育ちました
小学部のみなさんが育てたミズアオイ、
今年もきれいに咲きました。

そして、このビオトープに、
栃木県県南環境森林事務所からいただいた
プランターが設置されました。

今年もきれいに咲きました。

そして、このビオトープに、
栃木県県南環境森林事務所からいただいた
プランターが設置されました。

秋を感じて!
10月8日(木) 自然観察部のみなさんが学校周辺の秋を
お届けします。
最初にご紹介するのは、校庭の南側にある「野鳥の庭」の
あけび棚です。たくさんの実をつけてくれました。

そしてこれは、プール南側にある「ちょうの里」に植樹されて
いるレモンです。「すっぱい香りが大好き!」一つもぎってみま
した。

今度は、学校の裏山にある「ほたる沢公園」を散歩しました。
「秋の七草!・・・ススキ」 先日の朝礼で聞いた校長先生の
お話を覚えていました。思わず二人で記念撮影!?

ほたる沢公園北側では、ダム工事が進められています。

沢の中をのぞくと、アメンボが泳いでいました。「次は網を
持ってすくってみよう!」と大はしゃぎでした。

お届けします。
最初にご紹介するのは、校庭の南側にある「野鳥の庭」の
あけび棚です。たくさんの実をつけてくれました。

そしてこれは、プール南側にある「ちょうの里」に植樹されて
いるレモンです。「すっぱい香りが大好き!」一つもぎってみま
した。

今度は、学校の裏山にある「ほたる沢公園」を散歩しました。
「秋の七草!・・・ススキ」 先日の朝礼で聞いた校長先生の
お話を覚えていました。思わず二人で記念撮影!?

ほたる沢公園北側では、ダム工事が進められています。

沢の中をのぞくと、アメンボが泳いでいました。「次は網を
持ってすくってみよう!」と大はしゃぎでした。

ぼくの夏休み Vol.2
8月4日(火) 学校ビオトープの隣に植樹されているエゴノキに、
たくさんの実がついていました。
この木には、秋になるとヤマガラが毎日訪れて、
この実をくわえて巣に運びます。
真冬の非常食になるようです。
この実をつぶしてみると、泡だって洗剤の代わりになることも、
生活の知恵として昔から伝えられています。

巣箱をかけた学校裏山
(あしかがの森 足利病院 ほたる沢公園)を散歩しました。
今年もたくさんの小鳥たちが巣だっていきました。

現在、この「ほたる沢公園」の北側では、
土石流に備え砂防堰堤(さぼうえんてい)工事が行われています。
(幅57m 高さ7.9m)
卒業生の皆さんへ: フクロウ用の巣箱が工事範囲内に
かかってしまいましたので 取り 外し ました。
ところで、堰堤(えんてい)とは何でしょう。

簡単に言えば、小さいダムのことで、
高さが10m以内のものを堰堤(えんてい)と呼ぶそうです。
(監督さんが親切に教えてくれました)
この工事は、平成27年11月まで行われる予定です。
(西越床沢 足利市大沼田町)
御覧のように、木々も伐採されてしまい、
クワガタ虫やカブト虫がいた木もなくなってしまいましたが、
私たちの安全な生活確保と自然環境保護について考える
良い機会としたいですね。
たくさんの実がついていました。
この木には、秋になるとヤマガラが毎日訪れて、
この実をくわえて巣に運びます。
真冬の非常食になるようです。
この実をつぶしてみると、泡だって洗剤の代わりになることも、
生活の知恵として昔から伝えられています。

巣箱をかけた学校裏山
(あしかがの森 足利病院 ほたる沢公園)を散歩しました。
今年もたくさんの小鳥たちが巣だっていきました。

現在、この「ほたる沢公園」の北側では、
土石流に備え砂防堰堤(さぼうえんてい)工事が行われています。
(幅57m 高さ7.9m)
卒業生の皆さんへ: フクロウ用の巣箱が工事範囲内に
かかってしまいましたので 取り 外し ました。
ところで、堰堤(えんてい)とは何でしょう。

簡単に言えば、小さいダムのことで、
高さが10m以内のものを堰堤(えんてい)と呼ぶそうです。
(監督さんが親切に教えてくれました)
この工事は、平成27年11月まで行われる予定です。
(西越床沢 足利市大沼田町)
御覧のように、木々も伐採されてしまい、
クワガタ虫やカブト虫がいた木もなくなってしまいましたが、
私たちの安全な生活確保と自然環境保護について考える
良い機会としたいですね。
ぼくの夏休み!
8月3日(月) 学校の裏山では、いよいよツクツクボウシがセミの合唱隊に加わってきました。セミの仲間は、日本には35種類もいるそうですが、学校周辺では、春ゼミ、ニイニイゼミ、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミ、ヒグラシ、ツクツクホウシの順番で鳴き始めるようです、ちょうど今頃は、最もにぎやかな混声合唱が聞こえてきます。

野鳥の庭のカキの木の下には、小さな穴ぼこがたくさん開いていました。これは・・・?

そうです、セミの幼虫が地中から出てきた穴なんですよ。まだ穴の中に幼虫がいる時は、大豆ほどの小さな穴です。少年の頃は、この穴にたくさんの水を入れて、幼虫を中から出してつかまえました。夜になってその幼虫を蚊帳(かや)の中に入れておくと、朝には立派なセミになっているのです。

シオカラトンボも飛んでいました。そして、アキアカネが校庭を舞い始める頃、楽しかった夏休みもいよいよ終盤を・・・。
先生、そう話をいそがないでくださいよ! という児童生徒のみなさんの声が聞こえてきそうなので今回はこれくらいにしておきましょう。

野鳥の庭のカキの木の下には、小さな穴ぼこがたくさん開いていました。これは・・・?

そうです、セミの幼虫が地中から出てきた穴なんですよ。まだ穴の中に幼虫がいる時は、大豆ほどの小さな穴です。少年の頃は、この穴にたくさんの水を入れて、幼虫を中から出してつかまえました。夜になってその幼虫を蚊帳(かや)の中に入れておくと、朝には立派なセミになっているのです。

シオカラトンボも飛んでいました。そして、アキアカネが校庭を舞い始める頃、楽しかった夏休みもいよいよ終盤を・・・。
先生、そう話をいそがないでくださいよ! という児童生徒のみなさんの声が聞こえてきそうなので今回はこれくらいにしておきましょう。
夏休みの校庭では!
7月23日(木) 今日の朝は雨が降っていました。日中は曇り空、時々小雨が降っています。
学部の花壇の除草を終え、校庭を散歩してみると、いろいろな果樹や草花が元気よく育っていました。夏休みに入ったばかりですが、いつの間にかいろいろな変化を見せてくれています。

まずはこんな写真から見ていただきます。なんとも美味しそうな? 姫がまの穂です。中庭のビオトープで元気に育っていました。

そして、バケツの中では、JA足利からいただいた「ばけつ稲」が所狭しと背伸びしています。その横には、山崎直子さんと宇宙を旅した「NAOKO☆アサガオ」がツルを伸ばしています、

これは、玄関のアクアリウムの隣のホテイアオイ、メダカの稚魚がたくさん泳いでいます。

校庭の「野鳥の庭」の姫リンゴです。巣箱の下にはかわいい実がなっています。この巣箱にも野鳥が繁殖しました。

姫リンゴのお隣には、おいしそうなカキの実がなっています。まだ渋いので食べてはいけません。

大きなヒマワリも咲いています。昨年、課外活動で植えたヒマワリの種がこぼれて、自分の力だけで育ちました。

そして最後に御紹介するのは、プールの西側の温州ミカンです。このミカンは、平成23年12月に 大塚実みどりの基金による「ふるさと”とちぎ”みどりづくり事業」(公社 とちぎ環境みどり推進機構)の支援によって植樹されました。 今年から、たくさんの実を付け始めました。
こうして、夏休みの校庭の木々たちは、元気な児童生徒の皆さんをいつでも待っているんですね。
学部の花壇の除草を終え、校庭を散歩してみると、いろいろな果樹や草花が元気よく育っていました。夏休みに入ったばかりですが、いつの間にかいろいろな変化を見せてくれています。

まずはこんな写真から見ていただきます。なんとも美味しそうな? 姫がまの穂です。中庭のビオトープで元気に育っていました。

そして、バケツの中では、JA足利からいただいた「ばけつ稲」が所狭しと背伸びしています。その横には、山崎直子さんと宇宙を旅した「NAOKO☆アサガオ」がツルを伸ばしています、

これは、玄関のアクアリウムの隣のホテイアオイ、メダカの稚魚がたくさん泳いでいます。

校庭の「野鳥の庭」の姫リンゴです。巣箱の下にはかわいい実がなっています。この巣箱にも野鳥が繁殖しました。

姫リンゴのお隣には、おいしそうなカキの実がなっています。まだ渋いので食べてはいけません。

大きなヒマワリも咲いています。昨年、課外活動で植えたヒマワリの種がこぼれて、自分の力だけで育ちました。

そして最後に御紹介するのは、プールの西側の温州ミカンです。このミカンは、平成23年12月に 大塚実みどりの基金による「ふるさと”とちぎ”みどりづくり事業」(公社 とちぎ環境みどり推進機構)の支援によって植樹されました。 今年から、たくさんの実を付け始めました。
こうして、夏休みの校庭の木々たちは、元気な児童生徒の皆さんをいつでも待っているんですね。
アケビの仲間たち
7月14日(火) 校庭のアケビ棚を見ると、小さなアケビの実がなっていました。そういえばアケビの種類ってどれくらいあるんだろうと思い調べてみました。

アケビの仲間には、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類があるそうです。本校のアケビは、小葉5枚からなる掌状複葉で、小葉は楕円形で縁にギザギザ(きょ歯)がないため、アケビであることが明らかです。

校庭の植物をいろいろ調べてみると楽しいですね。

アケビの仲間には、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類があるそうです。本校のアケビは、小葉5枚からなる掌状複葉で、小葉は楕円形で縁にギザギザ(きょ歯)がないため、アケビであることが明らかです。

校庭の植物をいろいろ調べてみると楽しいですね。
山崎宇宙飛行士と宇宙を旅しました!
7月7日(火) 校庭の片隅にある課外活動の花壇から、かわいいカボチャの双葉が顔を出していました。これは、6月25日(木)、課外活動の時間にまかれた宇宙を旅したカボチャです。
この種は、山崎直子宇宙飛行士の公式記念品(OFK)として宇宙を旅しました。

そして、こちらは宇宙を旅したアサガオです。「NAOKO☆アサガオ」と呼ばれており、「やさしさ」「おもいやり」『きぼう』を育てることをねらいとしています。さらには、いのちを育てることの大切さを学んでもらいたいという大きな願いも込められています。

この種は、山崎直子宇宙飛行士の公式記念品(OFK)として宇宙を旅しました。

そして、こちらは宇宙を旅したアサガオです。「NAOKO☆アサガオ」と呼ばれており、「やさしさ」「おもいやり」『きぼう』を育てることをねらいとしています。さらには、いのちを育てることの大切さを学んでもらいたいという大きな願いも込められています。

ヒヨドリのひな誕生!
6月8日(月) 学校中庭に作られたヒヨドリの巣を観察しました。
先日、御紹介した時は4個の卵がありました。昨年のひなの数も4匹、そして今日4匹のひなが確認されました。ヒヨドリは、シジュウカラなどの小型の鳥よりも身体が大きいためか、卵も4つくらいが適当なのかも知れません。(本校の児童生徒によるシジュウカラの観察では、6個~11個までの記録があります)
今年も無事に巣だってほしいですね。そしてまた来年も同じ木で繁殖してほしいと願っています。

先日、御紹介した時は4個の卵がありました。昨年のひなの数も4匹、そして今日4匹のひなが確認されました。ヒヨドリは、シジュウカラなどの小型の鳥よりも身体が大きいためか、卵も4つくらいが適当なのかも知れません。(本校の児童生徒によるシジュウカラの観察では、6個~11個までの記録があります)
今年も無事に巣だってほしいですね。そしてまた来年も同じ木で繁殖してほしいと願っています。

ユスラウメの赤い実
「ユスラウメの実が美味しそうでしたね」 本校の交流運動会(5月30日)、生徒を引率して来校してくださいました交流校の先生のお話。「食べたかったけど、悪いと思って・・・」そう言いながら昔をなつかしんでいました。
小学生の頃、通学路になっていた果物たちの一つに、このユスラウメがありました。ちょっとサクランボに似た味がします。
このコーナーで、ユスラウメの実を御紹介するのは初めてです。あっと言う間に小鳥が食べてしまうためか、あまり目立たなかったようです。

小学生の頃、通学路になっていた果物たちの一つに、このユスラウメがありました。ちょっとサクランボに似た味がします。
このコーナーで、ユスラウメの実を御紹介するのは初めてです。あっと言う間に小鳥が食べてしまうためか、あまり目立たなかったようです。

ブルーベリーのお話
5月29日(金) 運動会を明日に控えた校庭の片隅の「野鳥の庭」。ブルーベリーが実を付け始めました。このブルーベリーは、結実を促進するために、ハイブッシュ系とラビットアイ系の2品種が植樹されています。
ブルーベリーに適した用土は、pH4,3~5,5という強い酸性土です。ピートモス(カナダの水苔を腐熟させた園芸資材)などを土にすき込みます。
児童生徒のみなさん、今年も小鳥たちに負けないように、甘い果実を楽しんでくださいね。

ブルーベリーに適した用土は、pH4,3~5,5という強い酸性土です。ピートモス(カナダの水苔を腐熟させた園芸資材)などを土にすき込みます。
児童生徒のみなさん、今年も小鳥たちに負けないように、甘い果実を楽しんでくださいね。

今年は防水性?の巣だ!
5月26日(火) 中庭にあるツバキの木に、今年もヒヨドリが巣を作りました。巣をそっとのぞいてみると、卵が4つ産み付けられていました。親鳥はまだ卵を温めていません。小鳥たちは、強い猛禽類とは異なり、卵を多く産みます。そして、卵を同時に孵化させるために、最終卵を産んでから卵を抱き始めます。雛たちを均一に育てるための工夫なんですね。
その点、タカやフクロウなどの猛きん類は、卵を1~2個しか産まず、第1卵から卵を抱き始めてしまいます。(強い雛しか育てません )しかし、小鳥たちは、厳しい生存競争を生き抜かなければならず、多くの卵を産んで、効率よく、しかも速やかに巣立ちさせる合理的な方法を選択しています。
ところで、今年の巣を下から見ると、なんとビニール袋が使われています。防水のためなんでしょうか? 雨がたまって、その重さで巣が落ちなければいいのですが・・・。
スイレンとミカンの花
ビオトープのスイレンの花が咲きました。このビオトープは、すでに御紹介のとおり、平成8年度に当時の観察池を改造して作られたものです。前回のヤゴのお話は、このビオトープで繁殖したギンヤンマのことでした。
「先生、スイレンとハスってどう違うの?」 「・・・なんでハスの花の上に仏像がいるの?」昔なつかしい生徒との会話を思い出しました。
ミカンの花も咲いていました。今年は、昨年より早い開花だったようです。今年の秋も甘いミカンが食べられそうですね。



「先生、スイレンとハスってどう違うの?」 「・・・なんでハスの花の上に仏像がいるの?」昔なつかしい生徒との会話を思い出しました。
ミカンの花も咲いていました。今年は、昨年より早い開花だったようです。今年の秋も甘いミカンが食べられそうですね。



ミズアオイの種まきをしました。
総合的な学習の時間「チャレンジタイム」において、小学部の児童たちによって「ミズアオイ」の種まきが行われました。昨年度に見事な花を咲かせた株からとった種をまきました。
このミズアオイの栽培は、平成8年度から始められました。当時は絶滅危惧植物の保護を通して、障害のある児童生徒たちの「生きる力」を育てることを目的としていました。
今年度は、野鳥の観察やメダカの飼育などを通して、もう一度原点に立ち返り、生命について考えてみるよい機会とします。


このミズアオイの栽培は、平成8年度から始められました。当時は絶滅危惧植物の保護を通して、障害のある児童生徒たちの「生きる力」を育てることを目的としていました。
今年度は、野鳥の観察やメダカの飼育などを通して、もう一度原点に立ち返り、生命について考えてみるよい機会とします。


♪ メダカの学校は ♪
本校の玄関に設置されているアクアリウム(120×45×45㎝)に、新しいメダカ(約40匹)がやってきました。今年度の環境教育推進委員会の活動テーマのひとつであるメダカの繁殖、児童生徒たちの活躍が期待されています。

赤、青、黄色のメダカたち、とても元気です。

赤、青、黄色のメダカたち、とても元気です。
ビオトープで発見!!
ゴールデンウィーク明けの木曜日、学校中庭のビオトープにてヒメガマの葉につかまった虫の抜け殻を発見しました。


体長を測ると約5cm、この日だけで5匹発見しました。小学部の子供たちも大きさにびっくりしていました!図鑑によると種類はギンヤンマ、成虫になると9cmほどにまで成長するようです。
ギンヤンマは幼虫で越冬し、大きくなるとメダカやオタマジャクシも捕食します。十分に成長した幼虫は4月の終わりから5月にかけて、成虫への脱皮を行います。夜に脱皮した成虫は朝早くまで、じっと動かず羽や腹が固くなるのを待つので、朝早くビオトープをのぞくと脱皮したての成虫を見ることができるかもしれません。


体長を測ると約5cm、この日だけで5匹発見しました。小学部の子供たちも大きさにびっくりしていました!図鑑によると種類はギンヤンマ、成虫になると9cmほどにまで成長するようです。
ギンヤンマは幼虫で越冬し、大きくなるとメダカやオタマジャクシも捕食します。十分に成長した幼虫は4月の終わりから5月にかけて、成虫への脱皮を行います。夜に脱皮した成虫は朝早くまで、じっと動かず羽や腹が固くなるのを待つので、朝早くビオトープをのぞくと脱皮したての成虫を見ることができるかもしれません。
藤の花を発見!
5月1日(金) 体育館に向かう通路と校舎の間のスペースには、カエデ、アジサイ、キョウチクトウ、ヤツデなどが植えられています。なんと、キョウチクトウの株元に、藤の花が・・・! それは、150㎝にも満たない小さな幼木ですが、立派な花をつけていました。ここに、藤の花が咲いていること知っている人は少ないでしょう。やがて、大きく育ったころ皆から尊ばれるようになるでしょう。それまで、元気に育ってほしいと願っています、


ブルーベリーとリンゴと・・・、
4月24日(金) 校地を散歩すると、ブルーベリーのかわいい花を見つけました。そして、リンゴの花も・・・・、昨年は、結実しなかったリンゴ(フジ)ですが、今年は初の結実となるでしょうか?
そして、ふと足下を見ると・・・。さりげなく咲いている身近な草花ですが、よく見てみると、きれいなものですね。



そして、ふと足下を見ると・・・。さりげなく咲いている身近な草花ですが、よく見てみると、きれいなものですね。



野鳥の繁殖がスタート!
4月21日(火) 学校裏山に仮設した巣箱(フクロウ用1,カラ類用17)の様子を見に行きました。現在、シジュウカラが抱卵している巣箱が一つありました。その他、産卵用に運ばれたミズゴケを中心とした巣が数カ所で確認されました。また、冬季にねぐらとして利用されていた痕跡も見受けられました。しかし、今年の2月に近隣に砂防ダムが完成し、山道の舗装工事などが行われていたため、繁殖数は昨年度より少なめと予想されます。今年も、野鳥の観察を通して、いろいろな学習に生かしてほしいと期待しています。(環境教育委員会では、事前に巣箱の繁殖調査を行い、その結果を児童生徒のみなさんに公開することで、学習の効率化を図っています)
*学校裏山:あしかがの森 足利病院 「ほたる沢公園」内

*学校裏山:あしかがの森 足利病院 「ほたる沢公園」内

開の時期を比べると!
4月20日(月) 姫リンゴの花が満開になりました。校庭南側の「野鳥の庭」に植樹されているこの姫リンゴ、昨年は4月16日頃満開になりました。
校庭の木々の開花や、学校裏山の野鳥たちのさえずりなどを記録していくと、いろいろなことがわかってくるようです。昔から伝わる話に、生け垣などに作られる蜂の巣の位置(高低)によって、その年の雨量(多いか少ないか)を予測することができるそうです。今年度は、いったいどのような年になるのでしょうか?

校庭の木々の開花や、学校裏山の野鳥たちのさえずりなどを記録していくと、いろいろなことがわかってくるようです。昔から伝わる話に、生け垣などに作られる蜂の巣の位置(高低)によって、その年の雨量(多いか少ないか)を予測することができるそうです。今年度は、いったいどのような年になるのでしょうか?

「野鳥の庭」の息吹
4月15日(水) 「野鳥の庭」の果樹たちの息吹を感じる季節になりました。まだ、シジュウ
カラのさえずりは聞こえてきませんが、メジロやコカワラヒワの鳴き声が響いてきます。
昨年度1月に完成した花壇(ふるさと とちぎ みどりづくり事業)では、ブルーベリーとサクラ
ンボが元気に育っています。また、姫リンゴやアケビの花も咲き出しました。
* ふるさと とちぎ みどりづくり事業:「大塚実みどり基金」公益社団法人とちぎ環境・みど
り推進機構の支援による。



カラのさえずりは聞こえてきませんが、メジロやコカワラヒワの鳴き声が響いてきます。
昨年度1月に完成した花壇(ふるさと とちぎ みどりづくり事業)では、ブルーベリーとサクラ
ンボが元気に育っています。また、姫リンゴやアケビの花も咲き出しました。
* ふるさと とちぎ みどりづくり事業:「大塚実みどり基金」公益社団法人とちぎ環境・みど
り推進機構の支援による。



学校花壇の花たち
学校花壇のチューリッップが満開になりました。今年は、1週間ほど早い開花になったよう
です。そして、花壇の傍らに植えられたレンギョウの花もきれいでした。「バナナみたいな
花!」と言ったのは、生徒ではなく、なんとK・A先生でした。よく見ると、花弁がバナナの実
のように黄色でかわいい形をしています。よく見ると、意外なところに気付くのが自然観察の
おもしろいところですね。


春を迎えた「野鳥の庭」
4月1日(水) 新年度を迎えた校庭の木々もいよいよ花盛り。校庭の南側にある「野鳥の庭」のユスラウメと乙女椿の花が咲きました。そして、大坊山の中腹から、メジロのさえずりが聞こえてきました。「ちょうべい、ちゅうべい、ちょうちゅうべい・・・」と昔の人は聞きなしていたそうです。そして、モンシロチョウも飛び始め、桜の花も満開になりました。いよいよ春本番ですね。






春が来た!
3月18日(水) 校庭の桜桃(サクランボ)が満開になりました。この桜桃は、暖地生で、佐藤錦やナポレオン(同校庭の野鳥の庭に植樹されている)よりも約半月早く開花します。一般に、園芸店で「桜桃(サクランボ)」と命名されています。実付きはたいへん良いのですが、あまり美味しくありません。児童生徒の皆さん、実がなったらぜひご試食を・・・。ヒヨドリやムクドリに負けないで収穫してみてくださいね。
ところで、今朝(18日)、ウグイスの初鳴きを聞きました。春がきました。これから、このホームページでは、野鳥や昆虫の初鳴きや初登場をいち早くお知らせしていきます。どうか、皆さんも季節を全身で感じていただければ幸いです。

ところで、今朝(18日)、ウグイスの初鳴きを聞きました。春がきました。これから、このホームページでは、野鳥や昆虫の初鳴きや初登場をいち早くお知らせしていきます。どうか、皆さんも季節を全身で感じていただければ幸いです。

ふるさととちぎみどりづくり事業に感謝!
1月28日(水) 校庭の「野鳥の庭」に、新しい花壇が完成しました。この事業は、公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構の支援による「ふるさととちぎみどりづくり事業」の一環として実施されました。
前回(本ホームページ)、御紹介いたしましたが、自然保護活動(現在では、環境教育活動)のフィールドとして設けられた「野鳥の庭」(校庭南側スペース)のブルーベリー(16本)とサクランボ(2本)を囲むコンクリートブロック積花壇(周長21.5m)が完成しました。
また、花壇用土に用いられたのは、ブルーベリーに適した弱酸性のバーク堆肥系用土で、幼木の健やかな成長を促します。
生徒会代表委員の生徒たちは、「おいしい実がたくさん成ってほしい」と期待に胸をふくらませていました。


前回(本ホームページ)、御紹介いたしましたが、自然保護活動(現在では、環境教育活動)のフィールドとして設けられた「野鳥の庭」(校庭南側スペース)のブルーベリー(16本)とサクランボ(2本)を囲むコンクリートブロック積花壇(周長21.5m)が完成しました。
また、花壇用土に用いられたのは、ブルーベリーに適した弱酸性のバーク堆肥系用土で、幼木の健やかな成長を促します。
生徒会代表委員の生徒たちは、「おいしい実がたくさん成ってほしい」と期待に胸をふくらませていました。


ふるさととちぎみどりづくり事業始まる
1月14日(水) 校庭南側にある「野鳥の庭」の工事が始まりました。この事業は、公益社団法人 とちぎ環境みどり推進機構の支援によって実施されているものです。
本校では、平成23年12月に、 同事業によって、花壇の造成、みかんとブルーベリーの植樹が行われました。残念ながら、ブルーベリーの植樹された場所は、豪雨などによって、土が少しずつ浸食してしまい、隣接する沼に流れ出てしまう状態でした。
今回の工事によって、校庭の土砂の流出を防止するとともに、ブルーベリーやサクランボなどの幼木に適した花壇が完成する予定です。


今度は、♪ あま~いミカンのお話 ♪
過日(6月17日:本ホームページ)御紹介いたしました「あま~くないミカンの話」の続編です。
10月30日(木) 校庭の南側の「野鳥の庭」に植えられている温州みかん。ごらんの通り、今年もたくさんの実がなりました。樹齢14年目を迎えたこのみかんも、いよいよおいしい実をつける適齢期(15年~)になりました。そして、白くてあまい香りを漂わせていた花を咲かせていたのも、つい昨日のように感じられます。(5月19日:本ホームページに掲載)
そして、今年もあまい実をもぎとるためのヒントを紹介します。
よく日光の当たっている枝についている実に注目、ちょっと握ってみて、比較的やわらかい実を食べてみましょう。(それでも酸っぱかったら、ハズレです。再チャレンジを・・・)

10月30日(木) 校庭の南側の「野鳥の庭」に植えられている温州みかん。ごらんの通り、今年もたくさんの実がなりました。樹齢14年目を迎えたこのみかんも、いよいよおいしい実をつける適齢期(15年~)になりました。そして、白くてあまい香りを漂わせていた花を咲かせていたのも、つい昨日のように感じられます。(5月19日:本ホームページに掲載)
そして、今年もあまい実をもぎとるためのヒントを紹介します。
よく日光の当たっている枝についている実に注目、ちょっと握ってみて、比較的やわらかい実を食べてみましょう。(それでも酸っぱかったら、ハズレです。再チャレンジを・・・)

お誕生おめでとう!
10月28日(火) 小学部川田学級で飼育されていたカタツムリの赤ちゃんがめでたく誕生しました。先生たちもカタツムリのたまごを見たのは初めてでした。思わずゴミかと思って洗ってしまうところでした。担任の先生は、うれしそうに笑いながらカタツムリの赤ちゃんを見つめていました。
そういえば、先週誕生したクロアゲハについてのレポートをアップしようとしていた矢先のことだったので合わせてご紹介することになりました。そして、この日はR君の誕生日だとか。楽しい思い出になりそうですね。



そういえば、先週誕生したクロアゲハについてのレポートをアップしようとしていた矢先のことだったので合わせてご紹介することになりました。そして、この日はR君の誕生日だとか。楽しい思い出になりそうですね。



花が咲いてうれしいな!
8月4日(木) ビオトープの近くを通った小学部の児童たちが、ミズアオイの花を見ていました。そのうちの一人の児童は、「きれいな花だと思いました、花が咲いて良かったです」と感想を述べていました。


エゴノミがいっぱい
学校の中庭にはエゴノキがあります。漢字では「斉墩果」と表記されます。う~ん、難読ですね。
今、エゴノキには、たくさんのエゴの実がなっています。写真は8月末のものです。
このエゴの実ですが、これが大好物の野鳥がいます。
「ヤマガラ」といいます。みなさんにはなじみの深いあのシジュウカラと同じ科に属します。
これから秋になるとエゴノキにヤマガラが飛来し、さかんにエゴの実をついばむ姿を観察することができます。ヤマガラはエゴの実を食べずに、くわえて飛んでいきます。樹木のウロなどに保存し、餌の少なくなった冬期に食べるそうです。学校に来るヤマガラは、実をくわえて林道を越え大坊山の麓のほうに飛んでいきます。いったいどこまで実を運んでいるのでしょう。
ヤマガラはもともと学習能力の高い野鳥と聞きます。芸を覚えたり手乗りで餌を食べたりする写真を見たことがあります。
気をつけていないと見落としがちな小さな野鳥ですが、これからの秋が楽しみです。

今、エゴノキには、たくさんのエゴの実がなっています。写真は8月末のものです。
このエゴの実ですが、これが大好物の野鳥がいます。
「ヤマガラ」といいます。みなさんにはなじみの深いあのシジュウカラと同じ科に属します。
これから秋になるとエゴノキにヤマガラが飛来し、さかんにエゴの実をついばむ姿を観察することができます。ヤマガラはエゴの実を食べずに、くわえて飛んでいきます。樹木のウロなどに保存し、餌の少なくなった冬期に食べるそうです。学校に来るヤマガラは、実をくわえて林道を越え大坊山の麓のほうに飛んでいきます。いったいどこまで実を運んでいるのでしょう。
ヤマガラはもともと学習能力の高い野鳥と聞きます。芸を覚えたり手乗りで餌を食べたりする写真を見たことがあります。
気をつけていないと見落としがちな小さな野鳥ですが、これからの秋が楽しみです。

オトメツバキの思い出
本校の自然保護活動が本格化して4年目の平成9年に、当時の小学部児童と中学部生徒が、環境省(当時は環境庁でした)「こどもエコクラブ」の活動に参加しました。翌10年には中学部3年生だったAくんの発案で「自然守り隊」の名で登録となりました。この頃は、まだ高等部はありませんでした。
その活動の一環に「こどもエコクラブエコロジカルあくしょん県コンテスト」がありました。自分たちが取り組んでいる自然保護活動を壁新聞で表現し発表するという内容でした。平成9年度は、シジュウカラやヤマガラ(カラ類)の巣箱架設で得られた今までの観察記録や当時絶滅危惧植物だったミズアオイの栽培・観察などを記事にしました。
結果は、めでたく優秀賞となり、栃木県代表として、名古屋で開催されたこどもエコクラブ全国フェスティバルに参加しました。2名の中学生が名古屋まで足を運びました。平成10年3月28日のことです。
そのときいただいた参加記念樹が「オトメツバキ」です。当時は高さが30センチほどでしたが、現在は大人の背丈ほどに成長しています。掲載の写真はその見事な実です。
校庭南側の「野鳥の庭」に植樹されています。
周囲の遊具では子どもたちが元気に遊んでいます。
オトメツバキもそっと見守っているようです。

その活動の一環に「こどもエコクラブエコロジカルあくしょん県コンテスト」がありました。自分たちが取り組んでいる自然保護活動を壁新聞で表現し発表するという内容でした。平成9年度は、シジュウカラやヤマガラ(カラ類)の巣箱架設で得られた今までの観察記録や当時絶滅危惧植物だったミズアオイの栽培・観察などを記事にしました。
結果は、めでたく優秀賞となり、栃木県代表として、名古屋で開催されたこどもエコクラブ全国フェスティバルに参加しました。2名の中学生が名古屋まで足を運びました。平成10年3月28日のことです。
そのときいただいた参加記念樹が「オトメツバキ」です。当時は高さが30センチほどでしたが、現在は大人の背丈ほどに成長しています。掲載の写真はその見事な実です。
校庭南側の「野鳥の庭」に植樹されています。
周囲の遊具では子どもたちが元気に遊んでいます。
オトメツバキもそっと見守っているようです。

サンカクイが元気に生育しています。
以前このコーナーでお伝えいたしました、かつては環境省の選定で絶滅危惧Ⅱ類(VU)、現在は準絶滅危惧となっている「ミズアオイ」の栽培について紹介しました。
本校には、絶滅危惧や準絶滅危惧(都道府県によって異なる)植物となっている「サンカクイ」が元気に育っています。ちなみに本校のある栃木県では、どちらにも選定されていません。(栃木県では珍しくないのかも?)
サンカクイは、名前のとおり、茎の断面が三角の形状をしています。湿地に育ちます。
本校では、平成8年に、中庭のそれまで観察池だったところに裏山の土砂を入れ、ビオトープを造成しました。教師と児童ゎ生徒が力を合わせて行いました。
当初は、環境省が絶滅危惧Ⅱ類(VU)に選定した「ヒメシロアサザ」や、準絶滅危惧の「ミクリ」も定植しましたが、残念ながら育ちませんでした。「サンカクイ」はこの環境が適したのか、19年たった今も元気に育をっています。
現在のビオトープには、スイレンの花が咲き、ヒメガマが背を伸ばし、メダカやクチボソがのんびり泳いでいます。
自然の安らぎに、心が安まる空間となっています。

本校には、絶滅危惧や準絶滅危惧(都道府県によって異なる)植物となっている「サンカクイ」が元気に育っています。ちなみに本校のある栃木県では、どちらにも選定されていません。(栃木県では珍しくないのかも?)
サンカクイは、名前のとおり、茎の断面が三角の形状をしています。湿地に育ちます。
本校では、平成8年に、中庭のそれまで観察池だったところに裏山の土砂を入れ、ビオトープを造成しました。教師と児童ゎ生徒が力を合わせて行いました。
当初は、環境省が絶滅危惧Ⅱ類(VU)に選定した「ヒメシロアサザ」や、準絶滅危惧の「ミクリ」も定植しましたが、残念ながら育ちませんでした。「サンカクイ」はこの環境が適したのか、19年たった今も元気に育をっています。
現在のビオトープには、スイレンの花が咲き、ヒメガマが背を伸ばし、メダカやクチボソがのんびり泳いでいます。
自然の安らぎに、心が安まる空間となっています。

コナギとミズアオイのこと
本校のミズアオイを栽培しているプランタには、「コナギ」も共生しています。コナギはミズアオイと同じミズアオイ科の植物ですが、花が咲くまではミズアオイと区別することが困難です。発芽したときから開花するまでの葉の形の変化など、このふたつの植物はそっくりです。
見分け方は、花の付き方です。ミズアオイは、花序を真上に伸ばします。葉より高い位置で開花することが多いです。コナギは花を葉腋に付けます。花の上に葉があります。
今までミズアオイと思っていたものが、じつはコナギだったということがよくあるようです。
ここに掲載したコナギの花の写真と、以前掲載したミズアオイの花の写真を見比べてみてください。なるほどと思いますよね。
本校のプランタにこの2種がなぜ共生しているかと考えると、栽培を始めたとき、ミズアオイの種子と思っていたものに、コナギの種子が混じっていたということのようです。

見分け方は、花の付き方です。ミズアオイは、花序を真上に伸ばします。葉より高い位置で開花することが多いです。コナギは花を葉腋に付けます。花の上に葉があります。
今までミズアオイと思っていたものが、じつはコナギだったということがよくあるようです。
ここに掲載したコナギの花の写真と、以前掲載したミズアオイの花の写真を見比べてみてください。なるほどと思いますよね。
本校のプランタにこの2種がなぜ共生しているかと考えると、栽培を始めたとき、ミズアオイの種子と思っていたものに、コナギの種子が混じっていたということのようです。

今年もミズアオイの花が咲きました!
以前、このコーナーで御紹介いたしましたように、今年の5月9日(金)のチャレンジタイム(総合的な学習の時間)で、小学部の児童たちが、ミズアオイの種を蒔きました。順調に生育が進み、今夏も開花を観察することができました。掲載の写真は、8月25日(月)に撮影したものです。
ミズアオイは、かつて環境省のレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に選定されていましたが、現在は保護が進んだようで、「準絶滅危惧」に変更されています。
本校では平成8年にミズアオイ栽培を始めました。渡瀬遊水池の植物に造詣の深い当時の理科の先生の御指導によるものでした。以後、毎年、播種と採種を繰り返し、今年で19年になりました。
ささやかな活動ですが、このことが自然を愛でる心が育つ一助となることをこころから願ってやみません。

ミズアオイは、かつて環境省のレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に選定されていましたが、現在は保護が進んだようで、「準絶滅危惧」に変更されています。
本校では平成8年にミズアオイ栽培を始めました。渡瀬遊水池の植物に造詣の深い当時の理科の先生の御指導によるものでした。以後、毎年、播種と採種を繰り返し、今年で19年になりました。
ささやかな活動ですが、このことが自然を愛でる心が育つ一助となることをこころから願ってやみません。

今年も同じ木で「ピー、ピー!」
7月8日(火) 中庭にあるビオトープの隣の小さなツバキの木に、今年もヒヨドリが巣をかけました。「ピー、ピー、ピー・・・」大きな声で鳴いています。
小学部の子どもたちがやって来ました。いつもの生き物が大好きなメンバーです。首を長く伸ばして、今にも巣から落ちそうなヒヨドリのひな(小学部の子どもたちも首を長くして)を見て、「見えた、見えた」と感激していました。今週は、台風8号が接近しそうです。無事に育ってくれることを願っています。


小学部の子どもたちがやって来ました。いつもの生き物が大好きなメンバーです。首を長く伸ばして、今にも巣から落ちそうなヒヨドリのひな(小学部の子どもたちも首を長くして)を見て、「見えた、見えた」と感激していました。今週は、台風8号が接近しそうです。無事に育ってくれることを願っています。


学校花壇の花が満開に!
先日ご紹介した学校花壇のサルビアの花が満開になりました、続報としてご紹介します。




7月のキノコ
7月3日(木) 学校の裏山にある「ほたる沢公園」を散歩しました。雨の多いこの頃、たまには病棟の外へ出てみることに。
山道の風はとてもさわやかで、柔らかな日差しが車椅子に降り注いでいました。・・・と、そんな時・・・。「あっキノコだ!」 なんと、遊歩道の傍らに、きれいなキノコを発見しました。「キノコって、秋だけじゃないんですね」
名前がわからないので、図鑑で調べてくれた人は、後でコメントをくださいね。

山道の風はとてもさわやかで、柔らかな日差しが車椅子に降り注いでいました。・・・と、そんな時・・・。「あっキノコだ!」 なんと、遊歩道の傍らに、きれいなキノコを発見しました。「キノコって、秋だけじゃないんですね」
名前がわからないので、図鑑で調べてくれた人は、後でコメントをくださいね。

絶滅危惧植物「ミズアオイ」が育つ
7月3日(木) 学校中庭にあるビオトープの「ミズアオイ」を紹介します。
この「ミズアオイ」は、5月9日(金)に、総合的な学習の時間において、小学部の児童たちによって播種されました。その後、無事発芽し、元気よく育っています。
「ミズアオイ」は、ミズアオイ科ミズアオイ属の植物です。また、環境省レッドリストによる絶滅危惧(VU)に分類されています。
近似種に、同じミズアオイ属のコナギがありますが、ミズアオイは花序を真上に伸ばすのに対して、コナギは花を葉の横側につけるので区別できるそうです。
花が咲いたら、よく観察してみましょう。

この「ミズアオイ」は、5月9日(金)に、総合的な学習の時間において、小学部の児童たちによって播種されました。その後、無事発芽し、元気よく育っています。
「ミズアオイ」は、ミズアオイ科ミズアオイ属の植物です。また、環境省レッドリストによる絶滅危惧(VU)に分類されています。
近似種に、同じミズアオイ属のコナギがありますが、ミズアオイは花序を真上に伸ばすのに対して、コナギは花を葉の横側につけるので区別できるそうです。
花が咲いたら、よく観察してみましょう。

ウチョウランの花
6月24日(火) 理科の先生に誘われて理科室に行ってみると、きれいな花を紹介してくれました。それはウチョウランという植物で、地生ランの一種、小さな多年草です。
紹介してくれた先生は、この球根を春に播いて育ててきました。理科の授業で生徒に見せてあげるそうです。
この球根は、小豆~小指頭大の大きさで、春に新芽を出し、6月に開花します。また、夏の成長期に1~3個の新球根ができ、秋に地上部が枯れ球根だけで越冬するそうです。来年は、生徒のみなさんによる一人一鉢栽培でも実施したくなるような可憐で小さなランでした。

紹介してくれた先生は、この球根を春に播いて育ててきました。理科の授業で生徒に見せてあげるそうです。
この球根は、小豆~小指頭大の大きさで、春に新芽を出し、6月に開花します。また、夏の成長期に1~3個の新球根ができ、秋に地上部が枯れ球根だけで越冬するそうです。来年は、生徒のみなさんによる一人一鉢栽培でも実施したくなるような可憐で小さなランでした。

四季を彩る学校花壇
本校の学校花壇は、校舎の南側にあります。(10㎡×7面)この花壇は、環境整備係の教師が中心となり、四季を通じて各種の草花が栽培されています。今は、サルビアとブルーサルビアの花がきれいに咲いています。
日頃の地道な土づくりや、草花の生育に適した施肥と灌水作業などがきめ細かに行われているため、いつも見事な花を咲かせています。


日頃の地道な土づくりや、草花の生育に適した施肥と灌水作業などがきめ細かに行われているため、いつも見事な花を咲かせています。


野菜を育てる楽しさを !
小学部と中学部の多目的花壇の様子(を紹介します。この花壇は、平成23年12月、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構(大塚実みどりの基金)の支援によって造成されました。
小学部のスペースでは、生活科や理科の授業で植えられたミニトマト、ヘチマ、オクラ、枝豆などが元気に育っています。
中学部のスペースには、サツマイモの苗がきれいに植えられています。
昨年は、イノシシやシカたちの被害によって、生育が思わしくありませんでしたが、今年はフェンスも取り付けられ、安心して野菜たちの観察ができるようになりました。おいしい実がなることを楽しみに、しっかり勉強しましょう。


小学部のスペースでは、生活科や理科の授業で植えられたミニトマト、ヘチマ、オクラ、枝豆などが元気に育っています。
中学部のスペースには、サツマイモの苗がきれいに植えられています。
昨年は、イノシシやシカたちの被害によって、生育が思わしくありませんでしたが、今年はフェンスも取り付けられ、安心して野菜たちの観察ができるようになりました。おいしい実がなることを楽しみに、しっかり勉強しましょう。


甘くな~い! ミカンの話
校庭の「野鳥の庭」にある温州ミカン(樹齢:15年、樹高:3m)の花が終わり、今ではこんなにも可愛い実がついています。
この2本の温州ミカンは、平成11年に植えられました。(県立学校個性化アクションプラン)また、この年は、第8回全国小学校中学校環境教育賞(主催:日本児童教育振興財団 後援:文部省、環境庁、全国都道府県教委、政令指定都市教委、全国39新聞社 協催:小学館)において、努力賞を受賞した年でもありました。
「先生、このミカン甘くないんだけど・・・」そうなんです。このミカンの実は、甘くないので有名?なんです。ここで、環境教育推進委員会からのコメントをひとつ・・・・。
● 熟していないミカンは甘くないのです。
鳥もまだ見向きもしないうちに、ほとんどの実が食べられてしまっているからですよ。(委員会としては、たいへんうれしいことなんですが・・・。)
一般に、ミカンは樹齢15年頃から収穫適齢期となり、20年で最盛期と言われています。
今年の秋は、「野鳥の庭」をよく観察して、鳥よりもはやく、しかも甘い実が食べられる児童生徒のみなさんを応援していますよ。

この2本の温州ミカンは、平成11年に植えられました。(県立学校個性化アクションプラン)また、この年は、第8回全国小学校中学校環境教育賞(主催:日本児童教育振興財団 後援:文部省、環境庁、全国都道府県教委、政令指定都市教委、全国39新聞社 協催:小学館)において、努力賞を受賞した年でもありました。
「先生、このミカン甘くないんだけど・・・」そうなんです。このミカンの実は、甘くないので有名?なんです。ここで、環境教育推進委員会からのコメントをひとつ・・・・。
● 熟していないミカンは甘くないのです。
鳥もまだ見向きもしないうちに、ほとんどの実が食べられてしまっているからですよ。(委員会としては、たいへんうれしいことなんですが・・・。)
一般に、ミカンは樹齢15年頃から収穫適齢期となり、20年で最盛期と言われています。
今年の秋は、「野鳥の庭」をよく観察して、鳥よりもはやく、しかも甘い実が食べられる児童生徒のみなさんを応援していますよ。

学校の樹木名を覚えよう
本校の敷地内に植えられている樹木には、その名前を示すプレートがつけられています。その数はなんと60種類以上です。このプレートは、環境教育推進委員である美術科の遅澤誠先生が数年にわたって製作くださっています。
今回は、「サクランボの花」についての続編です。数年前、元教頭の室井崇生先生が「野鳥の庭」に植えてくださいましたサクランボの名前がわかりました。「佐藤錦」と「ナポレオン」という品種です。サクランボは、このように品種の異なる木を植えることで、結実を促進させます。(他花受粉:適した品種の組み合わせがあります)室井先生は、佐藤錦とナポレオンの組み合わせが良いことをご存知でした。
今年はまだ結実しませんでしたが、来年はサクランボが食べられることでしょう。


今回は、「サクランボの花」についての続編です。数年前、元教頭の室井崇生先生が「野鳥の庭」に植えてくださいましたサクランボの名前がわかりました。「佐藤錦」と「ナポレオン」という品種です。サクランボは、このように品種の異なる木を植えることで、結実を促進させます。(他花受粉:適した品種の組み合わせがあります)室井先生は、佐藤錦とナポレオンの組み合わせが良いことをご存知でした。
今年はまだ結実しませんでしたが、来年はサクランボが食べられることでしょう。


「野鳥の庭」の果実たちは今!
校庭の南側にある「野鳥の庭」の果実たちは今、きれいな花を咲かせた後、かわいい実をつけはじめました。校庭に出たら、ちょっとのぞいて見てくださいね。
今回は、柿、姫リンゴ、ブルーベリーの子どもたちを紹介します。



今回は、柿、姫リンゴ、ブルーベリーの子どもたちを紹介します。



♪オタマジャクシはカエルの子♪
6月10日(火) 小学部6年生の教室で飼われているオタマジャクシの様子が気になり、放課後お邪魔してみました。オタマジャクシから育てられてきた小さなカエル(先日ホームページで紹介)は、もうこんなに大きくなっていました。そして、アメリカザリガニも別の水槽で、チョキを振りかざしていました。
アゲハ蝶の幼虫も食欲旺盛でした。今度、さなぎになった姿も紹介できるといいですね。



アゲハ蝶の幼虫も食欲旺盛でした。今度、さなぎになった姿も紹介できるといいですね。



サツマイモの苗を植えました
5月29日(木) 高等部の生徒によってサツマイモの苗が植えられました。この花壇は、平成25年12月「学校環境緑化モデル事業」(公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構)によって造成された多目的花壇です。
従来の花壇は、耕土も浅く、花壇の縁石が無かったことから、土がフェンスを超えて沼に流出してしまいましたが、今回の造成によって縁石が設けられ、新しく土も入れられました。そのため、耕土も5倍近く増加し、いろいろな草花や野菜を育てるのに適した多目的な花壇が誕生しました。
まずはサツマイモの栽培から挑戦することになり、生徒たちによる心のこもった栽培がスタートしました。

従来の花壇は、耕土も浅く、花壇の縁石が無かったことから、土がフェンスを超えて沼に流出してしまいましたが、今回の造成によって縁石が設けられ、新しく土も入れられました。そのため、耕土も5倍近く増加し、いろいろな草花や野菜を育てるのに適した多目的な花壇が誕生しました。
まずはサツマイモの栽培から挑戦することになり、生徒たちによる心のこもった栽培がスタートしました。

学校風景
連絡先
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町619-1
電話 0284-91-1110
FAX 0284-91-3660
ナビを利用して本校に来校される場合には、
「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。
リンクリスト