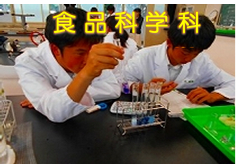文字
背景
行間
食品科学科より
食品科学科より
デコレーション実習を行いました。
デコレーション実習を行いました。
食品科学科の3年生は12月3日に、1年生は12月4日に、2年生は12月5日にデコレーション実習を行いました。3年生は3度目ということもあり、手早くケーキを作っていました。
2年生では、ほかの学年ではみられなかったチョコレートクリームを利用した作品もみられ、学年による個性がみられました。


一方、1年生はというと、2学期後半は食品化学・食品製造の授業では脂質とその性質を利用した食品をテーマに学習をしており、クリームが固まる原理(*1)等もあわせて学習しました。


*1 生クリームは水中油滴型のエマルション(エマルジョン)です。
エマルション(エマルジョン)は乳脂肪が水中で分離せず平均に浮遊しているような液体をあらわす用語です。
乳脂肪は脂肪球膜といって、表面に極性を持つ(水と親和性の高い)膜で覆われた状態にあるため分離せずに浮遊していることができます。しかし、ホイッパーでかき混ぜられるとその膜が崩れ、内部の脂肪球どうしが凝集し、最終的には気泡を取り込んだ網目状に変化していくのです。乳脂肪により形成されているつながりですから、温度が高くなると固さを失うことになりますし(バターを想像してください)、ホイップする際には10℃以下の温度で泡立てるときめの細かい状態にできる。また、膜を壊しすぎれば脂肪球の大きなかたまりが形成されるので、空気を含みにくくなり、最終的には分離してしまう。
こういった理論を知り、実際にやってみることで生徒のみなさんもよりよく理解できるのではないでしょうか。
余談ですが、従来、エマルジョンと呼ばれていましたが、最近ではJIS規格ではエマルションと表記されているため、この記事では併記しています。
このように、食品科学科の授業においても、農業という総合科学の1分野として、日々、学と業とを両の手に生徒の学びが展開されております。

そして、最後には試食することも学習の一部なのです。
食品科学科の3年生は12月3日に、1年生は12月4日に、2年生は12月5日にデコレーション実習を行いました。3年生は3度目ということもあり、手早くケーキを作っていました。
2年生では、ほかの学年ではみられなかったチョコレートクリームを利用した作品もみられ、学年による個性がみられました。


一方、1年生はというと、2学期後半は食品化学・食品製造の授業では脂質とその性質を利用した食品をテーマに学習をしており、クリームが固まる原理(*1)等もあわせて学習しました。


*1 生クリームは水中油滴型のエマルション(エマルジョン)です。
エマルション(エマルジョン)は乳脂肪が水中で分離せず平均に浮遊しているような液体をあらわす用語です。
乳脂肪は脂肪球膜といって、表面に極性を持つ(水と親和性の高い)膜で覆われた状態にあるため分離せずに浮遊していることができます。しかし、ホイッパーでかき混ぜられるとその膜が崩れ、内部の脂肪球どうしが凝集し、最終的には気泡を取り込んだ網目状に変化していくのです。乳脂肪により形成されているつながりですから、温度が高くなると固さを失うことになりますし(バターを想像してください)、ホイップする際には10℃以下の温度で泡立てるときめの細かい状態にできる。また、膜を壊しすぎれば脂肪球の大きなかたまりが形成されるので、空気を含みにくくなり、最終的には分離してしまう。
こういった理論を知り、実際にやってみることで生徒のみなさんもよりよく理解できるのではないでしょうか。
余談ですが、従来、エマルジョンと呼ばれていましたが、最近ではJIS規格ではエマルションと表記されているため、この記事では併記しています。
このように、食品科学科の授業においても、農業という総合科学の1分野として、日々、学と業とを両の手に生徒の学びが展開されております。

そして、最後には試食することも学習の一部なのです。
農業部会研究会(食品)
農業部会研究会(食品)
12月3日(火)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。内容は、午前中「食品化学実験」として3年生の授業を見学。食品成分、炭水化物の単元で、フェーリング反応により、還元糖と非還元糖の構造の違いを理解させる実験をしました。午後はHACCP(ハサップ、食品を製造する過程で発生する食中毒の原因となる危険因子を特定しやすくする仕組み)についての研修で、地元のあんこ製造会社おかしゅう様にお世話になり、講話と施設見学をさせていたきました。今後の授業に生かせ、HACCP取得に向けて良い研修の時となりました。








12月3日(火)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。内容は、午前中「食品化学実験」として3年生の授業を見学。食品成分、炭水化物の単元で、フェーリング反応により、還元糖と非還元糖の構造の違いを理解させる実験をしました。午後はHACCP(ハサップ、食品を製造する過程で発生する食中毒の原因となる危険因子を特定しやすくする仕組み)についての研修で、地元のあんこ製造会社おかしゅう様にお世話になり、講話と施設見学をさせていたきました。今後の授業に生かせ、HACCP取得に向けて良い研修の時となりました。








JR大宮エキナカに出店しました
JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市
11月16日(土)JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市に出店し、食品科学科と総合ビジネス科の生徒達が味噌、苺メロンパン(いちごいちえ)、苺杏仁豆腐、真岡もめんを使用したバッグ等を販売しました。大宮駅は、新幹線をはじめ14もの路線が乗り入れ乗降客数25万人と多く、北陵高の魅力を発信する絶好の機会でした。来年3月に真岡市で開催される「いちごサミット」についても宣伝ができ、とても良い経験となりました。








11月16日(土)JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市に出店し、食品科学科と総合ビジネス科の生徒達が味噌、苺メロンパン(いちごいちえ)、苺杏仁豆腐、真岡もめんを使用したバッグ等を販売しました。大宮駅は、新幹線をはじめ14もの路線が乗り入れ乗降客数25万人と多く、北陵高の魅力を発信する絶好の機会でした。来年3月に真岡市で開催される「いちごサミット」についても宣伝ができ、とても良い経験となりました。








味噌の製造実習
味噌の製造
北陵祭に向けて、食品科学科では味噌の製造実習が行われています。令和元年度の栃木県味噌鑑評会では審査委員会特別賞を受賞し、今年の出来も例年通り良さそうです。(表彰式が11月7日の予定です。)11月9日の北陵祭に販売しますので、是非御来校下さい。



「柿のパウンドケーキ」の試食会
「柿のパウンドケーキ」の試食会 於:道の駅もてぎ
10月27日(日)道の駅もてぎにて「柿のパウンドケーキ」の試食会を開きました。本校の食品科学科では、2018年から茂木町の河井上柿生産組合と協力して柿のペーストを使った商品開発を目指しています。今回、同組合との意見交換や試食会を重ね、生地に柿ペーストを練り込んだパウンドケーキの商品化となり一般の方に試食会となりました。当日200個用意し、たくさんのお客様に来ていただきアンケートにもお答えしていただき本当にありがとうございました。柿の風味があり、とても美味しく仕上がっていると好評でした。今回の貴重な意見を参考とし再度改良を重ねて商品化へ繫げたいと思います。




10月27日(日)道の駅もてぎにて「柿のパウンドケーキ」の試食会を開きました。本校の食品科学科では、2018年から茂木町の河井上柿生産組合と協力して柿のペーストを使った商品開発を目指しています。今回、同組合との意見交換や試食会を重ね、生地に柿ペーストを練り込んだパウンドケーキの商品化となり一般の方に試食会となりました。当日200個用意し、たくさんのお客様に来ていただきアンケートにもお答えしていただき本当にありがとうございました。柿の風味があり、とても美味しく仕上がっていると好評でした。今回の貴重な意見を参考とし再度改良を重ねて商品化へ繫げたいと思います。