文字
背景
行間
日誌
水産科掲示板
動き出す新たな製品制作
今年から、木曜日に水産科3年生がHPを更新します!
~今週の水産科3年生~
本日3年水産科で新たな実習製品の作成を行った。6センチ程度のアユを開き、魚醤で味付けをし、アユの一夜干しを製作した。捌く担当、開いたアユを洗う担当など役割ごとに作業を分けて効率よく製品を作成した。前回同様の製品の試作品を学校の先生方に配布した際、「お酒に合う」や「とてもおいしかった」など好評だったため、製品販売が楽しみだ。

~今週の水産科3年生~
本日3年水産科で新たな実習製品の作成を行った。6センチ程度のアユを開き、魚醤で味付けをし、アユの一夜干しを製作した。捌く担当、開いたアユを洗う担当など役割ごとに作業を分けて効率よく製品を作成した。前回同様の製品の試作品を学校の先生方に配布した際、「お酒に合う」や「とてもおいしかった」など好評だったため、製品販売が楽しみだ。

水産科3年 カヌー実習
5月14日(金)に3年生水産科の生徒19名でカヌー実習を実施しました。
天候にも恵まれ、絶好のカヌー日和でした。
八溝大橋からスタートして、那珂川町から那須烏山市まで計4時間12キロの区間でカヌーの実習を行いました。
今年はチンする(ひっくり返ってしまう)生徒が多かった等ハプニングはありましたが、生徒は楽しそうにカヌー操作技術を安全に学ぶことができました。そして、那珂川町から那須烏山の美しい自然を1日身近に感じ、自然の素晴らしさを改めて感じられました。
また、仲間との集団の中での自分の役割や関わり方を学ぶことができました。
終わりにはみんな肌を真っ赤に日焼けをしました。
貴重な体験ができて、生徒は満足そうにしていました。
アユの放流
ゴールデンウィークは終わりましたが、この記事はゴールデンウィーク前の話です。4月30日にアユの放流を行いました。
この日は水産試験場の方々から指導を受けて、2・3年生でアユの放流を行いました。今回は実習場横の武茂川に放流しました。放流したアユは、3月末にフィンカット(標識)をして実習場で飼育していた個体10,000尾です。死亡してしまった個体ありましたが、多くの鮎がすくすく育ちました。
事前説明を受けて、いよいよ放流です。10㎝程のアユをバケツに移し、武茂川までダッシュ!ゆっくりとバケツを傾け、アユが泳ぎ出すのを見守りました。放流した地点の近くに、実習で石を積んで環境改善をしたポイントがあります。今後は放流した個体を観察しながら、実際に釣りをしてヒレの有無を確認することで、釣りやすさや、定着の度合いを調査していきます。釣りに向けてやる気を見せている生徒そして教員にとっては、解禁日を心待ちにしているのではないでしょうか。
今回教えていただいたことを、今後の活動に役立てていきたいと思います。水産試験場の方々ありがとうございました!
水産クラブ 大森 小川 佐藤 でした☆



今回教えていただいたことを、今後の活動に役立てていきたいと思います。水産試験場の方々ありがとうございました!
水産クラブ 大森 小川 佐藤 でした☆



里山のサワガニ取り
4月28日(火)水産科1年生の「水産海洋基礎」の授業で、馬頭高校の裏山にサワガニ捕りに行きました。学校から歩いてすぐの場所で、「里山を体感する」というテーマです。小さな山から湧水が生じ、那珂川の一次支流である武茂川に注ぎます。生息するサワガニは一年中枯れることのない細流に定着しています。
生徒21名と教員5名で約1時間程度、計58個体のサワガニが採集できました。今回はあえてピンポイントで生息箇所を見つけるようにするため網を使わず、素手で採集しました。一番たくさん採った生徒は16個体、全くとれない生徒もいました。
生徒の感想には「見方によって採集数に大きな差がつく」というコメントもあり、生物採集の醍醐味も少しだけ味わってくれたようです。県外の東京、神奈川から入学してきた2名の生徒は、学校から歩いてサワガニが捕れる衝撃を口にしていました。
まとめでは、コドラート法という簡易的な生息数を推測する調査法を紹介し、その原理からこの細流には1㎡あたり2個体のサワガニが生息すると想定しました。そして、小さな山の小さな自然に様々な生物が生息し、私たち人間の生活や活動にうまく順応しながら代を重ねていることを生徒たちは体感してくれたのではないでしょうか。同時にそのような自然を知り、自然や生き物に目を向けられる人でいてほしい。そのための勉強をこれから送りましょうと結びました。


生徒21名と教員5名で約1時間程度、計58個体のサワガニが採集できました。今回はあえてピンポイントで生息箇所を見つけるようにするため網を使わず、素手で採集しました。一番たくさん採った生徒は16個体、全くとれない生徒もいました。
生徒の感想には「見方によって採集数に大きな差がつく」というコメントもあり、生物採集の醍醐味も少しだけ味わってくれたようです。県外の東京、神奈川から入学してきた2名の生徒は、学校から歩いてサワガニが捕れる衝撃を口にしていました。
まとめでは、コドラート法という簡易的な生息数を推測する調査法を紹介し、その原理からこの細流には1㎡あたり2個体のサワガニが生息すると想定しました。そして、小さな山の小さな自然に様々な生物が生息し、私たち人間の生活や活動にうまく順応しながら代を重ねていることを生徒たちは体感してくれたのではないでしょうか。同時にそのような自然を知り、自然や生き物に目を向けられる人でいてほしい。そのための勉強をこれから送りましょうと結びました。


水路清掃
4月15日(水)終日、水産科3年生が水路清掃を行いました。馬頭高校水産科実習場は、那珂川の支流武茂川から水を取り入れています。取り入れ口や実習場の水槽に溜まった泥やゴミを取り除き、きれいな水が流れ込むように熱心に作業を行いました。








アユの塩焼き
この日は1年水産科全員で鮎を焼くのに欠かせない竹串を作りました。


作:佐藤 成功例
はじめは一定の太さで削るのが苦戦しましたが、
時間が経って慣れていくうちに上手く削れるようになりました。
次は,アユを串に刺しました。
皆、刺すのに慣れていなくて上手く刺すことが出来ませんでした。
次は、アユを炭火で焼きました。

そして、皆でおいしくいただきました。
午後は、皆でガサガサをしました。
皆楽しく網で生き物を採集し、観察をしました。

水産科1年佐藤、小川、大森でした


作:佐藤 成功例
はじめは一定の太さで削るのが苦戦しましたが、
時間が経って慣れていくうちに上手く削れるようになりました。
次は,アユを串に刺しました。
皆、刺すのに慣れていなくて上手く刺すことが出来ませんでした。
次は、アユを炭火で焼きました。

そして、皆でおいしくいただきました。
午後は、皆でガサガサをしました。
皆楽しく網で生き物を採集し、観察をしました。

水産科1年佐藤、小川、大森でした
サケの放流
2020年11月12日に水産科3年生が行った「サケの採集」にて捕獲したサケから、卵と精子を取り、人工受精にてふ化したサケの稚魚をある程度のサイズにまで成長させ、2021年3月12日に武茂川に約90匹放流しました。
本校におけるサケの放流は、資源の維持を図るという目的で実習として行っています。
サケには、「母川回帰」という、海に降った後産まれた川に戻ってくる習性があります。そのため今回放流したサケは4年後大人になってからまた武茂川に戻ってくるはずです。
しかし、無事に海から産まれた川に帰って来れるのは、良くて100匹に1匹ととても少ないです。なので今回放流したサケ約90匹のうち1匹でも武茂川に戻って来ることが出来れば、大成功と言えます。
サケの放流後、クラス全員で自然に産まれたサケの稚魚を探しました。
たくさんの稚魚を見つけることは出来ませんでしたが、数匹サケの稚魚を確認することが出来ました。
(水産クラブ会長 鈴木)
未来の職業人育成事業 3日目
「オニテナガエビで町おこし」というテーマをもとに、今年度オニテナガエビの養殖に励んできました。
稚エビから育てたエビが親となり、採卵することができました。生存率は低いものの、養殖方法を確立させることができました。
この1年間、大きな成果を残すことはできませんでしたが、確実に前進をしていると感じることのできた1年間でした。
3回目の本事業。今回のテーマは「普及」。
と言うことで、本校で飼育したオニテナガエビが「なかがわ水遊園」で展示されることになりました。
新型コロナウイルスの影響で、生徒たちが直接持参することはできませんでしたが、無事に水遊園に到着。今後も継続して連携を図っていきたいです。
コロナウイルスの影響が少し落ち着いた頃に、ぜひ足を運んでみてください。

↑飼育員さんとオニテナガエビ

↑オニテナガエビの子どもたち
今日の実習(水産科1年生)
1月27日(水)
水産科1年生が実習でアユを捌きました。
今回使用した冷凍アユは、去年の7月に1年生が取り上げ、冷凍したアユです。
小さく、また解凍アユということもあり、難易度は高め。
人生で初めて、魚を捌いた生徒もいましたが、無事成功!
回数を重ね、より一層上達する君たちを楽しみにしています。


水産科1年生 石、積みました
12月16日 実習題目「巨石を積む」
水産科1年生が実習で石を積みました。
なぜ川に石を積むのかと言うと、、、
生きもの豊富な武茂川を目指しているからです。

まずは佐々木先生からレクチャーを受けます。
巨石とは250mm以上の石であり、石があることで魚の餌場や隠れ場ができます。
平らで流れの変化のない川は、生きものにとって餌場や隠れ場が少なく、生きづらい環境です。そのために石を積み、生きものが安心して生息できる川作りをしているのです。
流されない石の組み方や組んだ石による水流の変化について話を聞き、いざ極寒の川へ。

まずはみんなで石拾い。各々目的の石を見つけ、協力して運んできます。

今日はあまりにも寒いので、佐々木先生が極寒の川に手を入れ、石を積んでいきます。

今日は水深が浅いため、石を積んだ効果はこれから春先にかけて分かってくるのではないでしょうか。

釣り人が好む、生物豊富な武茂川になれるか。佐々木先生の挑戦は続きます。
~番外編~
①餃子石と喜んで運んできたおちゃめな生徒

②大きなサワガニをゲット!そのサワガニを飼育しようとしているご満悦な生徒

冬のご馳走できました
12月7日に、馬頭高校、冬の恒例行事となりつつあります、「チョウザメの採卵実習」が水産科3年生12名によって行われました。
11月26日に抱卵個体の確認を行い、加工するために泥抜きを開始。
約12kgの個体から約1.7kgのキャビアを加工することができました。
出来たキャビアはすでに完売となりました。本当にありがとうございます。
もし興味のある方は、本校のキャビアを使用してくれています、
「ホテル四季の館那須」へ足を運んでみてください。
最高の料理があなたを待っています。

↑慎重に腹部を切り開いています

↑取り出した卵巣をふるいにかけています

↑キャビアをきれいに洗浄中です

↑協力してくれた3年生、ありがとう!!
水産科3年永田くんの活動について
11月12日、令和2年度関東東海地区水産海洋高等学校生徒研究発表大会の審査がリモートで行われ、水産科3年永田旭くんが見事2位(優秀賞)となり、全国大会出場権を得ました。
永田くんの研究活動は、10/8と10/20に紹介したとおりです。校内発表大会で1位となり、関東東海地区大会に事前撮影の動画で出場し、各校長先生方の審査の結果、2位の報をいただきました。また、20日に掲載しました大田原市自然観察館の展示の様子は、下野新聞の取材を受けて25日の朝刊に掲載されました。
残念ながら、12月14・15日に静岡県焼津水産高校で開催予定の全国大会も事前撮影動画による出場となりました。練習を重ね、校内発表からさらにブラッシュアップして充実した発表ができるよう努力していきたいと思います。

永田くんの研究活動は、10/8と10/20に紹介したとおりです。校内発表大会で1位となり、関東東海地区大会に事前撮影の動画で出場し、各校長先生方の審査の結果、2位の報をいただきました。また、20日に掲載しました大田原市自然観察館の展示の様子は、下野新聞の取材を受けて25日の朝刊に掲載されました。
残念ながら、12月14・15日に静岡県焼津水産高校で開催予定の全国大会も事前撮影動画による出場となりました。練習を重ね、校内発表からさらにブラッシュアップして充実した発表ができるよう努力していきたいと思います。

第2回未来の職業人育成事業2日目
11/19(木)
馬頭中学校の実習場見学に合わせて、第2回目の未来の職業人育成事業を行いました。
今回は地元中学生にオニテナガエビを知ってもらい、興味を持ってもらうことを目標に、PRを行いました。
実習場見学も含め、この企画がこの先、地元を担う若者に水産業に興味を持ってもらうきっかけになったでしょうか!?
僕たちと一緒にオニテナガエビの養殖をしてくれる人、大募集中です。
次なる3回目にはオニテナガビを食することはできるでしょうか。養殖奮闘中です。



馬頭中学1年生水産科実習場見学
11月19日(木)
馬頭中学校の1年生65名が馬頭高校水産科実習場を訪れてくれました。地元を知ろう!という授業内容で高校に目を向けてくれたことにまず感謝です。
今回は3年生12名が、65名を受け入れました。3班に分かれて高校生4人ずつで水産科のことを説明しました。1時間強という短い時間でしたので20分ごとに、Ⅰ活動内容紹介 Ⅱ実習池見学 Ⅲ実習場隣設ビオトープ見学 の3つをローテーションで学んでもらいました。



当日は校長先生にお越しいただいたほか、馬頭ケーブルテレビも取材に訪れてくれました。本校生徒にとっても、自分たちの学校や活動を自分たちで説明する良い機会となりました。中学生は本当に熱心に話を聞いてくれました。この中から何とか馬頭高校水産科に入学してくれるといいなと、真剣にメモを取る中学生を見て思いました。
馬頭中学校の1年生65名が馬頭高校水産科実習場を訪れてくれました。地元を知ろう!という授業内容で高校に目を向けてくれたことにまず感謝です。
今回は3年生12名が、65名を受け入れました。3班に分かれて高校生4人ずつで水産科のことを説明しました。1時間強という短い時間でしたので20分ごとに、Ⅰ活動内容紹介 Ⅱ実習池見学 Ⅲ実習場隣設ビオトープ見学 の3つをローテーションで学んでもらいました。



当日は校長先生にお越しいただいたほか、馬頭ケーブルテレビも取材に訪れてくれました。本校生徒にとっても、自分たちの学校や活動を自分たちで説明する良い機会となりました。中学生は本当に熱心に話を聞いてくれました。この中から何とか馬頭高校水産科に入学してくれるといいなと、真剣にメモを取る中学生を見て思いました。
海洋生物 最後のガサ授業
11月19日(木)
水産科3年生「海洋生物」の授業で、この授業としては高校最後の水辺のガサガサによる水生生物採集を行いました。水産科実習場周辺の農水路やビオトープにおいて、自由に生物を採集するという授業です。与えられた課題はちょうど一時間をかけて誰が一番多くの種類を捕まえることができるか。水温の低くなったこの時期、どのような水生生物がどこにどのようなかたちで生息しているかを推測し、採集するというものです。採集した後は、用意された各種図鑑をもとに種の同定を行います。採集方法と場所は自分で考えます。一番多くの種類を見つけることができた人に豪華賞品をプレゼントするという人気企画です。


結果、クラス全体で合計41種類の生物を採集、同定できました。種は間違いなく違うけど同定できなかった生物もいましたので、実際にはもっと多くの種類が見つかっていたのかもしれません。内訳は次の通りです。
甲殻類3 アミメカゲロウ1 カゲロウ3 カメムシ3 カワゲラ2 トビケラ1 コウチュウ2
トンボ9 ハエ類1 軟体動物5 両生類2 魚類6
このうち、両生類でカジカガエルおよびヤマアカガエルが捕れるのはこの時期ならではであることと、山間部であることを示しているのかもしれません。魚類はカジカとアブラハヤが捕れました。アブラハヤは最近姿をなかなか見ることができなくなりました。レッドデータブックで栃木県では要注目となっていますが、より上位にしてもよいのではというくらい数が減りました。武茂川系の水路にいたことが非常に良かったです。
今回の授業は2つのことを示してくれたと思います。ひとつは八溝の自然が豊かであること。この短時間でこれだけの種類が見つかるということ。希少な種も含まれること。改めてこの自然を大切にしたいです。もうひとつは、生徒の知識と経験と技術。3年間で様々なことを学び、教員のアドバイスを受けずに41種を集めることができたことを頼もしく思いました。ちなみに、最も多くの種類を見つけたのは3人で、それぞれ31種でした。
最後は、生物が生息していた場所に生きたまま戻しました。
水産科3年生「海洋生物」の授業で、この授業としては高校最後の水辺のガサガサによる水生生物採集を行いました。水産科実習場周辺の農水路やビオトープにおいて、自由に生物を採集するという授業です。与えられた課題はちょうど一時間をかけて誰が一番多くの種類を捕まえることができるか。水温の低くなったこの時期、どのような水生生物がどこにどのようなかたちで生息しているかを推測し、採集するというものです。採集した後は、用意された各種図鑑をもとに種の同定を行います。採集方法と場所は自分で考えます。一番多くの種類を見つけることができた人に豪華賞品をプレゼントするという人気企画です。


結果、クラス全体で合計41種類の生物を採集、同定できました。種は間違いなく違うけど同定できなかった生物もいましたので、実際にはもっと多くの種類が見つかっていたのかもしれません。内訳は次の通りです。
甲殻類3 アミメカゲロウ1 カゲロウ3 カメムシ3 カワゲラ2 トビケラ1 コウチュウ2
トンボ9 ハエ類1 軟体動物5 両生類2 魚類6
このうち、両生類でカジカガエルおよびヤマアカガエルが捕れるのはこの時期ならではであることと、山間部であることを示しているのかもしれません。魚類はカジカとアブラハヤが捕れました。アブラハヤは最近姿をなかなか見ることができなくなりました。レッドデータブックで栃木県では要注目となっていますが、より上位にしてもよいのではというくらい数が減りました。武茂川系の水路にいたことが非常に良かったです。
今回の授業は2つのことを示してくれたと思います。ひとつは八溝の自然が豊かであること。この短時間でこれだけの種類が見つかるということ。希少な種も含まれること。改めてこの自然を大切にしたいです。もうひとつは、生徒の知識と経験と技術。3年間で様々なことを学び、教員のアドバイスを受けずに41種を集めることができたことを頼もしく思いました。ちなみに、最も多くの種類を見つけたのは3人で、それぞれ31種でした。
最後は、生物が生息していた場所に生きたまま戻しました。
水産科3年サケ採集
11/12(木) 毎年水産科3年生の恒例実習、武茂川遡上サケの採集を行いました。
今年はサケの遡上数が激減し、昨年まであれだけたくさん遡上していたサケの群れが全くといっていいほど見られませんでした。わずかに見られるサケを採集し、人工授精を行いました。今後ふ化させた稚魚を飼育し、ある程度のサイズに成長させて再度武茂川に放流することにより、資源の維持を図るという目的で実習を行っています。
人工採卵が終わったサケは、小さく切り刻み、魚醤の製造に活用します。採集することは一見残酷なようですが、親魚を確保することで資源を維持し、本来ならば川の異臭につながる産卵を終えたサケの亡骸を生じさせずに有効活用することができるのです。
しかしながら、サケの遡上数が大きく減少していることは極めて大きな問題です。原因は多種多様に考えられているところだと思います。原因が何であれ、いろいろなことを考えさせられます。治水工事は本当に大切ですが、サケやアユなど水産上重要種はもちろん、生物多様性を大切にした河川のあり方の論議は必要だと思います。また、コクチバスをはじめとした外来魚の生息がサケの稚魚期に及ぼす影響も詳しく調査する必要があるかもしれません。その他挙げたら五指では足りないのでしょうが、いずれにせよ、生徒にとってはそのすべてが勉強です。ひとつひとつを大切に学んでほしいです。
今年はサケの遡上数が激減し、昨年まであれだけたくさん遡上していたサケの群れが全くといっていいほど見られませんでした。わずかに見られるサケを採集し、人工授精を行いました。今後ふ化させた稚魚を飼育し、ある程度のサイズに成長させて再度武茂川に放流することにより、資源の維持を図るという目的で実習を行っています。
人工採卵が終わったサケは、小さく切り刻み、魚醤の製造に活用します。採集することは一見残酷なようですが、親魚を確保することで資源を維持し、本来ならば川の異臭につながる産卵を終えたサケの亡骸を生じさせずに有効活用することができるのです。

しかしながら、サケの遡上数が大きく減少していることは極めて大きな問題です。原因は多種多様に考えられているところだと思います。原因が何であれ、いろいろなことを考えさせられます。治水工事は本当に大切ですが、サケやアユなど水産上重要種はもちろん、生物多様性を大切にした河川のあり方の論議は必要だと思います。また、コクチバスをはじめとした外来魚の生息がサケの稚魚期に及ぼす影響も詳しく調査する必要があるかもしれません。その他挙げたら五指では足りないのでしょうが、いずれにせよ、生徒にとってはそのすべてが勉強です。ひとつひとつを大切に学んでほしいです。
馬頭小学校交流 サケの観察
11月10日(火)風の冷たさを感じつつも快晴の日差しを浴びる天候に恵まれ、馬頭小学校の4年生49名と本校水産科3年生12名が武茂川河川敷にて交流授業を行いました。
前半は、1組が武茂川を遡上してきたサケが泳ぐ様子や産卵床などを観察し、武茂川の環境、サケ漁の仕方や道具などの解説を本校生が行いました。2組はサケの一生についての解説を聴き、武茂川で生まれたサケがアラスカ周辺まで回遊した後数年かけてもう一度武茂川に戻ってくることを学びました。実際に投網で捕まえたサケを観察し、雄と雌の特徴や違いについてスケッチを通して学習しました。後半はクラスを変えて同じ学習活動を行いました。小学生はサケの大きさやかっこよさに大きな歓声を上げ、中には鋭い質問で高校生が答えられない場面もありました。
最後には、那珂川町にはサケが遡上する素晴らしい川があること、そしてサケが遡上し続ける環境をみんなが守ってほしいというメッセージを伝え、交流授業を終えました。本校生にとっても、学んだことを小学生に伝える本当によい機会となりました。
前半は、1組が武茂川を遡上してきたサケが泳ぐ様子や産卵床などを観察し、武茂川の環境、サケ漁の仕方や道具などの解説を本校生が行いました。2組はサケの一生についての解説を聴き、武茂川で生まれたサケがアラスカ周辺まで回遊した後数年かけてもう一度武茂川に戻ってくることを学びました。実際に投網で捕まえたサケを観察し、雄と雌の特徴や違いについてスケッチを通して学習しました。後半はクラスを変えて同じ学習活動を行いました。小学生はサケの大きさやかっこよさに大きな歓声を上げ、中には鋭い質問で高校生が答えられない場面もありました。
最後には、那珂川町にはサケが遡上する素晴らしい川があること、そしてサケが遡上し続ける環境をみんなが守ってほしいというメッセージを伝え、交流授業を終えました。本校生にとっても、学んだことを小学生に伝える本当によい機会となりました。

水産科3年生那珂川カヌー下り
11月5日(金)快晴のベストコンディションの中、毎年恒例の那珂川カヌー下りが実施されました。本来ならば、アユ釣りが解禁される直前の5月末に実施される予定でしたが、コロナウイルス感染対策として延期となっていました。最も心配だったことは11月になったことによる水温低下と天候の悪化でしたが、生徒の日ごろの行動が良かったのか、これ以上ないほどの雲と風のない温暖な一日となりました。
変更は時期だけでなく、航程自体も大幅に縮小しました。水産科3年生は、全部で12名。担任と指導教員と合わせ、15艇のカヌーが例年よりもゆっくりと大松橋から那須烏山市落石地区までのおおよそ14㎞を、時間をかけて下りました。ちょうどアユが産卵のため川を下り始めており、アユ釣り師の姿はまばらとなり、興野大橋下の堰には落ちアユを待つ投網を持った漁師が並んでいました。一方で上流とへ向かう大魚を凝視する釣り師の姿も見られました。ここ数年、すっかり遡上数を減らしてしまっているサケを狙っているようです。例年ならば新緑の中をですが、今年は赤く色づき始めた山々を背後に、生徒たちは瀬に見え隠れする岩や変化に富んだ流れにも集中しながら、3年余りを共にしてきた仲間とともに雄大な那珂川を下りました。


なお、当日は下野新聞社や那珂川テレビの取材を受けて報道されました。新聞のリンクは下記の通りです。
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/381166
変更は時期だけでなく、航程自体も大幅に縮小しました。水産科3年生は、全部で12名。担任と指導教員と合わせ、15艇のカヌーが例年よりもゆっくりと大松橋から那須烏山市落石地区までのおおよそ14㎞を、時間をかけて下りました。ちょうどアユが産卵のため川を下り始めており、アユ釣り師の姿はまばらとなり、興野大橋下の堰には落ちアユを待つ投網を持った漁師が並んでいました。一方で上流とへ向かう大魚を凝視する釣り師の姿も見られました。ここ数年、すっかり遡上数を減らしてしまっているサケを狙っているようです。例年ならば新緑の中をですが、今年は赤く色づき始めた山々を背後に、生徒たちは瀬に見え隠れする岩や変化に富んだ流れにも集中しながら、3年余りを共にしてきた仲間とともに雄大な那珂川を下りました。


なお、当日は下野新聞社や那珂川テレビの取材を受けて報道されました。新聞のリンクは下記の通りです。
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/381166
令和2年度高校生未来の職業人育成事業1日目
今年度、本校で初めて高校生未来の職業人育成事業に応募し、昨年度から養殖に取り組んでいるオニテナガエビについて「オニテナガエビの養殖改善と普及」を目標に掲げ、活動を始めました。
10月27日(火)
初回となるこの日は、地元川魚店である林屋さんとなかがわ水遊園さんをお迎えして、本校の取り組みと課題について意見交換会を行いました。いただいたアドバイスをもとにまずはふ化幼生の生存率向上に向けて養殖方法を改善していきたいと思います。
今後予定されている2回目には成長した稚エビを見せられるよう頑張っていきたいです。


10月27日(火)
初回となるこの日は、地元川魚店である林屋さんとなかがわ水遊園さんをお迎えして、本校の取り組みと課題について意見交換会を行いました。いただいたアドバイスをもとにまずはふ化幼生の生存率向上に向けて養殖方法を改善していきたいと思います。
今後予定されている2回目には成長した稚エビを見せられるよう頑張っていきたいです。


課題研究発表会が行われました
10月15日【木】
本校で課題研究発表会が行われました。
今年はコロナウイルスの影響もあり、満足のいく研究が出来なかった背景もありますが、水産科の2・3年生および水産科学研究部のメンバーが発表をしました。
結果は以下のようになりました。
1位 「那須・大田原のイシガイ類の保全に向けて」
生息数が減少しているイシガイ類を市役所や漁協と連携し、保全を行っていこうという内容で、2年間の集大成となる発表でした。
研究者である永田くんは、関東・東海地区への出場権を獲得したました!今年度はビデオ審査となりますが、より発表態度を磨き上げてほしいと思います。

2位「オニテナガエビで町おこし」
こちらも3年生による継続研究です。昨年度ふ化に失敗した経験から、飼育方法を改善し、見事ふ化、稚エビ、親エビへと成長させることができました。那珂川町の名産品になる日は近いかも!?

3位「内水面漁業の振興~鮎釣りをもっと身近に~」
2年生による新規の研究です。高額で費用のかかる鮎釣りの道具を、安価な値段で購入出来る道具を代用して、気軽に鮎釣りを楽しもうという研究。見事手作り竿でアユを釣ることができました。来年に期待です。
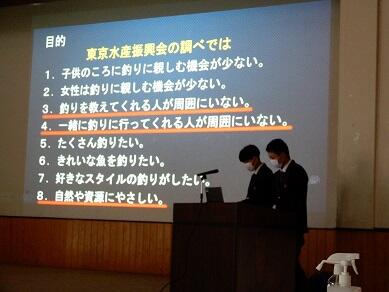
フォトアルバム
HP閲覧者数
0
2
2
4
0
4
9
6









