スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです
令和7年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会
今年度も盛大にSSH研究成果発表会を実施することができました。
各Roundに分かれて、2年次生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)や3年次生によるハイブリッドゼミの発表(口頭発表)が行われました。またグループ研究として、SSHクラブの各研究班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。それぞれの会場では、発表が行われただけではなく、活発に質疑応答や意見交換などがなされ、有意義な交流が行われていました。1年次生も積極的に発表を見て、聞いて、学びを得ようとする様子が窺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったのではないでしょうか。3年次生はこれまで助言等で関わってきた2年次生の発表に対して質疑応答や助言を送り、後輩のためにしっかり役割を果たしてくれました。今年度は新たにタイのカセサート大学附属高校と交流を開始し、発表会当日は交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校と本校を合わせた3校で、互いの研究発表をオンラインで行うことができました。英語での質疑応答は大変刺激になったことと思います。
また、新しい取組として、当日は市内の神明宮境内においてSSHクラブ数学班による数学イベントと研究発表を行い地域の皆様と交流することができました。
開催にあたり、ご協力くださいました皆様、当日来場してくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
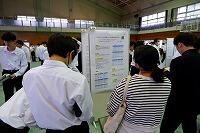
ポスター発表(第2体育館) ポスター発表(第2体育館)

口頭発表(各教室) 口頭発表(各教室)


口頭発表(第一体育館) 全体会での口頭発表 全体会

神明宮境内での数学イベント 神明宮境内での数学班の研究発表





