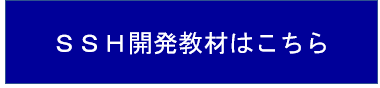SSH事業の概要.pdf
Ⅱ期目とⅢ期目の相違点.pdf
栃高探究スタイルとは.pdf
クリックすると詳細が表示されます
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業とは、文部科学省が未来を担う科学技術系人材を育てることをねらいとして「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」指定し、理数系教育の充実を図る取り組みです。
高等学校等において、先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組、また創造性、独創性を高める指導方法、教材の開発等の取組を実施するものです。平成14年度から始まり、20年以上続く事業です。
SSHの概要について 科学技術振興機構HPへ
〈研究開発課題名〉
栃高探究スタイルで栃木から世界へ
―新たな価値を創出し国際社会に貢献する科学技術人材の育成―
第Ⅱ期までの成果を踏まえ、科学的素養(※)を身に着けた新たな価値創造に挑む人材の育成に向けて、大学や企業、研究機関等と連携・協力しながら、次の4つを事業の柱として取り組みます。そして、得られた成果の普及・発信にも努めます。
(1)一人一研究を軸とした課題研究指導法の深化
(2)STEAM教育の視点に立脚したカリキュラム・マネジメント
(3)先進的な科学系課外活動
(4)SSH事業の評価法の開発
※科学的素養とは…
本校のSSH事業を通じて育成を目指す生徒の資質・能力を「科学的探究力・情報実践能力・多様性理解力・創造的思考力」に整理し、これらをまとめたものです。
それぞれが示す力は次のとおりです。
〇科学的探究力
自然科学に限らず人文・社会科学も含めた幅広い興味や関心を基に、科学的な探究のプロセスを意識して行き来しながら、主体的に課題を発見し、解決に向かう力
〇情報実践能力
課題の発見・解決に向けて、ICT機器を駆使しつつデータサイエンスを効果的に活用して客観的なデータから情報を抽出し、多面的・多角的に精査・分析する力
〇多様性理解力
異なる言語環境や文化的背景がもたらす認識の枠組みや考え方の違いを的確に理解し、国際社会において他者と対話し協働していく力
〇創造的思考力
既存の概念を結び付け、困難な状況でも粘り強く挑戦し続ける姿勢をもって課題を問い直し、新たな関係性へと組み替えていくことで課題の解決をはかろうとする力
第Ⅲ期では、科学的な探究のプロセスを繰り返しながら主体的に課題を発見・解決する力や情報技術を効果的に活用してデータを読み解き考察する力を身につけ,価値観の多様性を受け入れて国内外の他者と積極的に協働していく力を高め,さまざまな学問分野の知を融合して新たな価値の創出に挑もうとする力を培うための教育プログラムの開発に取り組み,これらの力を駆使して不確実性の高い時代における世界の諸課題の解決に向けて挑戦し続けていく人材の育成を目指します。
スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです
令和7年度とちぎ探究活動・課題研究発表会で優秀賞を受賞
12月19日(金)に県教育委員会主催で開催された、令和7年度とちぎ探究活動・課題研究発表会に生徒2名が参加してきました。授業で取り組んできた「一人一研究」の成果をポスターで発表し、他校の生徒との質疑応答など交流し、刺激を受けてきました。
発表テーマ「重回帰分析を用いて人口を求める式を作る」
発表テーマ「卓球ラケットの位置ごとの弾み」
「重回帰分析を用いて人口を求める式を作る」の発表が「スーパーサイエンスハイスクール部門」で優秀賞をいただきました。

令和7年度SSH授業研究会を開催
12月19日に、スーパーサイエンスハイスクール授業研究会を実施しました。午前の研究授業では,A 数学/B 物理・英語/C 音楽の3種類の授業を,午後の研究授業ではD 美術・英語/E 国語・英語の2種類の授業を行い、見学いただいた方と研究協議を行いました。その後の全体会では、今回、いくつかの授業でも取り入れた、教科横断授業をテーマとしたグループ協議を行い、他教科、他校の視点を共有するとともに、19の授業アイデアを考えることができました。
ご参加いただいた方々、本当にありがとうございました。


授業動画による研究授業の様子 授業公開による研究授業の様子 全体会の様子
県高文連 自然科学部会研究発表会にて、物理部門と化学部門で最優秀賞を受賞
第7回栃木県高等学校文化連盟 自然科学部会研究発表会に、5つの研究テーマのグループが参加してきました。
結果は以下の通りです。
○物理部門
物理部(SSHクラブ物理班)
最優秀賞:「写真測量における地形測定の最適なデータ処理」
○化学部門
化学部(SSHクラブ化学班)
最優秀賞:「大谷石の銅(Ⅱ)イオン吸着能に関する研究」
優秀賞:「金属の表面積に関する研究」
○生物部門
生物部(SSHクラブ生物班)
奨励賞:「トルキスタンゴキブリの触角の破損と成長の関係」
奨励賞:「ザリガニに利き手はあるのか」
最優秀賞に選ばれました2つの研究グループは、来年度の第50回全国高等学校総合
文化祭(あきた総文祭2026)へ出場予定です。
今回指導助言いただきました内容を踏まえて、さらに研究に励んで参ります。




第3回「わが町Kawashiruプロジェクトwith栃高」実施報告
栃木市第四小学校の児童を対象に、市内で進行中の河川整備事業や防災対策について理解を深めてもらい、建設業の魅力を伝えるイベントを、栃木土木事務所と連携して実施しました。
現在、市内を流れる巴波川では、災害対策の一環として地下捷水路工事が進められています。本日は、小学校と工事現場をオンラインでつなぎ、現場担当者へのインタビューを通じて工事の様子や概要を紹介する「現場リポート」を本校生徒が行いました。
質問コーナーでは、工事内容に関する質問に加え、「勉強は難しいですか?」「好きな教科は何ですか?」といった小学生ならではの質問も飛び出し、市内の小学生と交流する貴重な機会となりました。これからも地域の小中学生との交流を大切にしながら、楽しく学べる機会をつくっていきたいと思います。
このような機会を創出してくださった栃木土木事務所ならびに現場の皆様に、心より感謝申し上げます。
※巴波川における改良復旧事業については、
栃木土木事務所HP https://www.pref.tochigi.lg.jp/h55/index.html で紹介されています。

現場入口からの配信(この後中へ) 掘削機シールドマシンの実物大写真
SSHクラブ物理班 宇宙甲子園缶サット部門に参加しました
11月29日(土)にSSHクラブ物理班2年次生6名が、東金青少年自然の家で行われた「宇宙甲子園缶サット部門2025東京地方予選大会」に参加しました。
午前中には打上競技が行われました。自作した缶サットを、自作したモデルロケットにより打ち上げ放出し、自分たちが設定したミッションの実行、投下後にミッションの結果確認を行いました。午後は事後プレゼンを行いました。自分たちが設定したミッションの結果を自己評価し、今後の改良プランを発表しました。今回エンジンの不具合によりうまく打ち上がらなかったため、事前に行っていた実験データをもとにプレゼンを行いました。
本校は残念ながら上位2校には選ばれませんでしたが、他校の様子を見てよい刺激になりました。今後の研究活動に大いに役立てていきたいと思います。

【告知】令和7年度SSH授業研究会の開催について
本校では、SSH事業の一環で「STEAM教育の視点に立脚したカリキュラムマネジメント」と題し、教科横断型の授業を多数開発しています。
本年度も新たに教科横断型の授業を開発し、その授業についての研究会を行います。
期日は12月19日(金)となります。午前の部、午後の部を設定しましたが、午前のみ、午後のみ、終日での参加が可能です。
参加いただけますのは、全国のSSH指定校、県内高等学校および中学校の先生方、教育委員会事務局、大学等の各教育機関の皆さまとなります。
教科横断型の授業をどのようにデザインし、STEAM教育をどのように展開するか、全国の先生方と議論したいと考えています。
詳細は下記PDFをご覧ください。
オンラインでの参加も可能ですので、ご興味ある方は是非参加申込フォームよりお申込みください。
日本学生科学賞県大会にて最優秀賞を受賞
第69回日本学生科学賞栃木県大会において、以下の5点が入賞し、表彰式に参加してきました。
最優秀賞(知事賞)
SSHクラブ化学班「大谷石のイオン吸着に関する研究」
優秀賞
2年次生 個人研究「写真測量のカメラの傾きと精度」
2年次生 個人研究「ムペンバ効果と粘度の関係」
優良賞
SSHクラブ化学班「金属の表面積に関する研究」
2年次生 個人研究「卓球ラケットの位置ごとの弾み」
最優秀賞の受賞は第66回大会から4年連続となりました。
いただいた審査コメントをもとに、さらに研究に励んでいきます。
令和7年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会
今年度も盛大にSSH研究成果発表会を実施することができました。
各Roundに分かれて、2年次生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)や3年次生によるハイブリッドゼミの発表(口頭発表)が行われました。またグループ研究として、SSHクラブの各研究班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。それぞれの会場では、発表が行われただけではなく、活発に質疑応答や意見交換などがなされ、有意義な交流が行われていました。1年次生も積極的に発表を見て、聞いて、学びを得ようとする様子が窺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったのではないでしょうか。3年次生はこれまで助言等で関わってきた2年次生の発表に対して質疑応答や助言を送り、後輩のためにしっかり役割を果たしてくれました。今年度は新たにタイのカセサート大学附属高校と交流を開始し、発表会当日は交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校と本校を合わせた3校で、互いの研究発表をオンラインで行うことができました。英語での質疑応答は大変刺激になったことと思います。
また、新しい取組として、当日は市内の神明宮境内においてSSHクラブ数学班による数学イベントと研究発表を行い地域の皆様と交流することができました。
開催にあたり、ご協力くださいました皆様、当日来場してくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
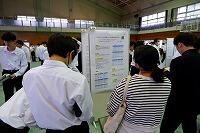
ポスター発表(第2体育館) ポスター発表(第2体育館)

口頭発表(各教室) 口頭発表(各教室)


口頭発表(第一体育館) 全体会での口頭発表 全体会

神明宮境内での数学イベント 神明宮境内での数学班の研究発表
1年次生 課題研究Ⅰ ゼミの進め方に関する講話
クラス単位の活動から今後は生徒1人1人がより主体的に活動ができるゼミ活動になります。この講話では、ゼミ活動について、1人1研究の進め方、SSH活動に関わる物品等についての説明を行いました。また、この講話の中で各ゼミがゼミ長と副ゼミ長を話し合いの中から決めました。これから10人1組のゼミ活動が始まります。
SSHクラブ物理班 千葉大学でのポスター発表で優秀賞を受賞
9月27日(土)にSSHクラブ物理班の1年次生3名が、千葉大学が主催する第19回高校生理科研究発表会に参加し、「ARマーカーを用いた目標位置追従システムの開発検証」についてのポスター発表を行いました。日頃の研究の成果を発表し、優秀賞を受賞することができました。
当日の発表の際には、審査委員の方々から多くの質問やアドバイスをいただきました。今後はいただいたアドバイスを基に、さらに研究活動に取り組んでいきます。
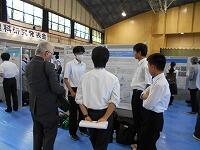
栃木県立
栃木高等学校
〒328-0016
栃木県栃木市入舟町12-4
TEL 0282-22-2595
FAX 0282-22-2534
※ 画像等の無断転載・引用を禁止します