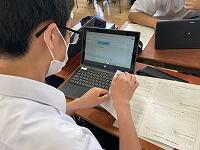スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです
1・3年次 課題研究Ⅰ・Ⅲ ハイブリッドゼミ成果発表
3年次生がハイブリッドゼミ活動の中で議論してきた成果を、1年次生に向けて発表しました。一人一研究を結び付けて考えた新しいアイデアを、その社会的・学術的意義なども踏まえて発表し、併せて結び付けた一人一研究の内容も紹介しました。1年次生からの質問に3年次生が答える場面や、3年次生が自分の探究活動の経験なども伝える発言もあり、異なる年次の生徒が交流する有意義な時間となりました。
1年次生にとって、これから一人一研究に取り組む際のヒントになればと考えています。
SSHクラブ定例会➂
8月に神戸で開催されるSSH生徒研究発表会に向けて、SSHクラブの代表として参加する化学班大谷石Gの発表リハーサルを行いました。質疑応答では伝わりにくい箇所など課題も明らかとなり、今後本番に向けてブラッシュアップしていきます。
また、各研究グループが4月から7月までの活動報告と今後の予定を発表し、共有しました。
1年次 課題研究Ⅰ 学問探究講義
1年次生では、6・7時間目の時間に学問探究講義を実施しました。宇都宮大学、群馬大学、茨城大学、自治医科大学から講師としてお招きした11名の先生に各分野ごとに大学での研究内容についてご講義いただきました。生徒は希望する2つの講義を受講しました。大学や学問分野への興味関心を深めるとともに文理選択の一助となる貴重な機会になりました。

大阪・関西万博 栃木県公式催事にてSSHクラブが取り組みを発表
大阪・関西万博の栃木県公式催事に本校SSHクラブ国際研究班がオンラインで参加しました。
栃木県公式催事の展示内容の1つ「次世代連携プロジェクト」において、山水共里をテーマに、栃木県を舞台にした研究活動の報告を栃木の魅力も交えながら行いました。
本校では、昨年度からマレーシアのロッジ国民中等教育学校と「土壌微生物電池の開発」に取り組んでいます。それぞれの国の土壌を用いたこの研究と、両校の交流の様子について、メンバーの2年次生4名が英語と日本語の両方で発表しました。
現地大阪からの質問もいただき、万博会場との交流を楽しむことができました。質問への返答では、SSHクラブ化学班が取り組んでいる栃木県の特産物である「大谷石」を活用した研究も紹介しアピールすることができました。
万博会場には行けませんでしたが、栃木県公式催事に参加させていただき、生徒職員共々、貴重な経験をさせていただきました。関係者の皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

栃木県のページ
栃木県/2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に向けた取組について
1年次 課題研究Ⅰ 一人一研究ガイダンス
1年次生では、いよいよ始まる一人一研究のガイダンスを行いました。テーマを設定するうえで重要となることや、テーマ設定の仕方、また物品や書籍の購入申請の仕方などの基本事項について説明しました。まずは夏季休業中に、興味のある分野についての先行研究を調べ、仮の研究テーマを設定する活動からスタートします。今後、どのような研究を進めていくのかが楽しみです。
2・3年次 課題研究Ⅱ・Ⅲ 2年次生への助言(対面)
今日は、先週の事前活動でまとめた2年次生へのアドバイスをベースにして、対面で2年次生のポスターに対して助言をおこないました。最初は緊張した場面も見られましたが、次第に意見が活発に飛び交うような様子が多くみられるようになりました。すでに一人一研究を経験した3年次生からの助言は、実体験に基づいた貴重なもので、有意義な時間を過ごすことができました。今回の活動を通して、2年次生のポスター及び一人一研究がより発展していってほしいです。

3年次 課題研究Ⅲ 2年次生への助言
今日は、2年次生が作成した一人一研究のポスター(初版)について、3年生が課題研究で培ってきた経験を生かして、検討会をおこないました。必要に応じて資料やインターネットを活用して、様々な視点から議論をしていました。次週は、今回議論をしたことをベースに2年次生へ対面で助言をおこなっていきます。
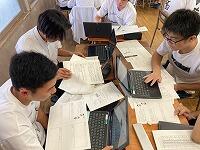
授業実践事例 数学科×美術科×家庭科
「STEAM教育の視点に立脚したカリキュラム・マネジメント」は本校SSH事業の4本柱の一つです。
今年度は「一人一実践」を掲げ、全教員で授業カリキュラム開発に向けて授業実践に取り組んでいます。
本日は、数学科と美術科と家庭科の教科横断・分野融合の授業が行われました。身近にある正弦曲線をテーマに、円柱の断面や洋服の型紙に隠れる曲線について、証明などに取り組みました。数学科の2名の教員が実践し、それぞれが異なるアプローチを試みました。今後検証し、実践事例も増やしながら研究開発を推進します。
なお、授業実践事例については、年度末にすべての事例を授業実践事例集『プラスワンの試み』としてまとめ、県内外に配布する予定です。また、教材開発のページにも後日、資料等を掲載していきます。


3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動④
課題研究Ⅲでは、これまで新たなアイデア(価値)、学術的・社会的意義を検討してきました。今日はこれまで考えてきた内容をパワーポイントにまとめるという作業をしました。7月にはこの資料を用いて1年生に発表するということもあり、どの班も力を入れて作成に臨んでいました。


1年次 課題研究Ⅰケーススタディ「まとめと発表準備」
前回の授業ではグループごとに実験・検証を行いました。本日は、そのデータをもとに、クラスで発表するための資料を作成しました。先輩の研究の、どのような点を工夫して実験し、どのような結果が得られたのかについてグループごとに話し合いながら資料を作成しました。夏季休業明けの発表に向けて、引き続き作業を続けていきます。
日本色彩学会第56回全国大会[米沢]’25に生徒が参加してきました。
6月7日(土)に山形大学米沢キャンパスで開催された、日本色彩学会全国大会に3年次生2名が参加してきました。2年次までに授業で取り組んできた課題研究(一人一研究)の成果を基に、口頭発表やポスター発表に臨みました。研究者の方々や大学生、他校の高校生との質疑応答では、様々な学びがあり、貴重な経験となりました。参加までサポートしてくださった日本色彩学会の皆様には、この場をお借りして感謝申し上げます。
以下、生徒の振り返りから抜粋
「自分は大学や大学院で研究をしたいと思っていたので学会発表や交流会を通じてそのビジョンが明確になった。進路が決定していない高校三年生のこの時期だからこそ学会に参加できてよかったと思う。」
「口頭発表で参加しましたが、発表の後の質問の際、何人かの研究者の方から鋭い質問やアドバイスをもらいました。研究を本職としている方たちからのものだったので、発表者として良い経験になり、研究において有意義なことを学ぶことができました。」


1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「ケーススタディ実験」
課題研究Ⅰでは、先週の授業においてグループごとに立てた実験計画をもとに、実験を実施しました。想定通りに進んでいるグループもあれば、予想とは違ったデータとなったグループもありましたが、どのグループも試行錯誤しながら主体的に取り組んでいました。次週は、本日得られたデータをまとめる作業に入ります。
2年次生 課題研究Ⅱ 課題研究表現講座② 結果・考察・結論
今回は1年次で学んだ結果・考察・結論の書き分けを復習し、特に、結果の取り扱い方を中心に、昨年度から取り上げ始めた仮説検定について本校教員が講義を行いました。過去の先輩のポスターを例に,結果の値についてt検定を用いて考えました。平均値の比較だけではなく、根拠を持った値で実験結果を分析することができることを学びました。今後のクラス別の課題研究Ⅱの時間では、本日の講座を踏まえて、実際に自分の研究結果や仮の値を基にPCで演習を行っていきます。数学や情報での学びを踏まえつつ、より実践的な経験を積んでいければと思います。
1年次生への吉田校長講話
「STEAM教育の視点に立脚したカリキュラム・マネジメント」は本校SSH事業の4本柱の一つです。
今年度は「一人一実践」を掲げ、全教員で授業カリキュラム開発に向けて授業実践に取り組んでいます。
本日は、吉田校長が1年次生に向けて、専門教科の数学をテーマにしつつ、関連する地球や宇宙、古典の話を交えて講話をしました。将来社会を担う栃高生に向けた激励のメッセージやこれから3年間、探究活動に取り組む生徒へ向けたエールも含まれる、あっという間の1時間でした。
吉田校長お疲れ様でした!

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「ケーススタディ実験計画」
課題研究Ⅰでは、グループごとに分かれ、担当するテーマの実験計画を考えました。先週までの講座と演習で学んだ内容をふまえて、どのような方法で実験すべきかを具体的に考えました。この実験計画をもとに、次週は実際に実験を実施する予定です。
課題研究Ⅱ ゼミ議論を受けてポスターの修正
本日は、前回までにゼミで議論した内容の修正や今後の活動について相談をしました。
生徒たちは自身のHRでポスターの改善や今後の計画の練り直しに取組み、ゼミ担当の先生方は、各HRを回りながら分野別ミーテイングで担当となっている生徒に声をかけ、進捗確認や生徒からの相談に乗っていました。
1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「結果・考察・結論の講座」
課題研究Ⅰでは、結果・考察・結論の書き方についての講座と演習を行いました。探究活動を論文やレポートにまとめるとき,結果、考察、結論は欠かせません。それらの違いや書き分け方、結果を示す際のデータに対するグラフの選び方など、グラフの特性も併せて学びました。講座後には、グループごとに分かれ、先輩の研究内容を題材にして改善案を考えました。
3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動③
今日の課題研究Ⅲでは、前回までの活動で考えた新たなアイデア(価値)に対して、どんな学術的・社会的意義があるのか。そして、そのアイデア(価値)を生み出すにはどのような実験や研究をしたらよいのかという点について議論をしました。今までの経験を活かし、積極的に活動に取り組んでいました。
課題研究Ⅱ ポスター作成 ゼミ議論
今日は、先週に引き続き、各自が研究をポスターにまとめたものを持ち寄って議論するゼミ活動を行いました。先週が5人、今日が5人と2週に分けて実施しています。今回も、序論~検証方法までの各項目について、ルーブリックやテキスト等を参考に、より良い研究を目指して改善案などについて議論しました。
1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「仮説と検証方法の講座」
1年次生では、課題研究Ⅰの授業において、仮説と検証方法についての講座と演習を行いました。仮説を立てるうえで重要なことは何か、また検証方法を考えるときに気を付けなければならないことは何かについて、講座を通して学びました。講座後には、先輩の研究内容を題材に、グループごとに改善案を考えました。