  |

文字
背景
行間
令和7年3月20日、駒澤大学駒澤キャンパスにて行われました表題の会におきまして、リベラルアーツ同好会1年の大島心緒さん、山寺紗耶さんの2名が研究発表を行って参りました。
研究は「地理院地図において地図記号で表示される病院とされない病院があるのはなぜか」という疑問から始まり、古い年代の地図や病院の沿革史などの文献にあたることで、明治期から現在までの矢板の医療体制の変遷の様相を明らかにする、というのものでした。
午前中の高校生同士で研究内容を発表しあう交流会を経て、午後は持参したポスターの前での発表を行いました。高校生や大学生、他校の先生方、大学の先生など、多くの方がポスターを観に来てくださり、その都度(のべ15回ほど)発表と質疑応答を行いました。発表の内容や態度は繰り返す度に洗練されていき、質疑応答を通して新たな研究の視点や方法に気づくなど、実り多き時間となりました。また、他校の高校生の発表にも触れ、さまざまな研究の切り口があることもあらためて学ぶことができました。今回得た知見を含め、さらに研究を深掘りさせていきたいと思います。
最後になりますが、今回の研究に際しまして多大なご協力をいただいた方々へ、感謝の意を申し上げます。今後とも、リベラルアーツ同好会をよろしくお願い致します。

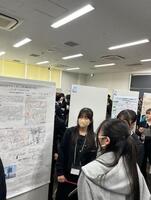
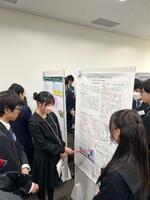
3月は、ほぼ毎週末に練習試合を実施しており、これまで出場機会の少なかった1年生が活躍する場面も多く見られました。レシーブが上達していたり、他選手のミスをカバーできるようになったり、と成長が感じられます。
2年生は引退や受験勉強を意識するようになり、1年生は後輩ができることに楽しみ半分、不安も半分といった様子です。まもなく新年度を迎えますが、更なる飛躍を遂げてくれることを期待しています。
(文責:森本 聖也)
2学年「総合的な探究の時間」において、今年度に取り組んだ課題研究活動をプレゼンテーションする【学年発表会】を開催しました。
2年生徒は、昨年度、「興味探究型」と銘打ち、自身の興味のあることについてとことん探究(半径5mの探究)することで、「探究のサイクル」を回すことや、探究計画書、レポートの書き方等を練習しましたが、今年度は「課題解決型」と銘打ち、自身の興味と社会課題を関連させて考える探究(半径5mからの探究)を行ってきました。
1学期。生徒たちは1年次の探究テーマを踏まえて、8つのカテゴリーを選択し、ゼミに所属しました。
この8つのゼミは、2学年の担任・副担任・学年総副担任がファシリテーターを務め、生徒たちの探究活動を見守り、助言、支援しました。
2学期。生徒は夏休みや冬休みといった長期休業中、あるいは学期中の部活動や勉強の合間を縫って、フィールドワークやインタビュー等を行って、オリジナリティのある探究活動を目指してきました。
10月にゼミごとに行った<中間発表会>では生徒同士で議論をしたり、アドバイスを送り合ったりすることで、探究をより良いものにするために試行錯誤を繰り返してきました。
そして、3学期。1月中旬に実施した【ゼミ発表会】でゼミ生の投票やゼミ担当の教員の評価によって代表グループを決め、今回の【学年発表会】を開催しました。
学年発表会の以下の通りです。(発表順)
①検索機の可能性の追求
②高齢者を自動車事故から救う「ガルドシート」
③ピーマンパウダーの最適解
④茶殻の食材としての活用方法の提案
⑤プラスチック問題と酪農家が抱える問題を解決する新しい食品トレー「ReBone」
⑥納豆をヒーローに!!
⑦阿久津城の保存に向けて
⑧騒音を気にせず楽器の練習をする方法
⑨赤ちゃんから高齢者まで使える人形型ロボット「ハモリス」
⑩障がい×スポーツ×ボランティアで矢板市をつなぐ
どの発表もすばらしいプレゼンテーションで、質疑応答も活発に行われました。
生徒たちの取り組みを見ると、多くの生徒が熱心にグループメンバーやファシリテーターと対話し、調査や手法を再検討しながらアンケートや取材などの活動を行うことで、当初持っていた考えや仮説が覆され、新たな結論が導き出される様子が見られました。
これは活動の中で、生徒たちが「変容」していった結果です。
学年全体の取り組みとして、成果物の出来具合だけを見ると、まだまだ未熟な部分が多くあると思われます。しかし、今回の活動の過程によって自身の価値観が揺り動かされ、知的好奇心の涵養や進路研究の進展のみならず、一人一人が<どのような「人生」を送るか>について考えるきっかけになってくれれば、大げさかもしれませんが、担当としては嬉しいかぎりです。
末筆にはなりましたが、2学年の総合的な探究の時間の取組にご支援、ご協力いただいた、専門機関、地域、ご家庭の皆様方をはじめ、かかわって下さったすべての皆様に感謝の意を表し、実施報告とさせていただきます。
今後とも、本校の「総合的な探究の時間」の取り組みにご注目いただければ幸いです。
文責:総合的な探究の時間係・主任 星野廣之
3月20日(祝)に日本経済大学お茶の水キャンパスにて開催された「第7回高校生サイエンス研究発表会2025」(主催:第一薬科大学、日本薬科大学、横浜薬科大学)に、2年生の3グループが参加しました。
この発表会は、高校生のプレゼンテーション能力向上と研究・開発への意欲向上とを目的としたものであり、事前に「テーマ」と「発表要旨」を作成し、発表が認められた生徒が大学に赴いてポスター発表の機会が与えられるイベントです。
生徒たちはポスターの作成、発表の準備等を工夫して今回の発表会に臨むことができました。
準備には他の活動でポスター発表を経験したことのある同じ2年生の生徒数名がポスター作成や発表のアドバイスをしてくれました。「学年の皆で学び合っている様子」がうかがえて、担当として非常に嬉しい出来事でした。
当日は、緊張もある中、参加者や大学の先生方の質問にもよく考えて回答しました。発表後はたくさんのアドバイスをいただき、自身の研究の課題が明確になったり、今後の方向性を再確認したりすることができたのではないかと思います。
参加した生徒からは「ハイレベルな発表を聞くことができてすごく刺激になった」「こんなことに興味を持っている人がいるんだ、こんな世界があるんだ、ということが知れて面白かった」「また発表したい」といった感想がありました。
今回の経験を、3年生になってからの学習や、大学等の進路への展望に活かしていってもらえれば幸いです。
末筆になりますが、運営にご尽力いただいた主催者の皆様、研究活動にご協力いただいたすべての皆様に感謝の意を表し、参加報告といたします。
文責:指導担当 星野廣之
本校2年生の相ケ瀨大翔さん、石塚瑠斗さんが「中高生探究コンテスト」(主催:株式会社CURIO SCHOOL)で【セミファイナリスト】に選出されました。
「中高生探究コンテスト」は、全国の中高生が学校で取り組んだ探究内容について発表し、競うコンテストです。
相ケ瀨さん、石塚さんは、総合的な探究の時間で取り組んだ「大好きな納豆をとことん調べる!!」をテーマにした探究活動を発表し、参加生徒数10,117名の中から、188組のセミファイナリストに選出されました。
惜しくも10組のファイナリストには選出されませんでしたが、運営の方からオンラインでいただいたフィードバックの際には「紙一重。素晴らしい探究だった。下を向く必要はないので、これからも探究を続けてほしい」と激励していただきました。
相ケ瀨さん、石塚さんは、自分たちが興味を持ったことについて、「とことん」追究するために、多くの情報を調べ、実験したり、観察したりしながら試行錯誤を繰り返しました。
あえて失敗をさらけ出し、思考の跡を残したことが「高校生らしい」「等身大の」探究活動としての評価につながったのではないかと思います。
2人は今後も探究活動を継続し、自分たちが大好きな納豆を突き詰めていきたいと話しておりました。
サッカー部、バスケットボール部に所属する両名、勉強と部活動の合間を縫ってのナイスチャレンジだったと感じております。
末筆にはなりましたが、コンテストの運営にご尽力いただいた主催者の皆様、探究活動にご助言いただいた方々に感謝の意を表し、報告とさせていただきます。
今後とも、本校の探究活動へのご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
文責:指導担当 星野廣之