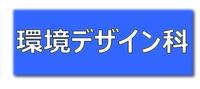文字
背景
行間

本学科で販売される野菜等の生産履歴を掲載しています。
いちご.pdf トマト.pdf ジャガイモ(農業と環境).pdf
ハクサイ(農業と環境).pdf ダイコン(農業と環境).pdf
ブロッコリー(農業と環境).pdf New!!
購入された際には、ぜひご確認ください。
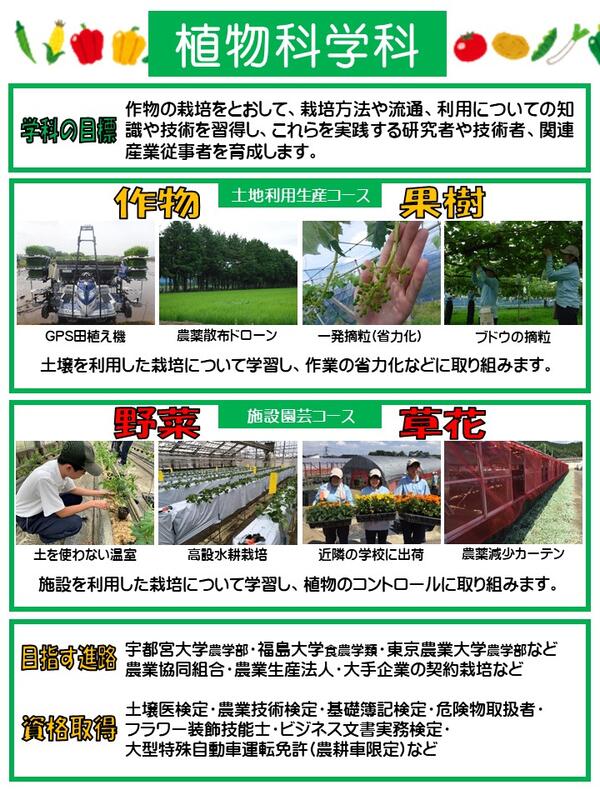
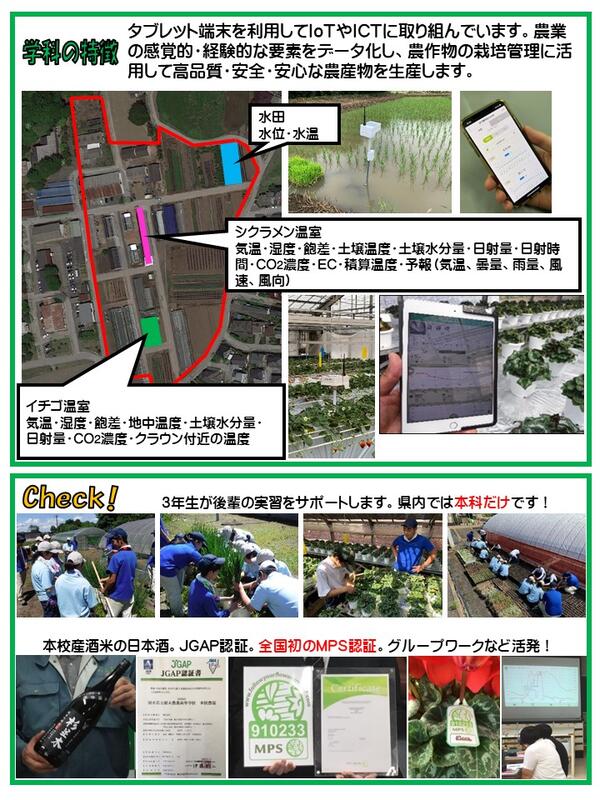
植物科学科日誌
【植物科学科】麦種まき
11月に入り作物部門で麦の種まきを行いました。
本校にある畑では小麦を、岩舟農場では二条大麦(もち麦)の種まきを行いました。
学校には種をまく機械がないので、どちらの農場でも手押しの播種機を使って丁寧に作業しました。
収穫は、来年の6月上旬ごろになるのでそれまでよく育つように管理していきます。
【植物科学科】コシヒカリ精米
今年度収穫したコシヒカリの精米、袋詰めを行いました。
こちらの白米(5kg入)は、11月15日の栃農祭で販売する予定です。
また、白米だけでなく玄米(30kg入)での販売も行います。
栃農祭にご来場予定の方は、品質が高く、食味も良い栃農米を是非お買い求めください。

【植物科学科】「にっこり」梨
生徒が大切に育ててきた本校産の「にっこり」を15日(土)の栃農祭で販売予定です。
「にっこり」は、栃木県農業総合研究センターで開発された品種で、栃木県が誇る観光地「日光」と梨の音読み「り」を合わせて名付けられました。
食べた人が「ニコニコにっこり」するようにという願いが込められています。
ご来場いただく予定の皆さまへ
秋の味覚である「にっこり」梨をご購入いただき、ご家族やご友人と一緒に「ニコニコにっこり」していただけると幸いです。
果樹専攻生一同より

【植物科学科】サツマイモ収穫
11月5日、本校で栽培していたサツマイモ(紅はるか)の収穫をしました。
このサツマイモは植物科学科2年生、土地利用コースの専攻している生徒が栽培していたもので、5月に植え付けてようやく収穫となりました。昨年は雨の影響などで収量が少なかったですが、今年は順調に生育した結果、多収で良いサツマイモを取ることができました。
獲れたものは、学校行事の収穫祭や授業等で活用していく予定です。
令和7年度とちぎものづくり選手権参加
10月25日(土)に県央産業技術専門校にて令和7年度とちぎものづくり選手権に植物科学科と環境デザイン科の生徒が2名がフラワー装飾職種に参加してきました。この競技では、バスケットアレンジを30分、ブートニアを20分で制作しました。


生徒2名とも時間内で作品も完成し、評価をしていただきました。競技終了後は、審査員の先生方に直接講評をいただくことができ、生徒たちの今後の技術向上のために大変有意義な時間を過ごすことができました。

審査結果は、10月29日(水)に栃木県のHPで発表があり、植物科学科の生徒が金賞、環境デザイン科の生徒が銀賞をとることができました。今後もフラワー装飾の技術を高めていけるように練習に取り組んでいきたいです。
【植物科学科】岩舟農場稲刈り(山田錦)
10月に入り岩舟農場では酒米の山田錦の稲刈りが始まりました。
収穫した山田錦は市内にある飯沼銘醸様に出荷し、日本酒の材料になる予定です。
良いお酒になるようにしっかり収穫していきます。
【植物科学科】ナシの収穫が始まりました
丹精込めて育ててきたナシの収穫が8月中旬より始まりました。
収穫したナシを選別し、丁寧に袋詰めをおこなっています。

【植物科学科】岩舟農場稲刈り(コシヒカリ)
2学期に入り、岩舟農場ではコシヒカリの収穫が始まりました。
主に2・3年生の実習で機械を使っての収穫・調整を行っています。普段、触ることがない機械を使っての作業なので慎重に操作しています。
また、1年生は手作業での収穫体験を行います。昔ながらの作業を体験することで食べ物のありがたみを感じることができました。
コシヒカリの収穫は9月下旬まで行う予定なのでおいしいお米が獲れるように作業を頑張っていきます。
3年生実習の様子
2年生実習の様子
1年生実習の様子
【植物科学科】本校水田田植えpart2
9月4日、本校にある水田で今年二回目となる田植えを行いました。
先週の8月29日に稲刈りを終えた田んぼを耕し、代かき(土と水を混ぜ泥状にし整地する作業)をして急ピッチで準備をしました。
3年生の作物専攻生も田植えに慣れているので順調に作業が行えました。
今後、二期作目がちゃんと生育し収穫できるか調査しながら管理していきます。
【植物科学科】本校水田稲刈り
8月29日、本校水田の稲刈りを行いました。
こちらの稲は、年に2回収穫する2期作という栽培について研究しているもので、田植えを年に2回行う区画と、稲刈りで残った株(ひこばえ)を再生させて収穫する区画の2つを用意し、栽培していました。
2度植えの区画は機械で収穫を行い、ひこばえの区画は高刈りをしなくてはいけないので手刈りで作業しました。
暑い中での作業でしたが、専攻生みんなで協力することで収穫することができました。
9月上旬には2回目の田植えを予定しているので頑張りたいと思います。
《のうくっく》は本校卒業生が制作