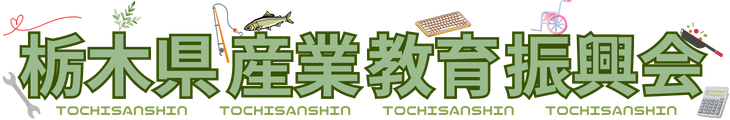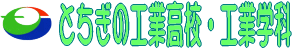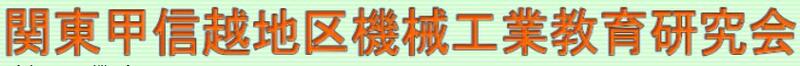文字
背景
行間
UK-Days/宇工デイズ
近江町市場 (修学旅行 1日目)
最初の見学地です!
賑わっています。

賑わっています。

兼六園で写真撮影 (修学旅行 1日目)
朝まで雨だったそうですが、来たらすごく天気がよくなりました。


【機械科B】 クラス別研修 (修学旅行 1日目)
機械科B組は、ひがし茶屋街に来ています。
ノスタルジックな雰囲気で、和の趣を感じる風情ある街並みを散策しています。

ノスタルジックな雰囲気で、和の趣を感じる風情ある街並みを散策しています。

昼食 (修学旅行 1日目)
ホテル金沢に到着し、待ちに待った昼食の時間です!


金沢に着きました! (修学旅行 1日目)
新幹線に揺られて金沢駅に着きました!


【機械科B】 あさま号からかがやき号へ (修学旅行 1日目)
2班 機械科B組は、あさま605号に乗り、長野駅に到着!
かがやき507号に乗り換え、金沢駅に向け再出発します!

かがやき507号に乗り換え、金沢駅に向け再出発します!

高崎駅より移動開始 (修学旅行 1日目)
高崎駅到着。ホームにて、乗車する新幹線を待っています。


高崎駅にて (修学旅行 1日目)
新幹線に乗車準備完了です!


出発(3) (修学旅行 1日目)
これから高崎駅に向かいます!
行ってきます。

行ってきます。

出発(2) (修学旅行 1日目)
11月30日月曜日、2学年の修学旅行バスは宇工を出発しました。北関東道でこれから高崎駅へ移動し、新幹線で金沢駅を目指します。


出発 (修学旅行 1日目)
いよいよ金沢に向け出発‼️


馬頭高校とのオンライン会議 (建築デザイン科)
令和2年11月24日(火)、建築デザイン科課題研究班は、馬頭高校とのオンライン会議を実施しました。
議題は、課題研究班が取り組んでいる「那珂川町地域協働研究」についてです。
本校からは今までの「那珂川町地域協働研究」への取り組みについて、馬頭高校からは「那珂川学」への取り組みについて報告がなされ、今後の連携や協働研究について意見交換をしました。
これからの馬頭高校との協働研究を楽しみにしています。




議題は、課題研究班が取り組んでいる「那珂川町地域協働研究」についてです。
本校からは今までの「那珂川町地域協働研究」への取り組みについて、馬頭高校からは「那珂川学」への取り組みについて報告がなされ、今後の連携や協働研究について意見交換をしました。
これからの馬頭高校との協働研究を楽しみにしています。




栃木県職業能力開発促進大会 参加(技能検定実技試験成績優秀者)
令和2年11月20日(金)13時30分から14時30分
栃木県総合文化センター サブホール(宇都宮市本町1-8)において、「栃木県職業能力開発促進大会」が開催され、昨年度行われた技能検定実技試験で成績優秀者の表彰が行われました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各事業所団体から出席者1名の制限ということで、本校から代表して機械科3年B組 樋口時生君が参加いたしました。
令和元年度 技能検定実技試験成績優秀者
普通旋盤作業3級 機械科3年B組 樋口時生
機械検査作業3級 機械科2年B組 高田綺斗
シーケンス制御作業3級 電子機械科3年 久我玲士
大工工事作業3級 建築デザイン科2年 金田未憂
【機械科】レーシングチーム活動講話&デモンストレーション走行
毎年この時期には、生徒たちが楽しみにしている施設見学会が行われていました。しかし、今年の状況下では実施が難しく、体育祭や学校祭などとともに中止が検討されていました。そんな中で、見学会に代わる行事として今回行われたのが、レーシングチームによる活動報告講話とデモンストレーション走行です。
多くの行事がなくなる中で、残念な思いを強いられている生徒たちを元気づけようと、協力を申し出てくださったのが『つちやエンジニアリング』の土屋武士さんです。その後多くの方のお力添えで今回の講話とデモ走行を実現することができました。
講話では、レースアナウンサーのピエール北川さんに軽快なトークで盛り上げていただき、土屋さんからは交通安全に関することや生徒たちに向けた熱いメッセージをお話しいただきました。
デモ走行では、大きな音で疾走するレーシングカーの速さと迫力に圧倒されました。また、走行後にはマシンを観察する機会を与えていただき、生徒たちは興味深く観察するなど、今回の行事を大いに楽しんでいるようでした。
このイベントにご協力してくださった、レーシングチームの方々やレース関係者の方々、走行にご配慮いただいた一般ドライバーの方々や雀宮地域の方々、南図書館や宇都宮南警察署の関係者各位に深く感謝申し上げます。


活動報告講演会 校内で走行準備と暖機運転


土屋武士さんとピエール北川さん デモンストレーション走行


ご協力いただいたレーシングドライバーの方々 見学やコックピット体験の様子
多くの行事がなくなる中で、残念な思いを強いられている生徒たちを元気づけようと、協力を申し出てくださったのが『つちやエンジニアリング』の土屋武士さんです。その後多くの方のお力添えで今回の講話とデモ走行を実現することができました。
講話では、レースアナウンサーのピエール北川さんに軽快なトークで盛り上げていただき、土屋さんからは交通安全に関することや生徒たちに向けた熱いメッセージをお話しいただきました。
デモ走行では、大きな音で疾走するレーシングカーの速さと迫力に圧倒されました。また、走行後にはマシンを観察する機会を与えていただき、生徒たちは興味深く観察するなど、今回の行事を大いに楽しんでいるようでした。
このイベントにご協力してくださった、レーシングチームの方々やレース関係者の方々、走行にご配慮いただいた一般ドライバーの方々や雀宮地域の方々、南図書館や宇都宮南警察署の関係者各位に深く感謝申し上げます。


活動報告講演会 校内で走行準備と暖機運転


土屋武士さんとピエール北川さん デモンストレーション走行


ご協力いただいたレーシングドライバーの方々 見学やコックピット体験の様子
文部科学省事業 技術経営(MOT)の講演会実施
11月18日(水)に日本工業大学大学院技術経営研究科の水澤直哉教授を講師に招き、2年生を対象に「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の一環として、技術経営(MOT)の講演会を実施しました。技術経営の定義や歴史と背景、今なぜ技術経営が重要なのか、技術経営教育の成果について等の講演をしていただきました。高校生にも理解しやすい例をあげながらの講演内容であったため、生徒達の理解も深まり、工業人であっても経営を学ぶ必要がある事を強く感じました。




機械科「キャリア形成支援事業」実施
11月16日(月)に日産栃木自動車大学校の先生方を講師に招き、機械科3年A組の生徒を対象にキャリア形成支援事業を実施しました。ロビンエンジンの分解・組立・始動の実習とブレーキパッドの着脱の実習を行いました。また、最新の自動車についての講義や自動運転技術、スポーツカー等の試乗も含め多くのことを体験しました。自動車に関する新たな理解を深めることができました。17日(火)には機械科3年B組の生徒を対象に実施します。




建築デザイン科「若年者建設業担い手育成支援事業」実施
11月12日(木)、13日(金)に建築デザイン科2年生を対象に「若年者建設業担い手育成支援事業」を実施しました。
建築技術コースは、建築大工に関する技術講習を中心に受講し、プロの高い技術力を目の当たりにしながら、大工技術の向上に役立てました。
住環境デザインコースは、室内パースの作図と彩色に関する技術講習を受講し、専門家ならではの彩色技術などを学び、図面の表現力の向上に役立てました。
〇建築技術コース
講師 株式会社 星居社 代表取締役 髙田 英明 様


〇住環境デザインコース
講師 宇都宮メディア・アーツ専門学校 信太 千紘 様 ・ 岡田 由実子 様


建築技術コースは、建築大工に関する技術講習を中心に受講し、プロの高い技術力を目の当たりにしながら、大工技術の向上に役立てました。
住環境デザインコースは、室内パースの作図と彩色に関する技術講習を受講し、専門家ならではの彩色技術などを学び、図面の表現力の向上に役立てました。
〇建築技術コース
講師 株式会社 星居社 代表取締役 髙田 英明 様


〇住環境デザインコース
講師 宇都宮メディア・アーツ専門学校 信太 千紘 様 ・ 岡田 由実子 様


令和2年度第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会出場
本校バスケットボール部が、11月8日(日)栃木県体育館で行われた令和2年度第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会栃木県予選会において文星芸大附属高校に119-94で勝利し、12月23日(水)より東京都で行われる本大会に出場が決まりました。栃木県代表として上位進出を目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。




旧職員から本をいただきました
先日、本校旧職員の茅島先生から多くの本をいただきました。現在その一部を図書館入り口のショーケースで紹介しています。読書の秋、茅島先生の「宇工生のためになれば」という思いが生徒の皆さんに伝われば幸いです。茅島先生ありがとうございました。
リスクマネジメント講演会開催

文部科学省指定 地域との協働による高等学校教育改革推進事業
-とちぎの「共創型実践技術者」の育成-実施日:令和2年11月4日(水)6限目
演題:『農業・JAにおけるリスクマネジメント』
講師:藤澤 勝 先生 (本事業の運営指導員)
対象生徒:2学年320名
講演内容:「リスクマネジメント」を工業高校生にも分かり易く、身近な話題を多く取り入れて講演いただきました。高校生活の中にもリスクマネジメントの考えを取り入れる場面が多くあることがわかりました。本校生が将来のとちぎの実践技術者として、リスクを上手にマネジメントしていくことができるよう期待しています。






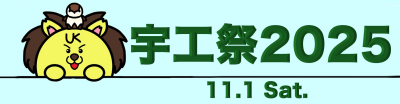


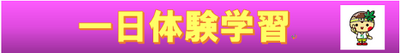


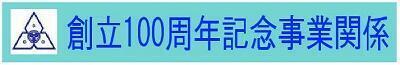
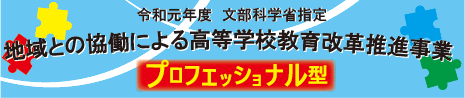

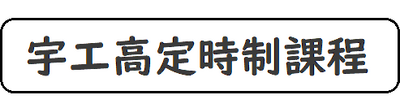
 栃木県教育委員会
栃木県教育委員会