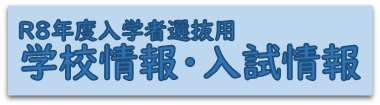 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
バナーをクリックすると各学科のページに移動します。

中国料理 ~人参の飾り切りに挑戦~
2年生の実技テストのひとつに「人参の飾り切り」があります。
ペティナイフ1本で人参から「花」を彫り出していきます。

先生はあっという間に美しい花をつくりあげ、生徒達はどのように手を動かしていたのか理解するまで時間がかかったようです。
実際に彫ってみると見るとやるのでは大違い。形にするのさえ困難でした。

1週間後の実技テスト。この1週間、生徒達は放課後残っては一生懸命に何個も花を彫っていました。彫っていく内にコツが分かり、彫るのが楽しくなった生徒も多くみられました。

お皿に盛りつけられた「花」
片方は生徒が彫ったものです。並べてみても遜色ありません!!


本当によく頑張りました。
『絵手紙』~日頃の感謝の気持ちを込めて
日本絵手紙協会公認講師の鈴木啓子先生に絵手紙の技法やルーツを教えて頂きました。

「ヘタでいい。ヘタがいい。」という絵手紙のこころえを胸に、真剣な顔つきで筆を持ちます
今回は、絵手紙の技法を箸袋作りに応用して、家族への感謝の思いを込めて作品をつくりました。

また、栄養食物科を卒業した先輩方へ、巻紙でエールを送りました。
鈴木先生に講評を頂き、褒められた生徒たちはとても嬉しそうでした

今日学んだことをこれからの日常生活にも是非活かして、潤いのある生活が送れるといいなと思います
鈴木先生ありがとうございました。
1級検定に向けて ~ かつらむき講習会 ~
全国高等学校家庭科食物調理技術検定2級検定が終わり、ホッとしたのも束の間・・・
12月には「1級検定」が予定されています。
1級検定では90分間でテーマに沿った供応食を調理します。また、指定調理が課せられ、今回は「大根のかつらむき」「二色ゼリー」に挑戦します。
そこで、3年生の総合調理実習でご指導頂いている舘田先生にお願いし、2年生に特別授業を実施して頂きました。
もちろんテーマは「大根のかつらむき」です。
先生のむいた大根は折敷が透ける位に薄く、また、ビックリするくらい長いです。
生徒達は目を丸くして一挙手一投足見逃さないように真剣に先生の様子を見ていました。
先生が簡単そうにリズムカルにむくのに対し、生徒達は皮をむく時点で悪戦苦闘していました。大根の持ち方、包丁の動かし方などを丁寧にご指導頂き、少しずつではありますがコツをつかんだようです。
「毎日、包丁を握ることが大切」先生のことばを胸に練習に励んで欲しいと思います
第51回 全国高等学校家庭科 食物調理技術検定2級
本日、栄養食物科2年生が本校にて食物調理技術検定2級に挑戦しました。
「17歳男子の通学用弁当献立」をテーマに献立作成、調理を行います。
50分という短い時間の中で、片付けまでを行わなくてはならず、何度も練習を重ねてきました。思い通りにいかず、悩んだこともあったと思います。
検定直前、生徒達の緊張と不安の表情に心配となりましたが、代表生徒の「検定、頑張ろう!」の掛け声で全員の気持ちがひとつとなり、前向きに取り組む様子が見られました。


出来上がりはそれぞれ思う所があったようですが、達成感や悔しい気持ち、期待を胸に次に向かって頑張って欲しいと思います。

ご協力頂きました保護者の皆様、先生方、大変お世話になりました。
いよいよ明日が本番です! ~食物調理技術検定2級~
新型コロナウィルスの影響で延期になっていた「第51回 全国高等学校家庭科 食物調理技術検定2級」が明日、実施されます。
例年に比べ実習方法も変更となり、生徒も職員も頭を悩ませ、試行錯誤しながらここまでどうにかやってきました。
今朝も準備のため、朝早くから手順を確認し材料を用意する姿が見られました。最初の頃に比べ、作品が上達したのはもちろんのこと。生徒達の表情にも自信が出てきました。
今までの頑張りがしっかりと実ることを期待しています。
今日はゆっくり休んで、明日に備えましょう。
温かくご支援頂いております保護者の皆様、引き続きご協力宜しくお願い致します。

食生活スキルアップ講話
栄養食物科では毎年、矢板市健康づくりみどりの会、矢板市健康増進課(管理栄養士、保健師)の協力を得て「生活習慣病予防のためのスキルアップ事業」を実施しています。
実際に調理を行い、減塩の大切さや食事の重要性を学ぶ良い機会になっているのですが、今年度は新型コロナウィルスの影響から中止となりました。
そこで、栄養食物科1年生を対象に「高校生における生活の課題と改善」3年生対象に「上手な減塩とカルシウム摂取について」講話をして頂きました。

1年生では高校生がどんな風に過ごせば良いのかを保健師さんが詳しく説明してくださり、生活習慣や生活リズムの大切さを学ぶことができました。夏休みでのんびり過ごしていた生徒達にとって、身近な問題に真剣に聞き入っていました。
また、3年生は1年次にお世話になった講師の方々との再会に初めは照れくさそうにしていましたが、講話が始まると積極的に参加する様子がみられ、さすが3年生と誇らしい気持ちになりました。この3年間で多くのことを学んだ上で聞く話は深く広く生徒の胸に刻まれたように思います。


お忙しい中、快くご講話してくださった講師の方々に厚く御礼申し上げます。また、来年も宜しくお願いします。
校内実習 最終日 ~ 調理師に求められること ~
いよいよ今日が校内実習の最終日となりました。初めての取り組みに反省、課題は多々ありますが、生徒の充実した顔をみていると実施して良かったと思います。
今日は三友学園 IFC栄養専門学校、IFC製菓専門学校から講師の先生をお招きし講話や実習をして頂きました。
栄養についての講話・演習では、カルシウムの体内における吸収の流れや骨量変化のメカニズムを詳しく教えて頂きました。また、栄養士と調理師の関係や大量調理における注意点を学び、実際の現場の厳しさや社会に出て求められることを実感したようです。
製菓では「カップ型シフォンケーキ」「シャルロット・フリュイ」の実習を行いました。
「ものづくりマイスター」でもある柿沼先生から繰り出される繊細な技の数々に生徒達は見とれていました。当初は失敗しないか不安だったようですが、講師の先生方が分かりやすく、ポイントを押さえてご指導くださったお陰で、見事な作品に仕上げることが出来ました。
ご指導くださいました講師の先生方、本当にありがとうございました。
校内実習4日目 ~ 栄食の絆 ~
校内実習も折り返しとなり、気も緩みがちな所ですが・・・
今日は卒業生による講話が行われ、生徒達はきりりと引き締まった表情を見せていました。


卒業年度が異なる4名(一番長い方は卒業後11年経っています)は、性別はもちろん、職業も異なります。共通項はというと「栄養食物科」を卒業し、食に関わる仕事に就き、夢に向かって頑張っていることです。

今回、新型コロナウィルスの影響で校外実習が実施できない後輩たちを想い、これから先の人生を考えるきっかけとなればと、今回の講話を引き受けてくれました。
年代を超え、つながる優しさを感じます。
生徒達はそんな先輩方の想いをしっかり受け止めてくれ、真剣に耳を傾けていました。
「自分の置かれている環境の中で前向きに、自分をしっかりと持つことの大切さ」
「近い目標、遠い目標を立て、それを実現するためにどうするか」「素直さ」等。社会に出てから必要なことだけでは無く、今と未来をつなげることを考える貴重な機会となりました。
講話をしてくださった卒業生の皆さん。本当にありがとうございました。
皆さんの頑張っている姿に大きな力をもらいました。明日も皆で頑張ります!!
校内実習3日目 ~正確さが求められます~
今日は「デコ巻き寿司」をご指導頂きました。講師は「日本デコずし協会 デコ巻き寿司マイスター」の鈴木真由美先生です。

作ったのは「四海巻き」「金魚」です。
正確にすし飯を計量し、パーツを作っていきます。尾びれ、口、背びれとつぎつぎにパーツができあがっていきますが、パーツを見ただけではどのようになるのか見当がつきません。 生徒達も首をかしげ、イメージを膨らませながら、「これはどこの部分かな?」と楽しそうにしていました。
先生のご指導通り、パーツを組み立てていくと何となく形が見えてきます。
実際に切ってみると先生が作った金魚はふっくらと可愛らしい作品で、それを見た生徒達の「私も頑張るー」と一生懸命に取り組む姿はとても微笑ましいものでした。

生徒達の作品はというと・・・ 切ってみるまで分かりません。ワクワクどきどきしますね
鈴木先生、本当にありがとうございました。
校内実習2日目 ~食中毒を撃退しよう!!~
本日は校内実習2日目です。今日は「栃木県保険福祉部生活衛生課」の方々に来て頂き「HACCP-ハサップ」についての講義を実施しました。

世界中で導入されている衛生管理法である「HACCP」についてをグループでの話し合いを通して、実践的に学ぶことができました。

楽しそうに意見を出し合いながらグループワークを行うことができ、「HACCP」が特別なものではなく、誰にでもできる衛生管理であることを理解できた様子です。

美味しいだけでなく、安全で安心な料理を提供できる調理師に近づけたと思います
生活衛生課の方々、本当にありがとうございました。