文字
背景
行間
栃高トピックス
2016年11月の記事一覧
日本学生科学賞 研究内容の紹介
SSHクラブ物理班(物理部)の生徒が研究した作品の内容をupしました。
物理部のページをご覧ください。
物理部のページをご覧ください。
日本学生科学賞 全国入賞確定!!
SSHクラブ物理班(物理部)の生徒たちが県代表として出展した研究作品「フーコーの光速測定の検証」が、中央審査でも高く評価され最終審査に進むことになり全国入賞が確定しました。最終審査には、全国で150近くの作品のうち15作品が選ばれました。最終審査の内容はポスター発表形式で、来月12/22~24まで日本科学未来館で行われます。中でも上位に入れば海外での発表のチャンスもありますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。
修学旅行最終日
いよいよ最終日となりました。
今日は、クラスごとに京都市内の研修を行いました。
1クラスが八ツ橋づくり体験、3クラスが保津川下り、2クラスがトロッコ列車を楽しみました。
八ツ橋は米粉を蒸すところから行い、一人二つの八ツ橋を作りました。
トロッコ列車と保津川下りの船は、偶然にも途中ですれ違い、
お互いに手を振り合う場面もありました。
何人かの生徒は、船頭さんの代わりに櫂を使って舟を漕ぐ体験を
することもできました。
最後は全クラスが嵐山で落ちあい、京都駅に向かいました。
京都駅で解団式を行い、校長先生からお話をいただきました。
そして予定通り小山駅に到着し、それぞれの家路につきました。
終わってみれば、あっという間の4日間でした。
沢山の思い出ができました。それぞれの家庭に戻り、土産話を
してくれる事と思います。
今日は、クラスごとに京都市内の研修を行いました。
1クラスが八ツ橋づくり体験、3クラスが保津川下り、2クラスがトロッコ列車を楽しみました。
八ツ橋は米粉を蒸すところから行い、一人二つの八ツ橋を作りました。
トロッコ列車と保津川下りの船は、偶然にも途中ですれ違い、
お互いに手を振り合う場面もありました。
何人かの生徒は、船頭さんの代わりに櫂を使って舟を漕ぐ体験を
することもできました。
最後は全クラスが嵐山で落ちあい、京都駅に向かいました。
京都駅で解団式を行い、校長先生からお話をいただきました。
そして予定通り小山駅に到着し、それぞれの家路につきました。
終わってみれば、あっという間の4日間でした。
沢山の思い出ができました。それぞれの家庭に戻り、土産話を
してくれる事と思います。
修学旅行第3日目
今日は京都市内の班別研修を行いました。
朝食の後、生徒全員がグループごとにホテルを出発しました。
曇り空でしたが、雨に降られることもなく、研修を行うことができました。
夕方は、大江能楽堂で狂言(附子:ぶす)と能(敦盛:あつもり)を鑑賞して来ました。
解説もついてわかりやすく、日本独自の芸能を十分に楽しむことができました。
何人かの生徒は、能の舞台での立ち振る舞いや、能面を付けるなどの体験も
させていただきました。
夕食後には、先生方が買って来たお土産を商品としてビンゴ大会も行われました。
とても盛り上がりました!
明日は最終日。あと一日です。
朝食の後、生徒全員がグループごとにホテルを出発しました。
曇り空でしたが、雨に降られることもなく、研修を行うことができました。
夕方は、大江能楽堂で狂言(附子:ぶす)と能(敦盛:あつもり)を鑑賞して来ました。
解説もついてわかりやすく、日本独自の芸能を十分に楽しむことができました。
何人かの生徒は、能の舞台での立ち振る舞いや、能面を付けるなどの体験も
させていただきました。
夕食後には、先生方が買って来たお土産を商品としてビンゴ大会も行われました。
とても盛り上がりました!
明日は最終日。あと一日です。
H28 学問探究講義(宇都宮大学)
11/9(水)、1年生を対象に、宇都宮大学の全5学部12学科の先生方をお招きして
学問探究講義を実施しました。
第1部では、各学部代表の5名の先生方にパネルディスカッションの形式で
「大学で学ぶとは」「何かを研究するとは」「文理選択を迎える生徒たちへのアドバイスを一言」
という少し広いテーマでお話をしていただきました。
「学ぼうとするなら、何でも学べるのが大学である」や「何事も興味を持って取り組む」ことが
研究の第一歩であるなど、生徒にわかりやすく具体例を挙げてお話をいただきました。

第2部では、出張講義形式で、12教室に分かれ、大学、学部学科の案内や各先生の研究内容を
かみ砕いて紹介していただくなど、どの教室も活気あふれる講座となりました。
時間を大きくオーバーしての質問にも丁寧に対応していただいた宇都宮大学の先生方には心より
感謝しております。



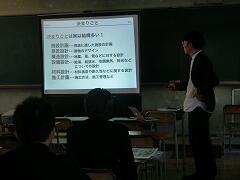


写真は紙面の関係でほんの一部ですが、どの教室を活気あふれる講座となりました。
学問探究講義を実施しました。
第1部では、各学部代表の5名の先生方にパネルディスカッションの形式で
「大学で学ぶとは」「何かを研究するとは」「文理選択を迎える生徒たちへのアドバイスを一言」
という少し広いテーマでお話をしていただきました。
「学ぼうとするなら、何でも学べるのが大学である」や「何事も興味を持って取り組む」ことが
研究の第一歩であるなど、生徒にわかりやすく具体例を挙げてお話をいただきました。

第2部では、出張講義形式で、12教室に分かれ、大学、学部学科の案内や各先生の研究内容を
かみ砕いて紹介していただくなど、どの教室も活気あふれる講座となりました。
時間を大きくオーバーしての質問にも丁寧に対応していただいた宇都宮大学の先生方には心より
感謝しております。



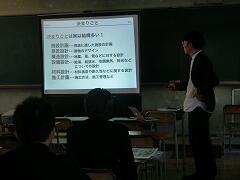


写真は紙面の関係でほんの一部ですが、どの教室を活気あふれる講座となりました。
1999年11月26日開設
7
6
6
5
7
2
8
栃木県立
栃木高等学校
〒328-0016
栃木県栃木市入舟町12-4
TEL 0282-22-2595
FAX 0282-22-2534
※ 画像等の無断転載・引用を禁止します
お知らせ
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1 |
2 | 3 | 4 | 5 2 | 6 1 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 1 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 1 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 1 | 2 2 | 3 2 | 4 1 | 5 | 6 |



