文字
背景
行間
栃高トピックス
行事や部活動の結果などの最新情報です
学会で研究成果を発表(SSHクラブ考古科学班)
SHHクラブ考古科学班は、1年間の研究の成果を5月19日に駒澤大学で行われた日本考古学協会が主催する学会の高校生ポスター発表部門で発表してきました。発表タイトルは、「放射性炭素年代測定による栃木高校所蔵の大型木製遺物の年代推定とその用途に関する考察」で、東京大学と共同で行ったものです。多くの専門家の方に興味を持って頂きました。

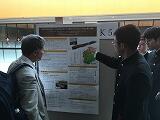

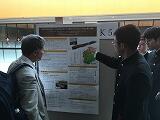
SSH 研究計画書作成講座
5月9日にSSH課題研究の一環として、一年生向けの研究計画書作成講座を行いました。主な内容は、本校教員による講話とマンダラートによる発想法のワークです。
研究のテーマ選びは、課題研究において最も重要な部分です。生徒はまず研究になる題材とそうでないものについて確認し、さらに自分が好きな物から発想して課題を発見するという、研究テーマ選びの方法の一つを学びました。
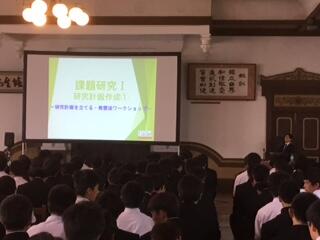
SSHオープニング講座
4月24日に1年生向けSSHオープニング講座として、東京大学の米田穣教授をお招きし、「なんで、高校生は勉強しないといけないか?についての進化的考察」というタイトルでの講演をしていただきました。
「研究」というものがまだまだピンときていない生徒達も「仮説→実験→解析→論文→疑問→仮説」のサイクルで研究が行われることが学べ、徐々に課題研究に向けて取り組む姿勢が出来てきたと思います。
質疑応答の時間も設けられて、先進的な研究を基盤とした科学全般に生徒達がふれる機会となりました。
2019年度入試結果について
大学合格状況を更新しました。大学合格状況
科学研究の手続き体験的に学ぶ~ブラックボックスの中身を想像する~
4月18日に行ったSSH課題研究Ⅰの授業風景です。仲間と協力しながら「決して見ることのできない箱の中身を想像する」という簡単なアクティビティーを行いました。この活動を通して、生徒たちは、「科学的にアプローチする」ということは、「研究者同士で協議・協力しながら、得られた結果を最も合理的に説明するモデルを構築すること」であることを学びました。これから行う各自の研究活動に活かしてほしいと思います。また、2学年の課題研究Ⅱでは、課題研究計画書の作成を各クラスで行いました。




1999年11月26日開設
7
5
5
6
1
7
3
栃木県立
栃木高等学校
〒328-0016
栃木県栃木市入舟町12-4
TEL 0282-22-2595
FAX 0282-22-2534
※ 画像等の無断転載・引用を禁止します
お知らせ
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1 |
2 | 3 | 4 | 5 2 | 6 1 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 1 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 1 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 1 | 2 2 | 3 2 | 4 1 | 5 | 6 |






