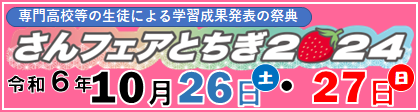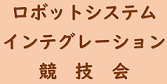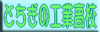文字
背景
行間
カテゴリ:機械科
機械科3年生 課題研究発表会を行いました
12月16日(木)、職場実習を実施していただきました、坂本工業(株) 瀬平様、菊地歯車(株) 永島様にご出席をしていただき、機械科3年1組の課題研究発表会を行いました。
下記の9グループが発表を行いました。
① 資格取得
➁ メダルゲーム機の製作
③ アップサイクルを利用した5S活動
④ ゴム動力自動車の製作
⑤ 3Dプリンタ
⑥ アメフトロボットの製作
⑦ 職場実習 ベンチ・テーブルの製作 坂本工業(株)
⑧ 職場実習 ギヤポンプの製作 菊地歯車(株)
⑨ 高大連携 マイコンカーの製作 足利大学
12月21日(火)、職場実習を実施していただきました、(株)深井製作所 島田様、佐藤金属工業(株) 山﨑様、(株)タツミ 野口様にご出席をしていただき、機械科3年2組の課題研究発表会を行いました。
下記の9グループが発表を行いました。
① 資格取得
➁ 電気自動車の製作
③ スターリングエンジンの製作
④ 3Dプリンタを用いた作品製作
⑤ 5S運動をとおしてのものづくり
⑥ エアホッケーの製作
⑦ 職場実習 (株)深井製作所
⑧ 職場実習 佐藤金属工業(株)
⑨ 高大連携 (株)タツミ

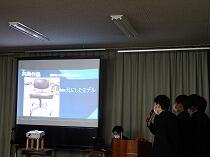

機械科1年生 第12回県高校生溶接コンクールで入賞

両名の頑張りは、夏休みまで遡り、まったく溶接の経験がない二人でしたが、自ら大会出場を志願してきました。それからというもの、猛暑日が続くという過酷な環境にも負けず、皮製のエプロンと手袋の支度で溶接の基本練習と安全作業に黙々と取り組みました。
機械科2年生 アーク溶接特別講習の実施


栃木県溶接協会の講師によるアーク溶接特別講習を、機械科2年生(80名)が受講しました。講習は、学科を2日と実技を1日の計3日間で行われ、全員が無事に終了しました。後ほど、修了証が交付されます。
栃木県高校生電気自動車大会に出場
12月11日(土)栃木市にあるGKNドライブラインジャパン ブルービンググラウンド高速周回路において、栃木県高校生電気自動車大会が行われました。11校から26台のマシンが出場し、40分間の耐久レースで周回数を競います。
本校からは、機械科の課題研究と機械研究部の2チームが出場しました。結果は課題研究は3周、機械研究部は2周でした。両チームとも、準備から本番まで一生懸命取り組んでおり、達成感を感じられる大会になったと思います。


機械科設備 安全点検実施
12月2日(木)、工業科職員にて機械科実習棟の旋盤、フライス盤、溶接機の安全点検・清掃を行いました。本校の施設設備は長く使われているものが多くあり、普段の授業で生徒が安全に実習できるよう、日々メンテナンスを怠らないようにしています。その一環として各学期に2回、定期試験の午後を利用し工業科職員で定期点検を行っています。全体で行うことにより職員の安全に対する意識を高めることにつながっています。
今後も、安全に実習が行える環境・意識づくりに努めていきたいと思います。


機械科でガス溶接技能講習を実施しました
9月25日(土)、26日(日)および10月2日(土)、3日(日)にガス溶接技能講習を実施しました。
機械科2年生80名と他科23名の合計103名が受講しました。
講習は2日間実施され1日目は学科講習、2日目は修了試験と実技講習が行われました。
受講した生徒は器具の取り扱いや構造、危険性などについて学習しました。
機械科1年1組 工業技術基礎
普段の実習では時間に限りがあるため、なかなか細かいところまで清掃が行き届いていない部分がありましたが、本日の活動でより安全に作業しやすい環境が整いました。
2学期以降も清潔な状態を維持しつつ、安全に作業出来るように取り組んでいきたいと思います。


機械科1年生 工業技術基礎
1年生の工業技術基礎では機械仕上げ、計測、手仕上げ、鋳造を行っています。
機械仕上げでは豆ジャッキ、手仕上げでは文鎮、鋳造では表札を製作し、最終的には生徒が持ち帰って使用します。
1.2組とも各班、6週間の1つ目の実習を無事終了しました。
普段の座学とは違い作業着に身を包み、工業人の第1歩を踏み出しました。これからも、引き続き安全に気をつけながら実習に臨んでいきます。

課題研究の1テーマである高大連携がスタートしました(機械科3年)
機械科3年1組3名が、2年ぶり足利大学様のご協力で高大連携プログラムをスタートさせました。大学の研究をとおして専門教科に関する知識・技術を総合的に学習したり、大学生の実態を体験することで将来の進路実現を目指します。研究先は足利大学創生工学科電気電子分野の横山和哉教授で超伝導の研究やマイコンカーの製作をとおして電気の基礎やプログラム等を学習します。これからコロナ感染拡大防止に努めながら7月迄に1週間に1回(6時間)を9回(計54時間)予定しています。


足利大学での様子
課題研究の1テーマである職場実習がスタートしました(機械科3年)


菊地歯車(株) 坂本工業(株)
機械科3年生 課題研究
機械科3年1組が毎週木曜日、機械科3年2組が毎週火曜日に実施しています。
下記に、今年度のテーマを紹介します。
【機械科3年1組】
・職場実習(菊地歯車(株)、坂本工業(株))
・高大連携(足利大学)
・木工製作 ・資格取得 ・3Dプリンタ
・ゴム動力自動車 ・アメフトロボット ・5S活動
【機械科3年2組】
・職場実習((株)深井製作所、佐藤金属工業(株)、(株)タツミ)
・木工製作 ・資格取得 ・3Dプリンタ
・電気自動車 ・5S活動 ・作品製作
機械科3年2組課題研究発表会
①テーブルベンチの製作
➁3Dプリンタ
③リヤカーの製作
④スケートボードセクションの製作
⑤ベンチ製作
⑥エコランカーのフレーム製作
⑦ロボットアメリカンフットボールの製作
⑧調査研究
各グループそれぞれの持ち味が出ていて大変良い発表会になりました。質疑応答では3Dプリンタ、スケートボードセクション、調査研究班等の質問がありました。講評では教頭先生より、自分達が自ら考え工夫して安心安全でより良い作品を製作することが大切である。という話をしていただきました。とても有意義な発表会でした。




機械科2年2組 工場見学
11月27日(金)に機械科2年2組が工場見学を実施しました。新型コロナウイルスの影響で例年6月に実施していたものがこの時期の実施となりました。
群馬県太田市にある、坂本工業(株)を見学させていただきました。自動車の燃料タンクやマフラーなど、私たちの生活に欠かせない製品を製造していることもあり、生徒達も真剣に話を聞いていました。
今後控えている進路選択に向けて、とても貴重な時間になったと思います。
機械科1年2組 工場見学
11月18日(水)に機械科1年2組は工場見学を行いました。例年6月に実施していますが、新型コロナウイルスの影響でこの時期に実施となりました。クラスを半分ずつにわけ、株式会社タツミ様と株式会社進恵技研様のそれぞれ一社ずつを見学させていただきました。
1年生にとって、外部の企業を見学するのは初めての機会だったので、普段の実習では見られない大きな機械や精度の高い製品を目の前にして、驚いた表情をしていました。
見学後には、積極的に質問をしていてとても有意義な時間を過ごせたのではないかと思います。


機械科1年 工業技術基礎
機械科1年2組は毎週水曜日1~3時間目に工業技術基礎を実施しています。
工業技術基礎のテーマの中で、『鋳造実習』があり、今年度初めて「鋳込み」の作業を行いました。
1学期中に、生徒ひとりひとりが製作した表札の木型を用いて砂型を作り、その型に750℃ほどに溶かしたアルミニウムを流し込みました。高温に熱した金属の取扱いなど、危険な作業も伴うので、安全に充分配慮して作業を行いました。
生徒達は、高温になりドロドロに溶けたアルミニウムを見て少し怖さを感じつつも、自分で作製した木型と同じように出来た表札を手にして、喜びを感じていました。

機械科3年1組の実習
毎週火曜日は、機械科3年1組の実習・課題研究となっています。
3年生の実習は、機械加工(旋盤)、原動機、制御、CADの4テーマです。
生徒は、一つ一つの作業に真剣な眼差しで取り組んでいました。


機械加工(旋盤) 原動機(風洞実験)


制御(シーケンス制御) CAD
技能検定3級(普通旋盤作業)に向けて
今年度は、栃木県技能振興コーナーよりものづくりマイスターの堀江辰雄様に講師として来ていただき、より実践的な加工法の指導をしていただいています。
生徒は全員が合格できるように放課後や冬休み、休日等を利用して練習に励んでいます。
この他にも機械科では数多くの資格・検定試験を受験することができます。
一つでも多くの資格・検定試験に合格してもらいたいと思います。




足利市立第二中学校で出前授業を行いました
1年1組32名、1年2組32名、1年3組31名の合計95名の生徒に対して、各クラス1時間ずつ時間をいただき、計測についての授業を行いました。
本校から、機械科2年生の生徒6名も参加し、中学生に一生懸命ノギスの使い方や目盛の読み方などを教えていました。
このような機会を通して、工業に興味をもつ中学生が一人でも多くなってほしいと思います。


機械科2年生 工場見学
令和元(2019)年6月5日(水)に全学年で工場見学が行われました。
機械科2年1組では、午前中にパナソニックAP空調・冷設機器(株)様を、午後は(株)山田製作所様を見学させていただきました。
パナソニックAP空調・冷設機器(株)様では大型空調機器やコールドチェーンの設計・開発・製造工程を見学させていただきました。担当者様による説明会では生徒からも積極的に質問する姿を見ることができました。
(株)山田製作所様では四輪車用機能部品の開発・製造、二輪車用各種機能部品・汎用機能部品・流量測定装置の開発・製造工程を見学させていただきました。工場内では車の模型を使った説明をしていただき、製造している部品が車のどこに使われているのか具体的に説明していただきました。
パナソニックAP空調・冷設機器(株) (株)山田製作所
機械科2年2組では、午前中に坂本工業(株)様を、午後は(株)オギハラ様を見学させていただきました。
坂本工業(株)様では自動車の吸排気系製品、燃料系製品の開発・製造工程を見学させていただきました。特に燃料系製品の「樹脂燃料タンク」は金属製タンクと比べ、錆びず、軽いなど大きなメリットを持つことを説明していただきました。製品紹介の専用展示室があり、実物を見ながらの説明は、より生徒に高い関心を持たせていただきました。
(株)オギハラ様では自動車部品のプレス用金型の設計・製造及びプレス加工の工程を見学させていただきました。金型製造においてはNC工作機械にて型を作成したのち、人の手による金型の研磨、非接触型センサーによる精密な検査など、徹底した作業風景を見学させていただきました。また3000トントランスファープレスの迫力に生徒たちも圧倒されていました。
坂本工業(株) (株)オギハラ
令和元年度栃木県高校生ものづくりコンテスト(機械系部門)
6月8日(土)に、宇都宮工業高校を会場として、令和元年度 栃木県高校生ものづくりコンテスト(機械系部門)が行われました。
このコンテストは、6尺旋盤を使用して与えられた課題図を決められた時間内に完成させ、寸法精度と表面、ねじ部の仕上がり、テーパ部分のあたり等を採点して順位を決めていきます。
今年度は、機械科2年2組 梅木敦盛君が出場しました。課題は、技能検定2級の課題に近い内容となっており、作業時間は2時間30分(打切3時間)でした。
梅木君は、2時間15分ほど作品を完成させました。上位入賞はできませんでしたが、5月から放課後はほぼ練習を行い、コンクール当日も自分の力を十分に発揮していました。
今後の活躍に期待するとともに、一人でも多くの生徒がコンテスト等に参加してほしいと思います。


開会式の様子 作業中の様子①


作業中の様子② 閉会式の様子

完成した作品