文字
背景
行間
定時制の出来事
定時制:県西地区ふれあいキャンプ(栃木県立太平少年自然の家)
県東地区ふれあいキャンプにつづき、3年ぶりの開催となった、令和4(2022)年度不登校児童生徒支援事業(県西地区ふれあいキャンプ)が11月9日(水)~11日(金)の3日間、栃木県立太平少年自然の家(栃木市)で行われ、本校から4名の生徒が“高校生ボランティア”として参加しました。
このふれあいキャンプは、栃木県教育委員会、栃木県市町村教育委員会連合会主催の行事で、「太平周辺の自然を満喫しながら楽しく活動し、心のエネルギーを高める」、「仲間と励まし合いながら、普段できないことに取り組んだり、少し困難なことを乗り越えたりする体験を通して自信をつける」、「新しく出会った仲間や高校生、スタッフとのふれあいを通して、人と関わる心地よさを味わう」という3つの目的が掲げられています。


初日は、“出会いの集い”を行い、昼食をはさんでから、“仲間づくりレクリエーション”と“カードをさがせ!”が行われました。活動班をつくり本校生がリーダーとなって活動していきました。最初は緊張している様子が見られましたが、打ち解けて楽しい雰囲気で活動していました。
夜は、夕食後に、ナイトハイキングを行いました。謙信平から見えた栃木市の夜景はとてもきれいでした。


2日目は“フォトオリエンテーリング”が行われました。マップを見ながら協力して太平山を登りました。
午後は、“クラフト活動「杉板写真かざり」”の制作でした。ガスバーナーで焼きつけて磨き、飾り付けをしました。オリジナルの作品が出来上がりました。
この日の夜は、“高校生主体の交流会”が開かれ、前半はゲームをし、後半は、本校の紹介動画をみてもらい、本校生が学校の様子について話をしました。


最終日は“室内ペタンク”“チャレンジランキング”を行いました。小中学生と協力しながら様々な競技を体験しました。
“別れの集い”では、本校生が一人ずつ感想を発表しました。

天気にも恵まれ、無事に3日間を終えることができました。本校生の活動ぶりはたいへん素晴らしいものでした。参加した生徒には、この経験を通して感じたこと、学んだことを、今後の学校生活に活かしてほしいと思います。
定時制:PTA工房「ZAKKA」開催(「江戸つまみ細工」の製作)
10月27日(木)18:00~ 前日準備
7名の保護者にご来校いただき、当日に向けて準備を行いました。講師の早乙女真由美先生のご指導のもと、布を1辺3cmの正方形に裁断しました。正確に裁断しないと形が整わないため、慎重に作業を進めました。その後、ビーズなどの材料の準備や会場作りを行いました。
10月28日(金)1回目13:30~ 2回目15:45~ 実施当日
講師に早乙女真由美先生、難波千恵子先生、桜井香織先生をお招きし開催しました。新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで、3年ぶりの開催となりました。分かりやすいご指導のもと、はじめて方でも楽しく実施することができました。保護者、教員合わせて、12名の皆さまにご参加いただき、「江戸つまみ細工」を施したかわいいヘアピンやブローチなどを製作することができました。製作した作品は、出藍祭で展示、販売しますので、ぜひお越しください。
実施の様子




定時制:県東ふれあいキャンプ(栃木県芳賀青年の家)
3年ぶりの開催となった、令和4(2022)年度不登校児童生徒支援事業(県東地区ふれあいキャンプ)が10月19日(水)~21日(金)の3日間、栃木県芳賀青年の家(益子町)で行われ、本校から4名の生徒が“高校生ボランティア”として参加しました。
このふれあいキャンプは、栃木県教育委員会、栃木県市町村教育委員会連合会主催の行事で、「美しい秋の風景を楽しみながら、自然の中で楽しく活動し、心のエネルギーをいっぱいにしよう」、「県内各地の仲間や、高校生のお兄さんお姉さん、スタッフの大人たちと協力して活動し、ふれあいながら交流を深めよう」、「仲間とはげましあいながらキャンプをやりとげることで、自信をつけよう」という3つの目的が掲げられました。

キャンプ初日は、まず“出会いの集い”を行い、その後昼食をはさんでから、“仲間づくりレクリエーション”が行われました。お互い初対面で緊張するかと思われましたが、うまくコミュニケーションをとっている印象を強く受けました。
その後、全員で“益子焼づくり(手びねり陶芸)”を行い、各々が個性的な作品を仕上げていました。
2日目は“ウォークラリー”が行われました。各班4~5名に分かれ、それぞれの班で協力しあいながら、途中休憩はあったものの、合計5時間を要する大きなイベントとなりました。ウォークラリーの最中に、高校生が小学生の手をとるような場面もみられ、より絆が深まるきっかけとなりました。
この日の夕方には、“高校生主体の交流会”が開かれ、前半は小中学生に向けて本校の紹介動画をみてもらい、実際に通って感じていることを高校生が話し、後半はおやつを食べながら、高校生が考えてきたゲームを楽しんでいました。
最終日は“カレーづくり”を行いました。班ごとに役割分担をし、どの班もおいしいカレーをつくることができました。
楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、“別れの集い”では、高校生から一緒の活動班だった小中学生1人ずつにメッセージを送りました。小中学生はそれを真剣に聞いている様子で、お互いにとって充実した、かけがえのない3日間になったことと思います。
無事に3日間がおわり、学校に戻ってから、校長先生よりありがたいお言葉をいただきました。参加した4名の生徒には、この経験を通して感じたこと、学んだことを、今後の学校生活に活かしてほしいと思います。
定時制:後期始業式
10月4日(火)、定時制の後期始業式が行われました。
昨年度に続き、今年度もメイン会場をアリーナ、その他校舎内のいくつかの教室に分散して始業式を行いました。
Ⅰ部(午前)が午前11時から、Ⅱ部(午後)・Ⅲ部(夜間)が午後1時20分から開始し、メイン会場以外は、LIVE配信(Ⅰ部)、録画映像(Ⅱ・Ⅲ部)を視聴しました。
はじめに、中塚昌男校長先生から式辞が述べられました。次に、校歌を聴いた後、学習・生徒指導の担当教員から後期の学校生活のアドバイスなどが伝えられました。
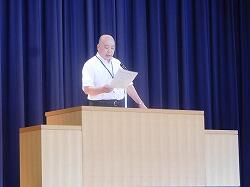

定時制:避難訓練 危機感を持ち速やかに避難
9月28日(水)、4時限目にⅠ部(午前)・Ⅱ部(午後)、9時限目にⅢ部(夜間)の生徒と担当教職員が参加して〝避難訓練〟が行われました。
今年度も、事務室内に設置されている“緊急地震速報”の発報端末を活用。震度5弱の地震を感知したとの想定で訓練がスタートしました。地震発生の直後に調理室から出火。サイレンや発生場所を知らせる自動音声が流れ、緊張感に包まれました。
Ⅰ・Ⅱ部で315名、Ⅲ部で61名が訓練に参加しました。避難指示から7分21秒(Ⅰ・Ⅱ部)、
4分28秒(Ⅲ部)で全員の避難を確認しました。
最後に、中塚校長先生(Ⅰ・Ⅱ部)、菊地教頭先生(Ⅲ部)より講評をいただきました。避難体制の確認や連絡体制の確認の重要性についてなどのお話があり、生徒たちは真剣に聞いていました。


【緊急地震速報】 【初期消火活動】 【火災報知器の発報と避難指示の放送】


【落下物に備える】 【速やかな移動】 【点呼・避難の完了】

【JRC部の提供品】
今日の避難訓練では、JRC部から手作りの『Q救パック』の提供がありました。
生徒の皆さんにとって、防災意識の高揚につながる意義深い〝避難訓練〟となりました。
































