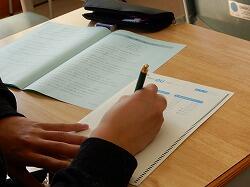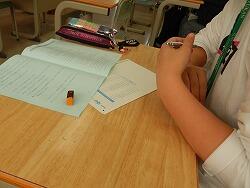文字
背景
行間
定時制の出来事
定時制:給食、大好き![第3回] 〝イタリア料理〟
イタリアを代表する料理には、スパゲティーやラザニア、アクアパッツアなどたくさんあります。今回は、ピザとミネストローネを提供しました。


献立は、ピザトースト、フレンチフライポテト、マカロニサラダ、ミネストローネ、牛乳でした。ピザトーストは、ふわふわの食パンの上にピザソース、ベーコン、野菜、チーズを載せて焼きました。酸味の効いたミネストローネと〝相性ばっちり〟でした。生徒の皆さんからも好評で、食べ残しが少なかったようです。

定時制:全教員が一丸となって「就職試験」対策をサポート
生徒の皆さんは、「就職試験」対策に意欲的に取り組んでいます。10月7日(水)も、模擬面接の練習のために、たくさんの生徒が進路室を訪ねていました。だれもが、『進路用面接ノート』に十分な書き込みをしている様子です。このノートには、面接マナーやたくさんの質問事項、アドバイスが掲載されています。
10月15日(木)には、就職希望の生徒が会議室と視聴覚室に集まり、1回目の〝面接練習会〟が行われます。この場で、面接のトレーニングを積むことになっています。
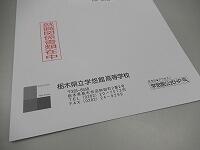


祝! 皆さまに支えられて 来場者数1,250,000名様 達成!
平成29(2017)年4月19日(水)に350,000アクセスに到達。それから1,258日目*で、1,250,000アクセスを突破しました。900,000アクセスを積み上げたことになります。この間、単純平均で1日あたり715アクセスほどを維持しています。おかげさまで、アクセス数は順調に推移しています。
ひとえにご来場くださいます皆さまのお力添えの賜物(たまもの)であると、“チーム学悠館”の教職員一同、改めて心から御礼申し上げます。

*バージョンアップ期間(9日間)を差し引いた日数です。
学悠館高校のホームページの運営の経緯については、これまでも500,000、700,000、1,000,000アクセスなどの節目を突破した時に紹介してきました。
平成17(2005)年の開校と同時に、学校HP(旧HP)を開設しました。さらに、平成24(2012) 年から現在のブログ形式のHPに移行。定時制の生徒もボランティアとして参加した〝蔵の街かど映画祭〟〔平成25(2013)年5月20日〕の記事が最初の掲載でした。しかし、しばらくの間、緊急記事や必掲事項のみが更新される状態となってしまいました。
平成28(2016)年度からは、赴任したばかりの教頭先生を中心に画像付き新着記事を定期的にアップ。また、定時制の旧情報部を中心にデータの更新作業にも積極的に取り組みました。いわば現在のHPの礎(いしずえ)が築かれた時代と言えます。
平成29(2017)年度からは、旧情報部を情報システム係として定時制の教務部に移管する組織の再編が行われました。これを機に、情報システム係を中心に、組織的なHPの運営が始まりました。数次にわたってトップページの更新を重ね、現在のスタイルに至っております。
今後も、定時制・通信制の総力を結集して、授業や各種行事、部活動に取り組む生徒の姿をはじめとした最新情報と魅力を発信し続けてまいります。引き続き、〝学悠館公式HP〟にアクセスくださるようどうぞよろしくお願い申し上げます。また、「YouTube学悠館チャンネル」の再生回数も、しだいに増えてまいりました。こちらの動画も、ぜひご覧くださるようお願いいたします。
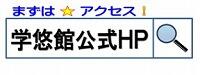

<来場者数と達成日>
350,000名様 平成29(2017)年 4月19日(水)
400,000名様 8月25日(土)
500,000名様 平成30(2018)年 1月23日(火)
600,000名様 5月21日(月)
700,000名様 10月17日(水)
800,000名様 平成31(2019)年 2月19日(火)
900,000名様 令和元年(2019)年 6月29日(土)
1,000,000名様 10月30日(水)
1,100,000名様 令和2(2020)年 3月22日(日)
1,111,111名様 4月 8日(火)
1,200,000名様 7月18日(土)
1,234,567名様 9月13日(日)
1,250,000名様 10月 7日(水)
1,350,000名様 ?????
2,000,000名様 ?????
〝公開授業〟が始まりました。ようこそ学悠館に!
事務室の前で「来校者」シール、関係資料、見取図(時間割付き)を受け取った後、自由に校内をご覧いただきました。また、グラウンドや体育館にも足を伸ばして、体育の授業を見学される方もいらっしゃいました。
担当者に質問する中学生、少人数の授業について興味を抱く中学生、施設の充実ぶりや職員の多さに驚く中学生、部活動を熱心に見学する中学生など、とても積極的にご覧いただきました。ご来校、ありがとうございました。




明日から〝公開授業〟が始まります。
見学を希望された皆様のご来校を心よりお待ちしております。当日は、どうぞお気を付けてお越しください。学悠館高校までのルートは、トップページ-メニューの「交通アクセス」・「栃木駅から学悠館高校まで歩く」でご確認いただけます。
受付は、事務室窓口の前です。来校される際には、マスク着用、手指消毒、事前の体温測定などのご協力をお願いいたします。
学悠館高校では、〝公開授業〟とは別に、令和3(2021)年1月末までの間に、平日・土曜・日曜の〝校内見学会・授業見学会・進学相談会〟も計画しております。こちらの参加のお申込みも受け付けております。どうぞ電話にて、定時制・通信制の「入試担当」までお問い合わせください。

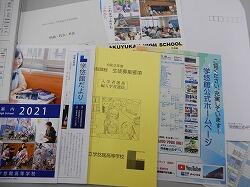
【受付(事務室窓口前)】 【お配りする資料】
定時制:給食、大好き![第2回] 〝お月見メニュー〟
献立は、コーンライス、月見うさぎハンバーグ、マセドワンサラダ、キャベツスープ、牛乳でした。月見うさぎハンバーグは、うさぎの形をしたハンバーグに濃厚なデミグラスソースをかけ、月に見立てた目玉焼きをトッピングしています。卵、人参、コーン、キャベツ、しめじなど、今日もたくさんの食材を使用した献立でした。


昔から日本では、十五夜に月を眺めたり、農作物の収穫に感謝をして月見団子やススキなどをお供えしたりする風習があります。
食堂に飾っているススキには、悪霊や災いから収穫物を守り、翌年の豊作を願う意味が込められています。

定時制:『保健だより』(10月号)が発行されました。
『保健だより』(10月号)が発行されました。
今月号のトップ記事では、感染症の影響によって延期された歯科検診・眼科検診の新たな実施日時をお知らせしています。クラスごとの検診日時などの詳細は、HR担任から伝えられることになっています。
10月号も、「インフルエンザ予防接種」、「10月10日は目の愛護デー」、「お手軽ファッション?要注意!」、「薬に頼りすぎない生活を!」など、ぜひとも目を通しておきたい内容ばかりです。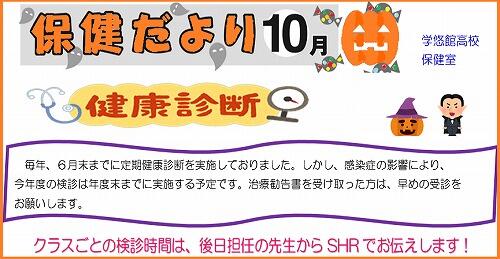
生徒の皆さんには、10月2日(金)から配付されています。
保護者の皆さまも、お子様をとおして手にされてどうぞご覧ください。〝Message from 学悠館〟の画像を更新しました。
いよいよ10月6日(火)から「公開授業」が始まります。10日(土)を除いて、通信制のスクーリングの行われる11日(日)までの予定で実施されます。この期間だけで、すでに50組ほどの見学のお申込みをいただいております。ありがとうございます。
「公開授業」だけでなく、令和3(2021)年1月末までの間に、平日・土曜・日曜の校内見学会・授業見学会・進学相談会も計画しております。こちらの参加のお申込みもお待ちしております。どうぞ電話にて、お問い合わせください。
定時制:後期始業式 気持ちを新たに後期スタート!
例年は、生徒・教職員あわせて700名近くが出席し、アリーナを会場に一堂に会したスタイルで実施されていました。しかし、今回は、メイン会場のアリーナのほか、校舎内のいくつかの教室に分散して始業式に臨むことになりました。
Ⅰ部(午前)が午前11時から、Ⅱ部(午後)・Ⅲ部(夜間)が午後1時20分からそれぞれ開始。メイン会場以外は、LIVE配信を視聴しました。



【〝後期始業式〟のメイン会場(アリーナ)】
はじめに、中塚昌男校長先生から式辞が述べられました。次に、〝YouTube学悠館チャンネル〟の校歌“君にエールを”を視聴。この後、学習・生徒指導の担当教員から後期の学校生活のアドバイスなどが伝えられました。



【LL教室】 【コンピュータ教室】 【文書処理教室】


【映像「式次第」】 【地学教室】 【マーケティング教室】

【会議室】 【視聴覚教室】 【映像「校歌〝君にエールを〟」】
始業式が終わった後は、LHRの時間。前期の成績の記された『通知票』が、生徒の皆さんに手渡されていました。HR担任による激励のことばに、大きくうなずいている様子でした。
『通知票』をクラスメートと見せ合う生徒、良い成績を見て思わずほほ笑む生徒、少し反省気味の生徒……。それぞれの教室では、ほのぼのとした時間が流れていました。



【2Cクラス】 【30Bクラス】 【2Hクラス】 【2Mクラス】
定時制:LHR(1~3年次): 「hyperQU調査」 実施
9月30日(水)、4・9時限目のLHRの時間に、1~3年次の生徒の皆さんが「hyperQU調査」に取り組みました。この調査では、生徒の皆さんがどのような気持ちで学校生活を送っているか、十分に満足しているかなどの「学校生活満足度」が測定されます。分析結果は、生徒の皆さん一人ひとりに寄り添ったさまざまな支援に役立てられます。
「hyperQU調査」は、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」として、これまでは年間2回、5月と12月に実施されてきました。しかし、通常授業の再開された時期を考慮して、本年度は1回のみ実施することとなりました。